近年、精神疾患を抱えながらも働き続ける方が増えており、その中で障害年金の受給を検討される方も多くなっています。2025年は障害年金制度にとって重要な転換点となっており、実に40年ぶりとなる制度改正が検討されています。令和7年度の障害年金額も1.9%引き上げられ、1級で年額1,039,625円、2級で年額831,700円となりました。
多くの方が「働いていると障害年金は受給できない」と誤解されていますが、実際には精神疾患者の約34.8%が就労しながら障害年金を受給しています。これは約3人に1人の割合で、決して珍しいケースではありません。重要なのは、働いているかどうかではなく、日常生活や就労においてどの程度の支援や配慮が必要かという点です。
精神疾患の特性上、症状の波があったり、職場での特別な配慮が必要だったりする場合があります。そうした状況では、経済的な安定を図りながら継続的に治療を受け、社会参加を続けるために障害年金が重要な役割を果たします。本記事では、働きながら障害年金を受給するための具体的な方法や注意点について詳しく解説します。

精神疾患があっても働きながら障害年金を受給することは可能ですか?
はい、精神疾患があっても働きながら障害年金を受給することは十分可能です。障害年金の受給要件には「働けない」ことは明記されておらず、実際に多くの精神疾患者が就労と年金受給を両立しています。
障害年金制度では、働いているかどうかよりも、日常生活や就労においてどの程度の制限があるかが重要な判断基準となります。たとえば、職場で特別な配慮を受けている、家族の全面的なサポートがあって初めて働けている、症状の波があるため安定した就労が困難、といった状況であれば、働いていても障害年金の対象となる可能性があります。
統計データを見ると、精神障害者の34.8%が就労しながら障害年金を受給しており、これは身体障害者の48.0%、知的障害者の58.6%と比較すると低い数値ですが、それでも相当数の方が両立を実現しています。精神疾患の場合、症状の不安定性や職場での理解不足などの理由で就労率が相対的に低くなっていますが、適切な支援があれば働き続けることは可能です。
重要なポイントは、働き方の質や職場での配慮の内容です。フルタイムで健常者と同様に働いている場合と、時短勤務や在宅ワーク、業務内容の調整など特別な配慮を受けて働いている場合では、障害の程度の評価が異なります。また、収入額についても明確な基準はなく、月収が一定額以上あるから受給できないということはありません。
ただし、20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金については所得制限があります。年所得が462万1,000円を超えると全額支給停止、360万4,000円を超えると2分の1支給停止となりますので、この点は注意が必要です。
対象となる精神疾患は幅広く、統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、PTSD、発達障害、認知症、てんかんなど多岐にわたります。診断名だけでなく、その疾患によってどのような日常生活上の制限があるかが重要な判断材料となります。
働きながら障害年金を申請する場合、どのような条件や審査基準がありますか?
働きながら障害年金を申請する場合の審査では、就労状況と日常生活能力の両面から総合的に判断されます。単に働いているという事実だけでなく、どのような条件や配慮のもとで働いているかが重要な評価ポイントとなります。
基本的な受給要件は以下の3つです。まず初診日要件として、障害の原因となった病気について初めて医師の診療を受けた日に、国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。次に保険料納付要件として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間で保険料が納付または免除されていることが求められます。最後に障害認定日要件として、障害認定日または20歳に達したときに、障害の状態が1級から2級(厚生年金は3級も含む)に該当することが必要です。
就労状況の評価基準では、勤務形態、労働時間、勤務日数、職場での配慮や支援の有無、業務内容の複雑さ、職場での人間関係やストレス要因などが詳しく調査されます。たとえば、正社員として働いていても、実際は時短勤務で単純作業のみを担当し、上司や同僚の特別な配慮を受けている場合と、フルタイムで責任のある業務を任されている場合では、評価が大きく異なります。
日常生活能力の評価も同様に重要で、家事や身辺処理の自立度、金銭管理能力、服薬管理の状況、対人関係の維持能力、社会生活への適応度などが総合的に判断されます。働いていても、家族の全面的な支援がなければ日常生活が成り立たない場合や、症状の波があるため継続的な就労が困難な場合は、障害年金の対象となる可能性が高くなります。
2016年から導入された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」により、認定基準が明確化されました。1級では「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」、2級では「日常生活が著しい制限を受ける程度」、3級では「労働が著しい制限を受ける程度」と定義されています。
具体的な評価ポイントとして、職場での配慮内容(勤務時間の調整、業務内容の簡素化、人事的配慮、産業医や保健師との連携など)、家族や支援者からのサポート内容、通院頻度や服薬状況、症状の変動パターンなどが詳細に検討されます。
重要なのは、働いているから軽度、働いていないから重度という単純な判断ではないということです。どのような支援や配慮があって初めて働けているのか、その人の全体的な生活状況はどうかという観点から、総合的に障害の程度が判定されます。
2025年の制度改正で精神疾患者の障害年金受給はどう変わりますか?
2025年は障害年金制度にとって歴史的な転換点となっています。厚生労働省から40年ぶりとなる制度改正法案が打ち出され、精神疾患者の障害年金受給に大きな影響を与える変更が予定されています。
令和7年度の年金額改定では、前年度に比べて1.9%の引き上げが行われました。障害基礎年金1級で年額1,039,625円(月額86,635円)、2級で年額831,700円(月額69,308円)となり、これは令和7年4月分から適用されます。また、障害年金生活者支援給付金も1級で月額6,813円、2級で月額5,450円が上乗せされ、前年の所得が一定額以下の場合に支給されます。
制度改正の主要ポイントは4つあります。第一に初診日要件の緩和で、これまで厳格だった初診日の証明について、より柔軟な取り扱いが検討されています。第二に後発的障害制度の改善により、複数の障害を併発した場合の取り扱いが改善される予定です。第三に法定免除期間の取扱い改善で、保険料納付要件の判定がより公平になります。第四に所得との調整の在り方の検討が行われ、働きながらの受給についてより適切な制度設計が目指されています。
精神疾患者への具体的な影響として、特に注目すべきは初診日要件の緩和です。従来、会社勤務中に精神を病んで退職後に医療機関を受診した場合、障害基礎年金のみの受給となっていました。しかし、改正により障害厚生年金の受給が可能になる可能性があります。これは受給額の大幅な増加につながる重要な変更です。
働きながらの受給への影響も大きく、より柔軟な就労支援制度との連携が図られる予定です。段階的な就労復帰への支援強化、企業の障害者雇用促進制度との連動など、社会復帰を支援する仕組みが充実される見込みです。
ただし、改正の対象は新規受給者のみで、現在の受給者には直接適用されない予定です。しかし、制度全体への影響は大きく、既存受給者にも間接的な影響が予想されます。審査基準の統一化、地域格差の是正、支援体制の充実などにより、より公平で持続可能な制度が構築される期待があります。
新制度への準備として、現在受給を検討している方は、改正内容を踏まえた申請戦略を立てることが重要です。また、既存受給者も制度変更の動向を注視し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。
この制度改正により、精神疾患者がより安心して働き続けられる環境が整備され、社会参加と経済的自立の両立が実現されることが期待されています。
障害年金の申請手続きと必要書類について教えてください
障害年金の申請手続きは複雑ですが、適切な準備と段階的な進め方により、スムーズに進めることができます。特に働きながらの申請では、就労状況を正確に伝えることが重要なポイントとなります。
申請の基本的な流れは以下の通りです。まず事前相談として、年金事務所や市区町村窓口で相談を行います。この段階で、受給要件を満たしているか、どのような書類が必要かを確認します。次に必要書類の準備を行い、すべての書類が揃ったら正式な申請を行います。その後審査期間(通常3~6ヶ月)を経て、結果通知が届きます。
必要書類は以下の8つが基本となります。年金請求書(国民年金・厚生年金保険用)、診断書(精神の障害用・様式第120号の4)、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書(初診時と現在の医療機関が異なる場合)、住民票、戸籍謄本、年金手帳または基礎年金番号通知書、預金通帳等です。
診断書作成のポイントは特に重要です。主治医との連携において、初診日、生活歴、通院歴、発育歴、学歴、職歴、現在の就労形態、月収の概算、職務内容などを明確に伝える必要があります。診断書には現在の精神状態の詳細、日常生活能力の程度、就労状況と職場での配慮、服薬状況と治療効果、今後の見通しなどが記載されます。
病歴・就労状況等申立書は自分で作成する書類で、障害年金の認定において極めて重要です。発病から現在までの経過、各時期の症状と日常生活への影響、就労状況の変化、受けている支援や配慮、困っていることや制限されていることを詳細に記載します。この書類は、診断書だけでは表現しきれない日常生活の実態を伝える重要な手段です。
働きながら申請する場合の特別な注意点として、職場での配慮や支援の具体的な内容を詳しく記載することが重要です。勤務時間の調整、業務内容の簡素化、上司や同僚からの理解と支援、産業医との面談、通院のための休暇取得など、働き続けるために必要な配慮を具体的に説明します。
申請時期の選択も重要で、症状が安定している時期よりも、日常生活や就労に支障をきたしている時期に申請することが有利です。ただし、障害認定日(初診日から1年6か月後)から申請が可能で、遡及請求により過去の分も受給できる場合があります。
専門家の活用も検討すべきポイントです。社会保険労務士に依頼することで、書類作成の負担軽減と受給可能性の向上が期待できます。費用はかかりますが、複雑な手続きを適切に進めるためには有効な選択肢です。
申請から結果が出るまでの期間は通常3~6ヶ月ですが、書類に不備があったり、追加資料が必要な場合はさらに時間がかかることがあります。焦らず、確実に手続きを進めることが重要です。
働きながら障害年金を受給する際の更新手続きや注意点は何ですか?
働きながら障害年金を受給する場合、定期的な更新手続きと継続的な状況管理が重要になります。更新時には就労状況の変化が大きく影響するため、適切な準備と対応が必要です。
更新手続きの基本的な仕組みでは、障害年金は原則として1~5年ごとに更新手続きが必要です。更新期間は初回認定時に決定され、年金証書に記載されています。更新時期が近づくと、日本年金機構から現況報告書や診断書の提出案内が届きます。これらの書類を指定期限までに提出しなければ、年金の支給が停止される可能性があります。
就労状況の変化への対応が最も重要なポイントです。更新時に就労している場合、職場からの特別な配慮を受けていることや、周囲のサポートを受けて働けている状況を診断書で正確に伝える必要があります。就労状況が改善した場合は障害等級の変更(軽度化)や年金額の減額、場合によっては支給停止の可能性があります。逆に就労状況が悪化した場合は障害等級の変更(重度化)や年金額の増額、額改定請求の検討が必要になります。
更新時の診断書作成における注意点として、現在の障害状態だけでなく、日常生活で不便に感じていることや困っていることも診断書に記載してもらうよう、主治医とコミュニケーションを取り、情報共有しておくことが重要です。働いていても、どのような配慮や支援があって初めて働けているのかを具体的に記載してもらいます。
職場での配慮内容の記録も継続的に行う必要があります。勤務時間の調整、業務内容の配慮、人事担当者の理解と協力、産業医や保健師との連携などを具体的に記録し、更新時の参考資料として活用します。また、家族や支援者からの日常生活での支援内容も記録しておくことが重要です。
症状の変動への対応では、精神疾患の特性上、症状に波があることが多いため、調子の良い時期と悪い時期の両方を記録しておくことが大切です。更新時期が調子の良い時期に重なった場合でも、普段の状況を正確に伝えられるよう準備しておきます。
更新手続きで注意すべき具体的なポイントとして、提出期限の厳守、診断書の記載内容の確認、現況報告書の正確な記入、必要に応じた追加資料の準備などがあります。特に、就労状況に変化があった場合は、その理由や背景を詳しく説明する必要があります。
更新結果への対応も重要です。等級が下がったり支給停止になった場合は、不服申立て(審査請求)を行うことができます。審査請求は結果通知から3か月以内に行う必要があり、新たな医学的証拠や生活状況の資料を提出することで、決定の見直しを求めることができます。
継続受給のための日常的な注意点として、定期的な通院の継続、服薬管理の徹底、症状や生活状況の記録、職場との良好な関係維持、家族や支援者との連携などがあります。これらの取り組みにより、安定した受給継続と就労継続の両立が可能になります。
専門家との継続的な関係も重要で、社会保険労務士や精神保健福祉士などの専門家と定期的に相談し、制度の変更や個人の状況変化に適切に対応していくことが、長期的な安定受給につながります。


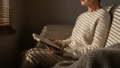
コメント