住宅ローンは人生における大きな決断の一つですが、その申請過程で精神疾患に関する診断書の提出を求められ、不安や戸惑いを感じている方も少なくありません。近年、団体信用生命保険(団信)の審査において、精神疾患の治療歴や通院歴がある場合に診断書の提出が必要となるケースが増加しています。しかし、診断書の提出を求められたからといって、必ずしも住宅ローンが組めないわけではありません。重要なのは、正しい知識を持ち、適切に対応することです。精神疾患があっても利用できるワイド団信やフラット35などの選択肢も存在し、多くの方が実際に住宅ローンを組んで夢のマイホームを実現しています。本記事では、診断書提出を求められた際の具体的な対応方法、審査に通過するためのポイント、利用可能な制度や選択肢、そして注意すべき法律上の義務について、実例を交えながら詳しく解説します。住宅ローンと精神疾患という繊細なテーマについて、冷静かつ実践的な情報を提供し、あなたの住宅購入の実現をサポートします。
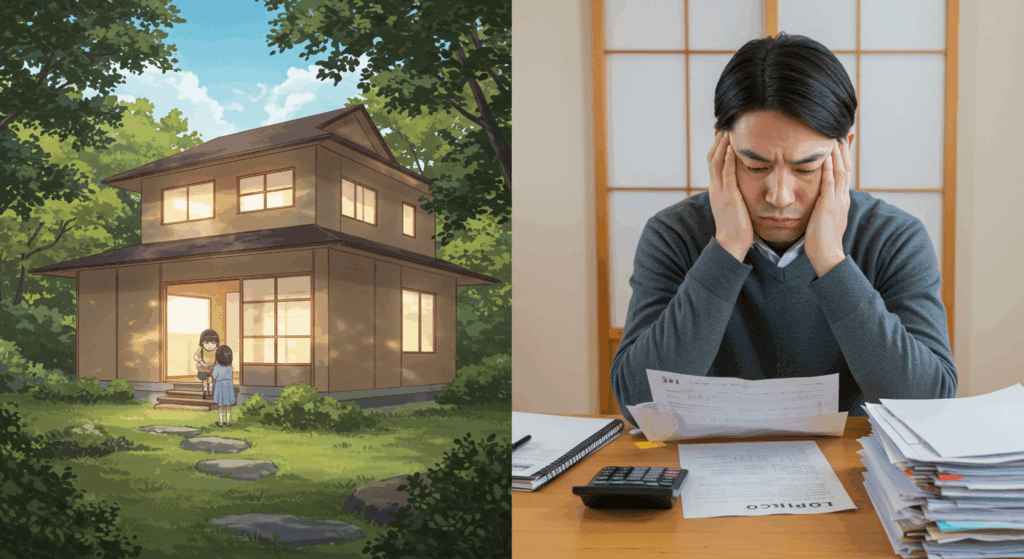
診断書提出が求められる理由と背景
住宅ローンを申し込む際、ほとんどの金融機関では団体信用生命保険への加入が必須条件となっています。団信は、万が一契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、残りのローン残高を保険金で完済する仕組みであり、金融機関にとっても借り手にとっても重要な保障制度です。この団信の審査において、精神疾患に関する診断書の提出が求められる場合があります。
診断書の提出が必要となる主なケースとして、まず借入金額が1億円を超える高額融資の場合が挙げられます。通常、1億円以下の借り入れであれば告知書への記入のみで審査が進められますが、高額な借り入れの場合は医師による正式な診断書が必要となることがあります。次に、告知書に記載した内容について保険会社がさらに詳細な情報を必要と判断した場合です。特に精神疾患の通院歴や治療歴がある場合、その症状の程度や現在の健康状態を正確に把握するために診断書の提出を求められます。また、がん保障特約や三大疾病保障特約などの特約を付与する場合にも、より詳しい健康情報の提出が求められることがあります。
精神疾患に関しては、うつ病、適応障害、パニック障害、双極性障害、統合失調症などが告知の対象となります。これらの疾患は再発のリスクや治療の長期化が懸念されるため、保険会社は慎重に審査を行います。うつ病は精神病に該当し、過去3年以内に2週間以上の通院や投薬があった場合は告知事項として詳細に申告しなければなりません。保険会社は、告知内容に基づいて審査を行い、場合によっては診断書や医療機関への照会を行うことがあります。診断書の提出要請は必ずしも審査に落ちることを意味するわけではなく、より正確な情報に基づいて公平な審査を行うための手続きであると理解することが大切です。
診断書提出を求められた場合の正しい対応手順
診断書の提出を求められた場合、まず冷静に対応することが何より重要です。焦りや不安から適切な対応ができなくなると、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。診断書の提出は、保険会社があなたの健康状態をより正確に把握し、適切な保険商品を提案するための手続きです。
最初のステップとして、金融機関または保険会社から指定された書式や必要な記載事項を確認します。診断書には特定の書式が指定されている場合と、主治医が自由形式で作成する場合があります。どのような情報が必要とされているのかを正確に把握することで、スムーズな手続きが可能になります。次に、現在通院している医療機関、または過去に治療を受けた医療機関に診断書の作成を依頼します。この際、住宅ローンの団信審査のために必要であることを明確に伝えましょう。
診断書に記載してもらうべき情報は多岐にわたります。病名と診断日については、正式な病名と最初に診断された時期を明記してもらいます。治療の経過に関しては、いつから治療を開始し、現在どのような状態にあるのか、症状の改善の過程、薬の変更履歴、治療方針の変更などを時系列で記載してもらいます。投薬の状況については、現在服用している薬の種類と量、過去の服薬歴、薬の減量や中止の経過も含めて記載してもらいます。症状の程度については、日常生活や就労への影響の有無、症状の重症度について具体的に記載してもらいます。そして今後の見通しとして、完治の見込み、治療の継続期間の予測、再発のリスク評価などを記載してもらいます。保険会社はこの部分を特に重視するため、可能な限り前向きな内容を、ただし正確に記載してもらうことが重要です。
診断書の作成には通常1週間から2週間程度かかります。医療機関によっては、さらに時間がかかる場合もあるため、早めに依頼することが重要です。また、診断書の作成には費用がかかります。医療機関によって異なりますが、一般的に3,000円から10,000円程度の文書料が必要となります。診断書が完成したら、内容を自分でも確認してから提出します。記載内容に誤りがないか、必要な情報がすべて含まれているかをチェックしましょう。
診断書作成時に主治医に伝えるべきこととして、診断書の使用目的が住宅ローンの団信審査のために必要であることを明確に伝えます。保険会社から指定された項目があれば、事前に主治医に伝えます。現在の良好な状態を適切に記載してもらうために、日常生活で問題なく過ごせていること、仕事にも支障がないこと、症状が安定していることなどを具体的に伝えます。ただし、虚偽の内容を記載するよう依頼することは絶対に避けなければなりません。これは告知義務違反となり、後述する深刻な結果を招きます。
告知義務について理解する
住宅ローンの団信加入時には、告知義務という法律上の義務があります。これは、自分の健康状態について正確に申告する義務のことで、非常に重要です。告知義務を正しく理解し、誠実に対応することが、長期的な安心につながります。
告知義務違反とは、事実と異なる内容を申告したり、重要な事実を隠したりすることを指します。具体的には、現在治療中の疾患を申告しない、過去の通院歴を隠す、服薬している薬について申告しない、症状を実際より軽く申告するなどの行為が該当します。告知義務違反が発覚した場合、深刻な結果を招きます。
まず、保険契約が無効になります。団信契約そのものが無効とされ、保険金が支払われなくなります。また、住宅ローン契約の解除を求められる可能性があります。金融機関によっては、団信加入を前提としたローン契約であるため、契約違反として一括返済を求められることがあります。さらに、詐欺罪に問われる可能性もあります。悪質な場合は刑事責任を問われることもあり得ます。
告知義務違反は、保険金請求時に発覚することが多いです。万が一の際に保険会社が医療機関に照会を行い、告知内容との相違が明らかになります。特に、精神疾患が死因に関わっていた場合、保険会社に提出する死亡診断書に記載されることになり、そこで告知内容との相違が発覚する可能性が高くなります。そのため、短期的には審査に通ったとしても、長期的には大きなリスクを抱えることになります。
告知期間の基準としては、多くの保険会社では過去3年以内の治療歴を確認します。この期間内に通院や投薬があった場合は必ず申告する必要があります。一方で、完治から3年以上が経過し、その間に一切の治療や投薬がなければ、告知する必要がない場合もあります。告知が必要となる具体的な治療内容としては、心療内科や精神科への通院、抗うつ薬や抗不安薬などの精神科系の薬の処方、カウンセリングやデイケアなどの治療プログラムへの参加、精神疾患による休職や入院の経験などが含まれます。
告知は必ず正直に行うべきです。一時的に審査が厳しくなったとしても、正確な情報を提供することで、適切な保険商品や代替案を提案してもらえる可能性があります。虚偽の申告は短期的な解決にしかならず、長期的には自分自身や家族を危険にさらすことになります。
精神疾患がある場合の住宅ローン選択肢
精神疾患の診断を受けている、または通院歴がある場合でも、住宅ローンを組むための選択肢は複数存在します。自分の状況に最も適した方法を選ぶことで、マイホームの夢を実現できる可能性が高まります。
ワイド団信の利用
ワイド団信とは、引受基準緩和型の団体信用生命保険のことで、一般的な団信よりも加入条件が緩和されています。通常の団信では加入が難しい高血圧症、糖尿病、うつ病などの持病がある人でも加入できる可能性があります。正式には引受基準緩和型団体信用生命保険と呼ばれます。
ワイド団信のメリットとしては、精神疾患の治療中でも加入できる可能性がある、通常の団信で断られた場合の代替手段となる、住宅ローンを諦めずに済むという点が挙げられます。一方でデメリットとしては、金利が通常より0.2から0.3パーセント程度上乗せされる、すべての精神疾患が対象となるわけではない、審査基準は保険会社によって異なるという点があります。
ワイド団信の審査基準は、病名だけで判断されるものではありません。お客様の年齢、性別、症状、治療歴などの詳細を記入した申込書兼告知書兼同意書の内容等に基づき、保険会社が総合的に審査を行います。そのため、同じ病名の方であっても、加入できる場合と加入できない場合があります。どの程度の症状であれば加入できるのか明確な条件が公表されていないため、実際に申し込んでみないと加入可能かどうかが分かりません。
ワイド団信を取り扱っている主な金融機関には、住信SBIネット銀行、イオン銀行、auじぶん銀行、ソニー銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行などがあります。金融機関によって審査基準や保障内容が異なるため、複数の金融機関を比較検討することが推奨されます。
審査に通りやすくするポイントとしては、症状が安定していることを示す医師の診断書を用意する、日常生活や就労に支障がないことを証明する書類を準備する、治療経過が良好であることを示す資料を提出する、現在の収入が安定していることを示す書類を充実させるなどが挙げられます。実際に、PayPay銀行などの金融機関では、うつ病があった顧客でも実際に加入できた事例があることを公表しています。
フラット35の活用
フラット35は、住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利型の住宅ローンで、最大の特徴は団信への加入が任意である点です。団信に加入できない場合でも住宅ローンを組むことができるため、精神疾患がある方にとって有力な選択肢となります。
フラット35のメリットとしては、団信に加入できなくても住宅ローンを組める、全期間固定金利で返済計画が立てやすい、保証料が不要、繰り上げ返済手数料が無料という点があります。デメリットとしては、団信に加入しない場合、万が一の際の保障がない、他の生命保険で代替する必要がある、金利が変動金利型より高めに設定されている、物件の技術基準を満たす必要があるという点があります。
フラット35を利用する場合は、別途、収入保障保険や定期保険などの生命保険に加入することで、万が一の際の保障を確保することが推奨されます。精神疾患があっても加入できる生命保険も存在するため、保険の専門家に相談することをお勧めします。
配偶者名義での申し込み
配偶者が健康で、安定した収入がある場合、配偶者を主債務者として住宅ローンを申し込むという方法があります。この方法のメリットは、配偶者が健康であれば通常の団信に加入できる、金利の上乗せなどの追加コストが発生しない、審査がスムーズに進む可能性が高いという点です。ただし、配偶者の収入のみで希望額を借りられない可能性がある、離婚などの際に権利関係が複雑になる、配偶者に万が一のことがあった場合のリスクが大きいというデメリットもあります。
完治を待つという選択肢
精神疾患が完治し、一定期間が経過すれば、団信の審査に通りやすくなります。一般的には、完治から3年以上経過していることが一つの基準とされています。完治後の経過年数による審査への影響は大きく、完治から3年以上経過している場合は、告知義務の対象外となる可能性があります。つまり、治療が終了してから3年以上が経過し、その間に一切の治療や投薬がなければ、精神疾患の履歴がなかったものとして審査を受けられる場合があります。
完治から1年から3年の場合は、告知は必要ですが、完治していることと経過が良好であることを示すことで審査に通る可能性があります。特にワイド団信であれば、この期間でも加入できる可能性が高まります。完治から1年未満の場合は、一般的な団信の審査は厳しくなります。この場合、ワイド団信への申し込みやフラット35の利用を検討することが現実的です。
この選択肢のメリットは、通常の団信に加入できる可能性が高まる、金利の上乗せなどの追加コストがかからない、心身ともに安定した状態で住宅購入ができるという点です。デメリットとしては、住宅購入の時期が遅れる、その間に金利や物件価格が変動する可能性がある、ライフプランの変更が必要になるという点があります。
診断書の内容が審査に与える影響
診断書に記載される内容によって、審査の結果は大きく変わります。審査で重視されるポイントを理解しておくことで、適切な診断書を準備することができます。
まず、現在の治療状況が重視されます。現在も治療中である場合は審査が厳しくなる傾向があります。一方、治療が終了している場合は、終了からの経過年数が重要な判断材料となります。症状の程度も重要な要素です。日常生活や就労に支障がない程度の症状であれば、比較的審査に通りやすくなります。逆に、入院歴がある、休職した経験がある、日常生活に大きな支障があるという場合は、審査が厳しくなります。
投薬の状況も審査に影響します。薬の種類や量、服薬期間などが評価の対象となります。抗うつ薬や抗不安薬などの長期服用は、審査において慎重に検討されます。再発のリスクも考慮されます。過去に何度も再発している場合や、主治医が再発リスクが高いと判断している場合は、審査が厳しくなる可能性があります。
診断書の記載で避けるべき表現としては、曖昧な表現(「おそらく」「かもしれない」など)、過度に否定的な将来予測、不必要に詳しい過去の悪化時の症状描写、再発リスクを強調しすぎる表現などがあります。逆に、審査に有利となる可能性がある記載内容としては、「症状は安定しており、日常生活に支障はない」「現在は投薬も終了し、経過観察中である」「再発予防のため定期的にフォローアップしているが、現状は良好である」「就労にも問題なく、社会生活を送れている」などの表現が挙げられます。
診断書を作成してもらう際には、主治医に対して正確な情報を伝えつつ、現在の良好な状態や回復の経過についても適切に記載してもらうよう依頼することが大切です。ただし、繰り返しになりますが、虚偽の記載を依頼することは絶対に避けなければなりません。
金融機関との交渉と相談のポイント
診断書の提出を求められた場合、金融機関との適切なコミュニケーションが重要です。誠実かつ戦略的な対応が、審査通過の可能性を高めます。
まず、事前相談を積極的に行いましょう。本審査の前の事前審査の段階で、精神疾患の通院歴があることを相談することで、金融機関側から適切なプランを提案してもらえる可能性があります。担当者に対しては、現在の症状の状態、治療の経過、就労への影響の有無などを正直に伝えましょう。
複数の金融機関に相談することも有効です。金融機関によって審査基準は異なります。A銀行で断られても、B銀行では承認されるケースもあります。ネット銀行、地方銀行、都市銀行など、異なるタイプの金融機関に相談することで、選択肢が広がります。
住宅ローンの専門家に相談することも検討しましょう。ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー、モーゲージバンカーなどの専門家は、精神疾患がある場合の住宅ローン選びについて豊富な知識と経験を持っています。どの金融機関が精神疾患のある人に対して柔軟な審査を行っているか、どのような書類を準備すればよいか、審査に通りやすくするためのアドバイスなどを提供してくれます。
不動産会社の提携ローンも活用できる場合があります。不動産会社は多くの住宅ローン事例を扱っているため、精神疾患がある人でも利用できる金融機関の情報を持っていることがあります。ただし、不動産会社の提携ローンは選択肢が限られる場合もあるため、自分でも複数の金融機関を調査することが重要です。
診断書以外に準備すべき書類
診断書以外にも、審査をスムーズに進めるために準備しておくべき書類があります。事前に必要な書類を揃えておくことで、審査期間を短縮し、スムーズな手続きが可能になります。
収入関連の書類としては、源泉徴収票(会社員の場合)、確定申告書(自営業の場合)、課税証明書、給与明細書(直近数ヶ月分)などが必要です。勤務関連の書類としては、健康保険証、在籍証明書、雇用契約書などが求められることがあります。物件関連の書類としては、売買契約書、重要事項説明書、物件の登記簿謄本、建築確認済証などが必要となります。
その他の書類としては、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、住民票、印鑑証明書、預金通帳のコピーなどが必要です。精神疾患に関連して追加で準備しておくとよい書類としては、診療明細書(過去の治療履歴がわかるもの)、お薬手帳のコピー、職場の就労証明書(安定して就労していることを証明)、主治医からの意見書(診断書とは別に、日常生活に支障がないことを証明する書類)などがあります。
特に、安定した就労状況を示す書類は重要です。精神疾患があっても安定して働いており、収入が継続的に得られることを証明できれば、審査において有利に働きます。在籍証明書や直近の給与明細書などを準備しておきましょう。
審査に落ちた場合の次のステップ
診断書を提出したにもかかわらず審査に落ちた場合でも、諦める必要はありません。次のステップを踏むことで、住宅ローンを組める可能性は十分にあります。
まず、審査に落ちた理由を確認しましょう。金融機関は詳しい理由を教えてくれないことが多いですが、可能な範囲で情報を収集します。精神疾患が理由なのか、収入面での問題なのか、借入金額が大きすぎたのかなど、原因を推測することが次のステップにつながります。
他の金融機関に申し込むことも検討しましょう。審査基準は金融機関ごとに異なるため、A銀行で落ちてもB銀行では通る可能性があります。特にワイド団信を扱っている金融機関や、フラット35を取り扱っている金融機関に申し込むことを検討します。
借入金額を見直すことも有効です。希望する借入金額を減らすことで、審査に通る可能性が高まります。頭金を増やす、物件価格を見直すなどの対応を検討しましょう。返済期間を短くすることも一つの方法です。返済期間を短くすることで、金融機関のリスクが減り、審査に通りやすくなる場合があります。
連帯保証人や連帯債務者を立てることも検討できます。親族などに連帯保証人になってもらうことで、審査に通る可能性が高まります。配偶者との収入合算や、ペアローンの活用も選択肢となります。時間を置いて再申請することも考えられます。治療が進んで症状が改善した、完治から一定期間が経過したなどのタイミングで再度申請することで、審査結果が変わる可能性があります。
精神疾患を持つ人が住宅ローンを組む際の注意点
精神疾患を持ちながら住宅ローンを組む場合、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解し、適切に対応することで、長期的な安心を確保できます。
返済計画は余裕を持って立てましょう。精神疾患は再発のリスクがあり、症状が悪化した場合には就労が困難になる可能性もあります。返済額は収入の25パーセント以内に抑える、ボーナス払いは避けるか少額にする、緊急時のための貯蓄を確保するなどの対策が重要です。無理のない返済計画を立てることで、精神的な負担を減らし、症状の安定にもつながります。
団信に加入しない場合の代替保障を確保しましょう。フラット35などで団信に加入しない場合は、別途生命保険に加入することが重要です。収入保障保険、定期保険、就業不能保険などを検討し、万が一の際の保障を確保します。精神疾患があっても加入できる保険商品も存在するため、保険の専門家に相談しましょう。
定期的な健康管理を継続しましょう。症状の安定を維持するために、定期的な通院を続ける、処方された薬を正しく服用する、ストレス管理を行う、十分な睡眠と休息を取るなどの健康管理が重要です。住宅ローンの返済は長期にわたるため、継続的な健康管理が不可欠です。
職場の理解とサポートを得ることも大切です。必要に応じて職場に病状を伝え、理解を得ておくことで、万が一症状が悪化した場合にも柔軟な対応が可能になります。家族との情報共有も重要です。配偶者や家族に病状や治療状況を共有し、万が一の際の対応を話し合っておくことが大切です。
返済中に精神疾患を発症した場合の対応
住宅ローンの返済中に精神疾患を発症した場合にも、適切な対応方法があります。この状況は決して珍しいことではなく、多くの人が経験しています。パニックにならず、冷静に対処することが重要です。
まず行うべき対応としては、速やかに医療機関を受診し、適切な治療を開始することが最優先です。早期治療により、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることができます。金融機関への相談も重要です。返済が困難になる前に、早めに金融機関に相談しましょう。多くの金融機関では、病気や怪我により返済が困難になった場合の救済措置を用意しています。
利用可能な制度としては、返済期間の延長があります。毎月の返済額を減らすために、返済期間を延長することができる場合があります。返済猶予も選択肢の一つで、一定期間、返済を猶予してもらえる制度です。通常、元金の返済を一時停止し、利息のみの支払いとする場合が多いです。条件変更も可能な場合があります。ボーナス払いの取りやめ、返済額の一時的な減額などの条件変更を申し出ることができます。
公的支援制度の活用も検討しましょう。傷病手当金は、健康保険に加入している会社員が病気で休業した場合、給与の約3分の2が最長1年6ヶ月間支給される制度です。精神疾患も対象となります。障害年金は、精神疾患により日常生活や就労に著しい制限がある場合、障害年金の受給資格がある可能性があります。自立支援医療制度を利用することで、精神科の通院治療費の自己負担額を軽減できます。
住宅ローンと精神疾患に関する法律と権利
住宅ローンの審査において、精神疾患を理由とした差別は禁止されていますが、団信の審査は保険契約の一部であり、健康状態に基づく審査は正当なものとされています。この法律と権利の関係を理解しておくことが重要です。
障害者差別解消法との関係では、2016年に施行された障害者差別解消法により、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されています。ただし、合理的な理由がある区別は差別にあたらないとされています。住宅ローンの審査において、精神疾患があることのみを理由に一律に融資を拒否することは差別にあたる可能性があります。一方、団信の審査において、保険数理に基づき健康状態を考慮することは合理的な区別とされています。
個人情報保護法との関係では、精神疾患に関する情報は「要配慮個人情報」に該当し、特に慎重な取り扱いが求められます。金融機関や保険会社は、本人の同意なく精神疾患の情報を取得、利用、提供することはできません。診断書の提出や医療機関への照会には、必ず本人の同意が必要です。申込書や告知書には、通常、医療機関への照会に同意する旨の条項が含まれています。
告知義務と人権のバランスについて、団信の告知義務は保険契約の公平性を保つために必要とされていますが、過度な情報提供の強制は人権侵害にあたる可能性があります。必要最小限の情報のみを告知すればよく、関係のない過去の病歴まで詳細に申告する必要はありません。告知書で尋ねられている範囲内の情報を正確に提供することが求められます。
審査結果に不服がある場合の対応としては、審査に落ちた理由の開示を求めることができます。ただし、金融機関には詳細な理由を開示する義務はありません。明らかに不当な差別と思われる場合は、金融機関の相談窓口や消費者センターに相談することができます。法的措置を検討する場合は、弁護士に相談し、障害者差別解消法や個人情報保護法に違反していないかを確認します。
完治後の審査通過事例と成功のポイント
精神疾患が完治した後、一定期間が経過してから住宅ローンを申し込むことで、審査に通過した事例は数多く存在します。希望を持って、適切なタイミングで申し込むことが重要です。
完治の判断基準としては、医師が完治または寛解と診断していること、投薬や通院が終了していること、再発の兆候がないこと、日常生活や就労に支障がないことなどが重要な要素となります。主治医から完治証明書を取得することが有効です。完治した時期、治療内容、現在の状態、再発リスクの評価などを記載してもらいましょう。
実際の審査通過事例としては、うつ病が完治して3年経過後に一般団信で審査通過したケース、適応障害が完治して2年経過後にワイド団信で審査通過したケース、パニック障害が完治して5年経過後に通常の住宅ローンで審査通過したケースなどが報告されています。これらの事例は、完治後の適切なタイミングで申し込むことで、精神疾患の履歴があっても住宅ローンを組めることを示しています。
金融機関への説明方法も重要です。完治した時期を明確に伝え、完治後の経過年数を強調します。治療中の状況と完治後の改善を具体的に説明し、再発防止のために行っている生活習慣の改善などについても言及します。現在の安定した就労状況と収入を強調することで、返済能力に問題がないことをアピールします。完治後の健康状態を示す資料として、定期的な健康診断の結果、就労状況を示す在籍証明書や給与明細、日常生活に支障がないことを示す書類などを準備します。
まとめ:住宅ローンと精神疾患の診断書提出について
住宅ローン申請時に精神疾患に関する診断書の提出を求められることは、決して珍しいことではありません。重要なのは、正直に対応し、適切な選択肢を選ぶことです。診断書の提出を求められたら、まず冷静に対応し、必要な情報を正確に提供しましょう。告知義務を守り、虚偽の申告は絶対に避けることが、長期的な安心につながります。
精神疾患があっても、ワイド団信、フラット35、配偶者名義での申し込み、完治を待つなど、複数の選択肢があります。自分の状況に最も適した方法を選びましょう。金融機関との事前相談を積極的に行い、複数の金融機関を比較検討することが成功への近道です。必要に応じて、ファイナンシャルプランナーなどの専門家のアドバイスを受けることも有効です。
一つの金融機関で審査に落ちたとしても、諦めずに他の選択肢を探ることが大切です。借入金額の見直しや、時間を置いての再申請なども検討しましょう。住宅ローンを組んだ後も、無理のない返済計画、適切な保障の確保、継続的な健康管理が重要です。家族との情報共有や、職場の理解を得ることも、長期的な安定につながります。
精神疾患があるからといって、マイホームの夢を諦める必要はありません。正しい知識と適切な対応で、住宅ローンを組むことは十分に可能です。焦らず、自分に合った方法を見つけて、着実に進めていきましょう。診断書の提出は、より適切な保険商品や金融商品を選ぶための一つのプロセスです。前向きに捉え、専門家のサポートを受けながら、理想の住まいを手に入れてください。


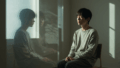
コメント