場面緘黙症で日常生活や学業、就労に困難を抱えている方にとって、精神障害者保健福祉手帳の取得は重要な選択肢となります。この手帳を取得することで、税制上の優遇措置や公共交通機関の運賃割引、障害者雇用枠での就職機会、さらには各種福祉サービスの利用など、多岐にわたる支援を受けることができるようになります。しかし、場面緘黙症で障害者手帳を取得するためには、いくつかの条件と基準を満たす必要があります。症状が日常生活や社会生活にどの程度影響を及ぼしているのか、初診日からの経過期間はどれくらいか、継続的な医療を受けているかなど、様々な要素が総合的に判断されます。本記事では、場面緘黙症の方が精神障害者保健福祉手帳を取得するための具体的な条件や基準、申請方法、手帳取得後に利用できるサービスについて詳しく解説していきます。手帳の取得を検討されている方やそのご家族にとって、有益な情報となるよう、実践的な内容をお届けします。

場面緘黙症の基本的な理解
場面緘黙症は選択性緘黙とも呼ばれており、家庭では自然に話せるにもかかわらず、学校や職場など特定の社会的状況になると話すことができなくなる症状を指します。この症状は単なる人見知りや恥ずかしがり屋とは本質的に異なるものです。本人は話したいという意思を持っているにもかかわらず、話せないという状態が1か月以上継続するのが特徴です。この症状はアメリカ精神医学会の診断基準であるDSM-5において不安症のカテゴリに属しており、精神保健医療の対象となる疾患として位置づけられています。
診断基準としては、まず他の状況では話しているにもかかわらず、話すことが期待されている特定の社会的状況において話すことが一貫してできないことが挙げられます。次に、その障害が学業上、職業上の成績、または対人的コミュニケーションを妨げていることが条件となります。さらに、その障害の持続期間が少なくとも1ヶ月であることが求められますが、学校の最初の1ヶ月だけに限定されないことが重要です。また、話すことができないことは、その社会的状況で要求される話し言葉の知識や話すことに関する楽しさが不足していることによるものではなく、コミュニケーション症や自閉スペクトラム症、統合失調症、または他の精神病性障害ではうまく説明されないことが必要です。
場面緘黙症に共通している特徴として、話せる場面とそうでない場面の区別がはっきりしていること、話せない状態が月単位や年単位で長く続くこと、その場所ではリラックスできる状態にあっても話すことができないという点が挙げられます。人見知りや恥ずかしがり屋の場合は慣れれば徐々に話せるようになりますが、場面緘黙症では特定の場面での発話が全くない状態が1か月以上続くという明確な違いがあります。家では普通に会話ができ、むしろおしゃべりな子どもであることも珍しくありません。このような症状の特性を理解することが、適切な診断と支援につながります。
場面緘黙症の原因については特定されていませんが、様々な要因が絡み合って発症すると考えられています。元々不安を感じやすい性格や発達に偏りのある子どもが、入園や入学などによる大きな環境の変化や人前で話す機会が増加して不安が高まるなど、複数の要因が重なった結果として発症するのではないかと言われています。なお、トラウマが場面緘黙症の原因であるというエビデンスはなく、保護者の育て方が原因ではありません。生まれ持った気質や環境要因などが複合的に関係していると考えられています。日本における出現率は0.2から0.5パーセント以下とされており、決して珍しい症状ではありません。
場面緘黙症の治療アプローチ
場面緘黙症は脳の損傷や先天的異常などの不可逆的で恒久的な器質障害ではなく、社交不安症の一つとして考えられる症状です。したがって適切な治療的介入を行えば症状の改善が可能であるとされています。この点は、障害者手帳の等級判定において重要な考慮要素となります。現在日本で最も効果的とされているのは行動療法的アプローチです。この方法は、呈示された問題を習慣的な行動と理解し、生活に適応する行動を学ぶことで改善を目指すものです。家庭でできているコミュニケーションを家庭外に徐々に広げていき、話せる範囲を段階的に拡大していくことが治療の主軸となります。
具体的な治療法として、エクスポージャー療法が広く用いられています。この療法は段階的に不安場面に慣れていく方法であり、本人との信頼関係を築き、心理教育を実施した後に認知行動療法の治療が展開されます。個人のニーズに応じて様々な技法が組み合わせられるため、一人ひとりの状況に合わせた柔軟な対応が可能です。また、系統的脱感作法も効果的な治療法として知られています。これは不安を引き起こす状況に徐々に慣れることで、話すことへの抵抗を減らしていく方法です。小さな成功体験を積み重ねていくことで、自信をつけていくことができます。
認知行動療法は、不安を引き起こす思考パターンや行動パターンを修正し、特定の状況における話すことへの恐怖を徐々に克服していく治療法として、効果的なアプローチであることが認められています。この治療法では、本人が持っている否定的な思考や信念を検討し、より現実的で適応的な考え方に修正していくプロセスが含まれます。さらに、家族療法も重要な役割を果たします。家族の協力を得て支援的な環境を作ることが治療の効果を高めるため、家庭、学校、医療機関の連携が成功の鍵となります。
必要に応じて薬物療法が補助的に用いられる場合もあります。抗不安薬や抗うつ薬が処方されることがありますが、これは症状を和らげる補助的な役割を担うものであり、主たる治療は行動療法的アプローチです。治療は個別化されるべきであり、専門家の指導のもとで複数の方法を組み合わせることが推奨されます。重要なのは、無理に話させようとする働きかけは逆効果であり、本人のペースを尊重した段階的なアプローチが必要であるという点です。この治療方針は、学校や職場における合理的配慮の提供においても基本的な考え方となります。
障害者手帳制度の概要
障害者手帳とは、障害のある方が取得できる手帳の総称です。手帳には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。場面緘黙症の方が取得できる可能性があるのは、精神障害者保健福祉手帳です。この手帳は精神障害がある方を対象としており、精神疾患による初診日から6ヶ月以上経過していることが申請の条件となります。この6ヶ月という期間は、症状の経過を十分に観察し、適切な診断を行うために必要な期間として設定されています。
精神障害者保健福祉手帳の対象となる疾患は幅広く、統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、発達障害、高次脳機能障害などが含まれます。場面緘黙症は発達障害者支援法の対象となっており、2011年の障害者基本法の改正により、発達障害も精神障害者保健福祉手帳の対象となる可能性が開かれました。不安症のカテゴリに属する場面緘黙症も、生活に著しい支障がある場合には手帳取得の対象となり得ます。この点は、場面緘黙症で困難を抱えている方にとって重要な選択肢となっています。
精神障害者保健福祉手帳には1級から3級までの等級があり、等級は障害の程度によって決定されます。1級は日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものであり、具体的には常に他者の援助を必要とする状態を指します。2級は日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものです。必ずしも他者の援助を必要としない場合でも、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の状態を含みます。3級は日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものであり、労働が著しい制限を受ける場合などが該当します。
場面緘黙症の場合、多くは2級か3級に該当すると考えられますが、個々の状況によって判断が異なります。症状の重症度、社会生活への影響の程度、併存する障害や疾患の有無、治療の経過と予後などを総合的に評価して判定が行われます。手帳の等級によって利用できるサービスや受けられる支援の内容が異なるため、正確な評価と判定が重要となります。また、手帳を持つことで不利益が生ずることはなく、障害が軽減すれば手帳を返すことや、更新を行わないこともできるという柔軟性があります。
障害者手帳取得の条件と基準
場面緘黙症で精神障害者保健福祉手帳を取得するための基本的な条件は明確に定められています。第一に、精神障害による初診日から6ヶ月以上経過していることが必須です。初診日とは、障害の原因となった病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日を指します。この期間は症状の経過を観察し、継続的な治療の効果を評価するために必要とされています。短期間での症状の変化ではなく、長期的な視点での評価が求められるのです。
第二に、症状が日常生活や社会生活に制限を及ぼしていることが必要です。単に話せないというだけでなく、学業や就労、対人関係に実際に支障が出ていることが求められます。具体的には、学校での授業参加が困難である、職場でのコミュニケーションが取れない、必要な場面で意思表示ができないなど、社会生活における実質的な困難さが評価されます。この評価においては、どの程度の場面で話せないのか、症状の範囲と程度が詳細に検討されます。
第三に、医師による診断書が必要です。場面緘黙症であることを証明する診断書を、精神科や心療内科などの医療機関で作成してもらう必要があります。診断書には、症状の詳細、日常生活や社会生活への影響、治療経過などが詳しく記載されます。医師は診察を通じて、本人の状態を総合的に評価し、障害の程度を判断します。第四に、継続的な治療を受けていることが望ましいです。医療機関で定期的に診察を受け、治療を続けていることが評価の対象となります。
判定基準としては、症状の重症度が重要な要素となります。場面緘黙症の場合、どの程度の場面で話せないのか、症状の範囲と程度が評価されます。家庭内でのみ話せる状態なのか、特定の親しい人とのみ話せるのか、あるいはほとんどの社会的場面で話せないのかなど、症状の広がりが考慮されます。次に、社会生活への影響が判断材料となります。学校や職場での活動、対人関係への影響がどの程度あるかが重要です。教育や就労に著しい支障が生じている場合は手帳取得の可能性が高まります。
また、併存する障害や疾患も考慮されます。場面緘黙症に加えて不安障害やうつ病などを併発している場合、それらも含めて総合的に判断されます。複数の症状が重なることで、日常生活への影響がより大きくなっている場合があります。さらに、治療の経過と予後も評価対象です。治療を受けても改善が見られない場合や、長期的な支援が必要と判断される場合には手帳取得の可能性が高まります。一方で、治療により症状が改善傾向にあり、近い将来に支障がなくなると予測される場合は、判定に影響を与える可能性があります。
これらの要素を総合的に評価して、最終的な判定が行われます。判定は都道府県の精神保健福祉センターなどで行われ、専門家による慎重な審査を経て決定されます。同じ診断名であっても、個々の状況によって等級が異なることがあるため、正確で詳細な情報提供が重要となります。
申請手続きの具体的な流れ
精神障害者保健福祉手帳の申請は、お住まいの区市町村の福祉担当窓口で行います。申請方法には2通りの方法があり、多くの場合は診断書による申請が用いられます。一つ目は診断書による申請であり、この場合は障害者手帳申請書と医師が作成した診断書を提出します。診断書は初診日から6ヶ月以上経過してから作成される必要があり、この期間を経過していない場合は申請することができません。また、顔写真1枚が必要です。写真はたて4センチメートル、よこ3センチメートルで、1年以内に撮影されたものを用意する必要があります。
二つ目は障害年金証書による申請です。精神障害を理由とする障害年金を受給している場合は、診断書の代わりに年金証書及び直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写しと同意書を提出することができます。この方法は、すでに障害年金を受給している方にとって、診断書作成の費用負担を軽減できるメリットがあります。平成28年1月以降の申請では、申請書にマイナンバーを記載する必要があります。そのため、個人番号カードなど、マイナンバーを確認できる書類の持参が必要です。
申請書類を提出すると、都道府県の精神保健福祉センターなどで審査が行われます。審査では提出された診断書の内容をもとに、障害の程度が判定されます。審査期間は通常2か月程度です。紙形式の手帳の場合は約2か月、カード形式の場合は約2か月半かかります。自治体によって審査期間は異なる場合があるため、申請時に確認することをおすすめします。審査の結果、手帳の交付が認められた場合は、申請した区市町村の窓口で手帳を受け取ることができます。
手帳には氏名、生年月日、障害等級、交付年月日、有効期限などが記載されています。手帳の有効期間は2年間です。継続して手帳を使用したい場合は、有効期限の3か月前から更新手続きを行うことができます。更新の際も新たに診断書の提出が必要です。この更新制度により、障害の状態が変化した場合には等級の見直しが行われることになります。症状が改善している場合には等級が下がる可能性があり、逆に悪化している場合には等級が上がる可能性もあります。
申請時には、症状の詳細や日常生活への影響を医師に正確に伝えることが重要です。場面緘黙症は外見からは分かりにくい症状であるため、どのような場面でどのような困難があるのかを具体的に説明する必要があります。医療機関を選ぶ際には、場面緘黙症や不安障害の治療経験が豊富な医師を選ぶことが望ましいです。継続的に通院し、医師との信頼関係を築くことで、より正確な診断書が作成されることになります。
手帳取得後に利用できるサービス
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、さまざまなサービスや支援を受けることができます。2025年4月からは特に交通機関の割引が拡充されるなど、利用できるサービスが広がっています。これらのサービスは、手帳を持つことの大きなメリットとなっており、日常生活の質の向上に貢献します。
税制上の優遇措置として、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。等級によって控除額が異なり、1級の場合は特別障害者として控除額が大きくなります。相続税の控除や、1級の方の場合は自動車税、自動車取得税の軽減も受けられる場合があります。これらの税制優遇は、本人だけでなく扶養している家族にとっても経済的な負担を軽減する効果があります。確定申告や年末調整の際に、手帳の写しを提出することで控除が適用されます。
公共交通機関の運賃割引も利用できます。2025年4月1日からは、JRで精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介護者1名までの運賃が5割引きとなりました。これは精神障害者にとって大きな前進であり、移動の自由が広がることになります。全国ほとんどのタクシーで1割引が適用され、バス会社によってはバス運賃の割引も受けられます。航空会社の多くが国内線に限って航空券の3割から5割引を実施しています。これらの交通機関の割引は、通院や通学、就労などの日常的な移動だけでなく、旅行やレジャーの際にも活用できます。
公共施設の利用料金の減免も受けられます。美術館、博物館、動物園、水族園などの公共施設の入場料が無料または割引になることがあります。各種公共施設や宿泊施設でも手帳を提示することで割引料金や無料で利用できる場合があります。レジャー施設では、ラウンドワンのスポッチャがクラブ会員価格で利用できるなど、民間施設でも割引が広がっています。これらの施設利用の割引は、文化的な活動や余暇活動を楽しむ機会を増やすことにつながります。
携帯電話料金の割引サービスを提供している通信事業者もあります。携帯会社各社では精神障害者手帳の交付を受けている方を対象に基本使用料などが割引になる制度を設けています。現代社会において携帯電話は必需品であり、この割引は日常的な経済負担の軽減に役立ちます。NHKの受信料については、世帯の構成員に精神障害者手帳を持っている方がおり、世帯全員が市町村民税非課税だと全額免除となります。
生活福祉資金の貸付制度を利用できる場合もあります。ネットスーパーやクリーニングといった民間の生活サービスの中には、独自で障害者向けの割引や特典サービスを展開しているものもあります。これらの日常的なサービスの割引は、生活の質を向上させるとともに、経済的な負担を軽減する効果があります。
また、障害者雇用枠での就職が可能になります。企業には一定割合の障害者雇用が義務付けられているため、手帳を持っていることで就職の選択肢が広がります。手帳所持者を事業者が雇用した際には障害者雇用率へのカウントとなり、障害者職場適応訓練の実施などの支援も受けられます。さらに、障害福祉サービスを利用できるようになります。就労移行支援、就労継続支援、自立訓練などのサービスを受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳を持つことで不利益が生ずることはありません。また、障害が軽減すれば手帳を返すことや、更新を行わないこともできます。利用の際は各自治体や事業者によってサービス内容が異なるため、事前に確認することをおすすめします。手帳を取得したからといって、必ずしもすべてのサービスを利用する義務はなく、必要なサービスを選んで利用することができます。
大人の場面緘黙症と就労支援
場面緘黙症は子どもの疾患と思われがちですが、大人になっても症状が続く場合や、大人になってから顕在化する場合もあります。大人の場面緘黙症では、職場でのコミュニケーションに困難を抱えることが多くあります。電話応対ができない、会議で発言できない、上司や同僚との会話ができないなど、就労上の課題が生じます。これらの困難は、キャリア形成や職場での評価に影響を与える可能性があり、深刻な問題となることがあります。
精神障害者保健福祉手帳を取得することで、障害者雇用枠での就職が可能になります。障害者雇用では、企業側が障害特性を理解した上で雇用するため、一般雇用よりも働きやすい環境が整備されている場合があります。具体的には、電話応対を免除してもらう、筆談やメールでのコミュニケーションを認めてもらう、会議での発言を強制されないなど、個々の状況に応じた配慮を受けることができます。企業は障害者雇用促進法により、従業員の一定割合を障害者として雇用することが義務付けられているため、障害者雇用枠は安定した就職の機会となります。
また、就労移行支援事業所などを利用することで、就職に必要なスキルを身につけたり、職場実習を経験したりすることができます。専門スタッフのサポートを受けながら就職活動を進めることができます。就労移行支援では、ビジネスマナーやパソコンスキルなどの職業訓練だけでなく、自分の障害特性を理解し、適切に説明するスキルを身につけることもできます。職場実習を通じて、実際の職場環境で自分がどのように働けるかを確認することも可能です。
就職後も、就労定着支援などのサービスを利用して、長期的な就労継続のための支援を受けることが可能です。就労定着支援では、定期的に職場を訪問して就労状況を確認したり、職場との調整を行ったりします。困難が生じた際には、早期に対応することで、離職を防ぐことができます。また、ハローワークには障害者専門の窓口があり、障害特性に配慮した職業相談や職業紹介を受けることができます。
場面緘黙症の方が就労する際には、自分の症状や必要な配慮について、あらかじめ企業に伝えることが重要です。どのような場面で話せないのか、どのようなコミュニケーション方法であれば可能なのかを具体的に説明することで、企業側も適切な配慮を提供しやすくなります。障害者雇用においては、オープンな対話を通じて、お互いに働きやすい環境を作っていくことが大切です。
障害年金との関係
場面緘黙症の方は、障害者手帳だけでなく障害年金の対象になる場合もあります。障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類が決まります。初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が対象となります。障害厚生年金の場合は、障害基礎年金に上乗せして支給されるため、受給額が大きくなります。
障害年金を受給するためには、初診日に年金に加入していること、保険料納付要件を満たしていること、障害認定日に障害の状態が一定以上であることが必要です。保険料納付要件とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることです。ただし、令和8年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいという特例があります。
場面緘黙症の場合、症状の程度や日常生活への影響の度合いによって、障害年金の対象となるかどうかが判断されます。特に就労が困難であったり、日常生活に著しい制限がある場合には、障害年金の受給が認められる可能性があります。障害年金の等級は1級から3級まであり、1級は日常生活に著しい支障がある状態、2級は日常生活に大きな支障がある状態、3級は労働に著しい制限がある状態を指します。なお、障害基礎年金には3級がなく、1級と2級のみです。
障害年金の申請には、初診日を証明する書類や診断書が必要です。場面緘黙症で障害年金を申請する場合は、精神の障害用の診断書を使用します。診断書には、日常生活能力の判定や日常生活能力の程度、就労状況などが詳しく記載されます。障害年金の申請は複雑であるため、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効です。障害年金を受給している場合は、精神障害者保健福祉手帳の申請時に、診断書の代わりに年金証書を使用することができます。
障害年金と障害者手帳は別の制度であり、どちらか一方を受けているからといって、もう一方が自動的に認められるわけではありません。しかし、両方を申請することは可能であり、それぞれの制度のメリットを受けることができます。障害年金は経済的な支援として、障害者手帳は各種サービスや支援を受けるためのツールとして、それぞれ異なる役割を果たします。
手帳取得のための医療機関の選び方
精神障害者保健福祉手帳の申請には医師の診断書が必要です。場面緘黙症の診断と診断書の作成ができる医療機関を選ぶことが重要です。精神科、心療内科、児童精神科などの医療機関を受診しますが、場面緘黙症は不安症のカテゴリに属するため、不安障害の治療経験が豊富な医師を選ぶとよいでしょう。医療機関を選ぶ際には、ホームページで専門分野を確認したり、電話で問い合わせたりすることをおすすめします。
初診時には、どのような場面で話せないのか、いつから症状が始まったのか、日常生活や学業、就労にどのような支障があるのかなどを詳しく伝えます。場面緘黙症は症状が目に見えにくいため、具体的なエピソードを交えて説明することが効果的です。たとえば、学校では一言も発することができない、職場での電話応対が全くできない、必要な場面で助けを求めることができないなど、実際の困難を具体的に伝えることが重要です。可能であれば、メモを用意して診察に臨むとよいでしょう。
継続的に通院し、医師との信頼関係を築くことが大切です。場面緘黙症は症状の評価が難しい場合があるため、複数回の診察を通じて医師が症状を把握することが重要です。医師は診察を重ねることで、本人の状態をより正確に理解し、適切な診断書を作成することができます。通院の際には、症状の変化や日常生活での困難について、継続的に報告することが望ましいです。
診断書の作成を依頼する際には、手帳申請のためであることを明確に伝えます。診断書には、症状の詳細、日常生活や社会生活への影響、治療経過などが記載されます。医師によっては、手帳申請用の診断書作成に慣れていない場合もあるため、どのような内容が必要かを確認することも有効です。診断書の作成には費用がかかりますが、この費用は医療機関によって異なります。一般的には数千円から1万円程度です。
また、場面緘黙症は大人になってから診断を受ける場合もあります。子どもの頃から症状があったものの、当時は診断されていなかったというケースも少なくありません。そのような場合でも、現在の症状と過去の経過を詳しく説明することで、診断を受けることができます。家族や学校の先生などから、子どもの頃の様子について情報を得ておくと、診断の際に役立ちます。
手帳取得が難しい場合の支援制度
場面緘黙症の症状があっても、すべての方が精神障害者保健福祉手帳を取得できるわけではありません。症状が軽度で日常生活への影響が少ない場合や、特定の場面に限定されていて社会生活全般には支障がない場合などは、手帳の取得が認められないことがあります。また、初診日から6ヶ月未満の場合は申請できません。十分な治療期間と経過観察が必要とされるためです。
手帳の取得が難しい場合でも、自立支援医療制度を利用できます。自立支援医療の精神通院医療は、精神疾患のために通院による医療を継続して受ける必要がある方の医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。てんかんも含まれます。制度の対象となる医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになります。通常の健康保険では3割負担ですが、この制度を利用すると1割負担に軽減されます。さらに、世帯の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられます。所得の低い方や重度かつ継続の方については月あたりの負担額に上限が設定されています。
受給者証の有効期間は1年です。継続して利用する場合は更新が必要です。申請は、お住まいの区市町村の窓口で行います。主な必要書類は自立支援医療申請書、医師の診断書、加入医療保険の状況が分かるもの、マイナンバーが分かるものです。診断書は作成日から3か月以内に申請する必要があります。申請に基づく審査を行い、認定された場合は、都知事から自立支援医療受給者証が交付されます。月額負担上限額が設定された方には、自己負担上限額管理票を受給者証と併せてお渡しします。
また、合理的配慮を求めることもできます。障害者差別解消法により、障害のある方への合理的配慮の提供が義務付けられています。改正障害者差別解消法は2024年4月1日に施行され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。この法律の事業者には、企業、団体、店舗などが含まれ、営利、非営利、個人、法人を問わず、同じサービスを繰り返し継続する意思をもって行う者が対象となります。個人事業主やボランティア活動グループも含まれます。
学校も事業者に該当するため、教育現場での合理的配慮の提供義務があります。手帳がなくても、医師の診断書などをもとに配慮を求めることができます。雇用分野においては、障害者雇用促進法により、2016年4月から障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮の提供が義務化されています。就労場面でも適切な配慮を受ける権利があります。合理的配慮とは、障害のある方が障害のない方と平等に権利を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害や困難さを取り除くための個別の調整や変更のことです。過度な負担にならない範囲で提供されます。
具体的な合理的配慮の例としては、無理に声を出させるような働きかけはせず、意思表示カードを活用するなどコミュニケーションの代替手段を習得するための支援を行うことが推奨されています。話す以外に書くことや手話、ジェスチャー、パソコンやタブレット型端末を利用する等の方法を伝えるという配慮も有効です。職場では、電話応対を免除してもらう、メールやチャットでのコミュニケーションを中心にする、会議での発言を強制されないなどの配慮が考えられます。
療育手帳との関係
場面緘黙症の方の中には、知的障害を伴う場合があります。その場合は療育手帳の対象となる可能性があります。療育手帳は知的障害のある方を対象とした手帳であり、IQ値や日常生活の状況などから判定されます。自治体によって名称が異なり、愛の手帳、みどりの手帳などと呼ばれることもあります。療育手帳の判定は、児童相談所や知的障害者更生相談所で行われます。
知的障害を伴う場合は、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を取得できる場合があります。複数の手帳を持つことで、より多くのサービスや支援を受けられる可能性があります。たとえば、療育手帳により受けられるサービスと、精神障害者保健福祉手帳により受けられるサービスを合わせて利用することができます。手帳の種類によって利用できるサービスが異なるため、それぞれの手帳のメリットを活用することが可能です。
ただし、場面緘黙症そのものは知的障害ではありません。話せないことと知的能力は別のものです。場面緘黙症の方の多くは知的能力に問題はなく、話せる場面では年齢相応の会話ができます。学業成績も良好である場合が多く、むしろ内面的な豊かさや思考力を持っている方も少なくありません。場面緘黙症は不安症のカテゴリに属する症状であり、知的機能の問題とは区別して理解する必要があります。
知的障害を伴わない場面緘黙症の場合は、療育手帳の対象とはならず、精神障害者保健福祉手帳のみが取得の選択肢となります。自分がどの手帳の対象となるかについては、医療機関や福祉担当窓口で相談することができます。症状の評価には専門的な知識が必要であるため、適切な機関で相談を受けることが重要です。
子どもへの支援体制
子どもが場面緘黙症の場合、早期発見と早期支援が重要です。日本における出現率は0.2から0.5パーセント以下とされ、発症のきっかけは環境の変化を伴う時期が多いとされています。保育園や幼稚園の入園時、小学校入学段階、引っ越しや転校などの環境変化が発症のきっかけとなることがあります。早期に適切な支援を開始することで、症状の改善や二次的な問題の予防につながります。
学校では、担任の教師やスクールカウンセラー、特別支援教育コーディネーターなどと連携して支援体制を整えます。無理に話させようとせず、段階的に不安を軽減する支援が必要です。場面緘黙の子どもは授業の妨害をするわけでもなく、誰に迷惑をかけるわけでもないので、教育現場ではただおとなしい子として見逃され、置きざりにされやすいタイプという課題があります。この点を理解し、積極的に支援を提供することが大切です。
個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、子どもの特性に応じた配慮や支援を具体化します。手を挙げる代わりにカードを使う、筆談を認める、小グループでの活動から始めるなどの工夫が考えられます。評価方法についても配慮が必要であり、口頭での発表を求めるのではなく、筆記やポートフォリオによる評価を取り入れるなどの方法があります。給食の時間や休み時間など、教室以外の場面での配慮も重要です。
教師が子どもの行動の変容を期待し指導するのではなく、子どもの意思や発信を重んじ、教師が歩み寄って支援することが必要とされています。家庭、学校、医療機関や相談機関が連携できることが、有効な支援へとつながります。場面緘黙は情緒障害という障害の分類に該当し、特別支援学級と通級による指導の対象となっています。医療機関での治療と並行して、学校での支援を継続することが効果的です。家庭、学校、医療機関が連携して子どもをサポートする体制を作ることが大切です。
保護者としては、子どもの症状を理解し、焦らずに見守る姿勢が重要です。無理に話させようとしたり、叱ったりすることは逆効果です。家庭では安心して話せる環境を維持し、子どもの自尊心を大切にすることが求められます。また、学校や医療機関と協力して、一貫した支援を提供することが効果的です。
相談窓口とサポート体制
場面緘黙症や障害者手帳について相談できる窓口はいくつかあります。お住まいの区市町村の福祉担当窓口では、精神障害者保健福祉手帳の申請方法や利用できる福祉サービスについて相談できます。窓口では、申請に必要な書類や手続きの流れについて詳しく説明を受けることができます。また、どのような支援が利用できるかについても情報提供を受けられます。
保健所や精神保健福祉センターでは、精神保健に関する相談を受け付けています。場面緘黙症の治療や支援について相談できます。精神保健福祉センターでは、専門の相談員が対応し、医療機関の紹介や福祉サービスの案内を行っています。匿名での相談も可能であり、プライバシーに配慮した対応がなされます。電話相談や来所相談など、様々な形態での相談が可能です。
発達障害者支援センターでは、発達障害に関する相談支援を行っています。場面緘黙症も発達障害者支援法の対象となっているため、相談できる場合があります。発達障害者支援センターでは、当事者や家族からの相談に応じ、適切な支援機関の紹介や情報提供を行っています。また、支援者向けの研修や啓発活動も実施しています。
また、かんもくネットや日本場面緘黙研究会などの民間団体も情報提供や支援を行っています。当事者や家族の体験談を聞くこともできます。これらの団体では、場面緘黙症に関する最新の情報を提供したり、当事者や家族が集まる会を開催したりしています。同じ経験を持つ人々と交流することで、孤立感を軽減し、有益な情報を得ることができます。インターネット上でも情報提供や相談の場が設けられています。
学校においては、スクールカウンセラーや特別支援教育コーディネーターに相談することができます。学校での具体的な支援方法や配慮について相談し、協力して支援体制を作ることができます。また、教育委員会の相談窓口でも、学校生活に関する相談を受け付けています。子どもの教育に関する困難については、これらの窓口を積極的に活用することが有効です。
相談する際には、症状の具体的な内容、いつから症状が始まったのか、日常生活や学業、就労にどのような影響があるのかなどを整理しておくと、スムーズに相談が進みます。また、医療機関を受診している場合は、診断名や治療内容についても伝えるとよいでしょう。相談窓口は、それぞれ専門分野や対応範囲が異なるため、自分の状況に合った窓口を選ぶことが大切です。
まとめ
場面緘黙症は、特定の社会的状況で話すことができなくなる不安症の一つであり、家では話せても学校や職場では話せないという状態が長期間続く症状です。話したり聞いたりする言葉の能力には特に問題がないものの、特定の場面では話すことができない状態を指します。この症状により日常生活や社会生活に著しい制限がある場合、精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。
手帳を取得するには、精神障害による初診日から6ヶ月以上経過していること、症状が日常生活や社会生活に制限を及ぼしていること、医師による診断書があること、継続的な治療を受けていることなどの条件があります。手帳の等級は1級から3級まであり、場面緘黙症の場合は多くが2級か3級に該当すると考えられます。症状の重症度、社会生活への影響、併存する障害や疾患、治療の経過などを総合的に評価して判定されます。
申請は区市町村の福祉担当窓口で行い、診断書または障害年金証書を提出します。審査には約2か月かかり、認められれば手帳が交付されます。有効期間は2年間で、更新が必要です。平成28年1月以降の申請では申請書にマイナンバーを記載する必要があります。手帳を取得すると、税制上の優遇、公共交通機関の運賃割引、公共施設の利用料金減免、障害者雇用枠での就職、障害福祉サービスの利用など、さまざまなメリットがあります。
2025年4月1日からはJRで精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介護者1名までの運賃が5割引きとなるなど、サービスが拡充されています。手帳を取得できない場合でも、自立支援医療制度を利用して医療費の自己負担を1割に軽減したり、障害者差別解消法に基づく合理的配慮を求めることができます。2024年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化され、学校や職場でも適切な配慮を受ける権利があります。
場面緘黙症は適切な治療と支援により改善が期待できる症状です。行動療法的アプローチ、エクスポージャー療法、認知行動療法、系統的脱感作法などの治療法があります。医療機関での治療、学校や職場での配慮、福祉サービスの利用などを組み合わせて、総合的な支援を受けることが大切です。場面緘黙症は情緒障害という障害の分類に該当し、特別支援学級と通級による指導の対象となっています。
家庭、学校、医療機関や相談機関が連携することが有効な支援につながります。無理に話させようとせず、本人のペースを尊重した段階的なアプローチが重要です。手帳の取得は、場面緘黙症で困難を抱えている方にとって、生活の質を向上させ、社会参加を促進するための有効な手段となります。自分の状況に合わせて、利用できる制度やサービスを積極的に活用していくことが、より良い生活を実現するための第一歩となります。

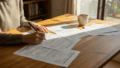

コメント