場面緘黙症は、家庭では普通に話せるにも関わらず、学校などの特定の社会的場面で話すことができなくなる症状です。この症状を持つ子どもと その家族にとって、一人で悩みを抱え込むことは大きな負担となります。しかし、同じ経験を持つ家族との出会いは、孤独感を和らげ、具体的な解決策を見つける重要な手がかりとなります。
場面緘黙症の家族会は、このような悩みを抱える家族が集まり、情報共有や相互支援を行う貴重な場です。2024年9月時点で、場面緘黙親の会のLINEオープンチャットには1600名以上が参加し、4周年を迎えるなど、多くの家族に利用されています。家族会への参加は、適切な知識の習得、実践的な支援方法の学習、心理的な安定、そして長期的な希望を得る機会となっています。

場面緘黙症の家族会に参加するとどのようなメリットがあるの?
場面緘黙症の家族会への参加には、多面的で実践的なメリットがあります。最も重要なメリットは、正しい知識と情報の習得です。場面緘黙症は原因や診断、治療方法について知られていないことが多く、家族会では最新の治療法や研究成果について学ぶことができます。知識を持つことで親御さんも楽になれる部分があり、先生や医師をはじめとする支援関係者に上手く相談していくことで、支援の現場もより良く変わっていくと考えられています。
同じ悩みを持つ家族との交流は、家族会参加の最大の価値の一つです。親の会では、何より親同士で話し合うことができます。同じ症状を持つ子どもの親同士だからこそ理解し合える悩みや不安を共有することで、孤独感を軽減し、精神的な支えを得ることができます。家族や教師が場面緘黙を理解することと、本人が場面緘黙について知識が得られるようサポートすることが大切で、話せない症状をもつのは自分だけでないことを知ることは子どもの孤独感を和らげるでしょう。
地域密着型の支援体制も重要なメリットです。「はぴもくcafe」では、オンラインであっても参加者を地域ごとに限定し、できる限り自分が住む地域の中で、同じ悩みをもつ親御さん同士が交流できるようにしています。これにより、実際の地域での支援体制や学校との連携について、より具体的で実用的な情報交換が可能になります。
さらに、参加しやすい環境作りにより、普段人前で話すことが苦手な保護者でも安心して参加できます。親御さんの中には発言することが得意でない方もいらっしゃるので、できるだけ少人数開催で、具体的な相談テーマを設定し、自己紹介も主催者側で代わりに行うなど、参加することや発言することに参加者がストレスを感じないように心がけています。
家族会で実際にどんな体験談が共有されているの?
家族会では、様々な段階の子どもを持つ家族の具体的で実践的な体験談が共有されています。これらの体験談は、現在困難を抱えている家族にとって具体的な希望と実践的な指針を提供しています。
高校受験に関する体験談は特に注目されています。場面緘黙親の会では、「場面緘黙症状があった娘の高校受験」についての詳細な体験談が紹介されており、中学3年生の場面緘黙の娘さんを持つ保護者の実体験が共有されています。この体験談では、受験準備の過程で学校との綿密な連携、受験校への事前説明、合理的配慮の申請など、様々な準備が必要でしたが、家族会での情報共有により、他の家族の経験を参考にしながら準備を進めることができました。結果として娘さんは希望する高校に合格し、新しい環境での成長への道筋をつけることができました。
付き添い登校に関する体験談も重要な情報源となっています。2024年には3家庭の保護者による付き添い登校の体験談が共有されており、学校に行けなくなった子どもに対して、親がどのように関わり、段階的に自立を促していったかという実体験が参加者間で共有されています。これらの体験談は、現在同様の困難を抱える家族にとって、具体的な対応方法と長期的な見通しを提供しています。
発達支援センターでの体験談も参考になる事例として紹介されています。場面緘黙親の会LINEオープンチャットに書き込みのあったももえさん(仮名)の発達支援センターでの体験談では、1歳から託児所に預けて場面緘黙の疑いが見つかった事例なども参加者から共有されており、早期発見の重要性が示されています。
これらの体験談に共通するのは、段階的な改善過程です。場面緘黙症を経験した当事者による体験記では、「無意識に突然しゃべりだすのは難しく、環境の変化をきっかけにちょっとずつ勇気を出し、スモールステップでほんのちょっとずつ頑張ることが重要」という経験が共有されており、焦らずに小さな変化を積み重ねることの重要性が示されています。
場面緘黙症の家族会はどのような活動をしているの?
場面緘黙症の家族会は、多様で継続的な活動を通じて、参加者に包括的な支援を提供しています。最も活発な活動の一つは、LINEオープンチャットによる24時間いつでもアクセス可能なオンライン支援です。場面緘黙親の会のLINEオープンチャットは、2024年9月8日に開設4周年を迎え、参加者数は昨年同時期の1270名弱から1600名以上に増加しており、多くの家族にとって重要な情報源となっています。
地域密着型の交流会「はぴもくcafe」も重要な活動です。2024年12月21日に行われた第26回「はぴもくcafe」交流会in京都では、京都のリアル会場では10回目の開催となり、お悩み相談会の形式では6回目として開催されました。同様に9月21日の第24回交流会では参加者8名で小学生のお子さんを持つ家庭が多数参加し、11月10日の第25回交流会(愛知)では過去最多の9名が参加するなど、継続的で活発な交流が行われています。
啓発活動と社会への発信も重要な活動分野です。2025年1月11日読売新聞京都版朝刊に、場面緘黙親の会の会長辻田和彰、副会長辻田那月のインタビュー記事が掲載され、場面緘黙症への理解促進と支援体制の充実について広く社会に向けて発信されています。このようなメディアを通じた啓発活動により、社会全体の理解促進に貢献しています。
学術活動と研究連携においても積極的な取り組みが行われています。場面緘黙親の会副会長の辻田那月が、「日本特殊教育学会第62回大会」で2024年9月6日にポスター発表を行うなど、学術的な側面からも場面緘黙症の支援向上に貢献しています。今後は社会全体として理解が進むことを目指し、研究者と連携しながら支援者や市民向けのセミナーを開催したり、親の声をまとめて記事にして配信していくことも予定されています。
かんもくネットとの連携により、場面緘黙の症状がある子どもや大人、経験者、家族、教師、専門家が協力しあい、活発な情報交換と正しい理解促進を目指しています。2024年春には会員システムを変更するなど組織的な改善も行われており、より多くの人が参加しやすい環境作りに取り組んでいます。
家族会参加により子どもや家族にどんな変化が期待できる?
家族会への参加は、子どもと家族の両方に多層的で持続的な変化をもたらします。最も重要な変化は、治療効果の向上です。現在日本で最も効果的とされているのは行動療法的アプローチで、多くの専門家、経験者、支援者は早期の治療介入を進めています。家族会で得られる正しい知識と実践的な対応方法により、家庭での支援が改善され、専門的な治療との相乗効果が期待できます。
二次障害の予防は特に重要な効果です。適切な治療・支援を受けないと、コミュニケーションに自信が持てず劣等感が増し、うつ状態などの二次障害につながるリスクが高まります。家族会への参加により、早期の適切な対応が可能になり、これらのリスクを大幅に軽減することができます。
家族全体の心理的安定も大きな変化の一つです。同じ困難を抱える家族との出会いにより、親自身の孤立感が軽減され、心理的な安定を得ることができます。この安定は、子どもへの支援においても重要な要素となり、より冷静で継続的な支援を提供する基盤となります。2020年に娘が場面緘黙を発症して幼稚園を不登園になったことをきっかけに、仕事を辞めて子育てと家事に専念するようになった父親の事例のように、家族の生活に大きな変化をもたらすことがありますが、家族会での支援により、このような変化をポジティブに捉え、効果的に対応することが可能になります。
長期的な成長と発達の促進も期待できる重要な変化です。家族会では様々な年齢段階の子どもを持つ家族と交流することで、場面緘黙症の子どもの成長過程を長期的な視点で捉えることができるようになります。現在の困難が永続的なものではなく、適切な支援により改善可能であることを実感することで、希望を持って支援に取り組むことができます。
社会適応能力の向上も重要な効果です。家族会で学んだコミュニケーション支援の具体例として、話したい内容をうまく伝えるためにホワイトボードやノートを用いて筆談をしてもいいという環境を整えることにより、子どもは声を出すことができなくても自分の意思を伝えることができ、学校生活における孤立感を軽減することができます。
場面緘黙症の家族会に参加するにはどうすればいい?
場面緘黙症の家族会への参加は、複数の方法とルートが用意されており、それぞれの家族の状況やニーズに応じて選択することができます。最も手軽でアクセスしやすいのは、LINEオープンチャットへの参加です。場面緘黙親の会が運営するLINEオープンチャットは、2024年9月時点で1600名以上が参加しており、24時間いつでも情報交換や相談が可能です。オンライン環境では地理的な制約を超えて全国の家族とつながることができます。
地域密着型の交流会「はぴもくcafe」への参加も推奨されます。これらの交流会は、オンラインであっても参加者を地域ごとに限定し、できる限り自分が住む地域の中で、同じ悩みをもつ親御さん同士が交流できるようになっています。2024年には京都や愛知などで定期的に開催されており、参加者8名から9名程度の少人数制で、参加しやすい環境が整備されています。
初めて参加する際の重要なポイントとして、参加することや発言することにストレスを感じないような配慮がなされていることを理解しておくことが大切です。親御さんの中には発言することが得意でない方もいらっしゃるので、できるだけ少人数開催で、具体的な相談テーマを設定し、自己紹介も主催者側で代わりに行うなど、参加者がストレスを感じないように心がけています。
専門機関との連携も参加の重要なルートです。療育センター・発達支援センター・教育センターなどの相談機関、子どもの発達に詳しい医療機関、学校の特別支援教室やスクールカウンセラーなどから家族会の情報を得ることができます。これらの専門機関では、家族会参加の意義や効果についても説明を受けることができ、より安心して参加を決定することができます。
かんもくネットも重要な情報源です。場面緘黙の症状がある子どもや大人、経験者、家族、教師、専門家が協力しあい、活発な情報交換と正しい理解促進を目指している組織で、2024年春には会員システムを変更するなど、より多くの人が参加しやすい環境作りに取り組んでいます。
参加にあたって重要なのは、段階的なアプローチです。まずはオンラインでの情報収集から始め、慣れてきたら地域の交流会への参加を検討するという方法が推奨されます。また、家族会への参加は一時的な支援にとどまらず、子どもの成長に伴う様々な課題に対して継続的な支援を提供するため、長期的な視点を持って参加することが重要です。

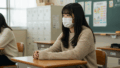
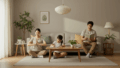
コメント