場面緘黙症は、特定の状況で話すことができなくなる状態として知られていますが、その背景には深く複雑な内面の葛藤が存在します。当事者は「話したいのに話せない」というジレンマに苦しみ、周囲からは「恥ずかしがり屋」や「大人しい子」と誤解されることも少なくありません。しかし実際には、声が喉に詰まり言葉が出ない感覚を「喉に鍵がかかったよう」と表現し、閉じ込められた声や感情が「外に出してくれといつも叫んでいる」ような内面の叫びを抱えています。国際的な診断基準であるDSM-5では不安症群の一つに分類されており、単なる性格の問題ではなく、本人の意思ではコントロールしにくい精神的な状態なのです。この記事では、2025年の最新知見と当事者の生の声をもとに、場面緘黙症の内面で起こっている複雑な葛藤について詳しく解説し、理解を深めるための情報をお伝えします。
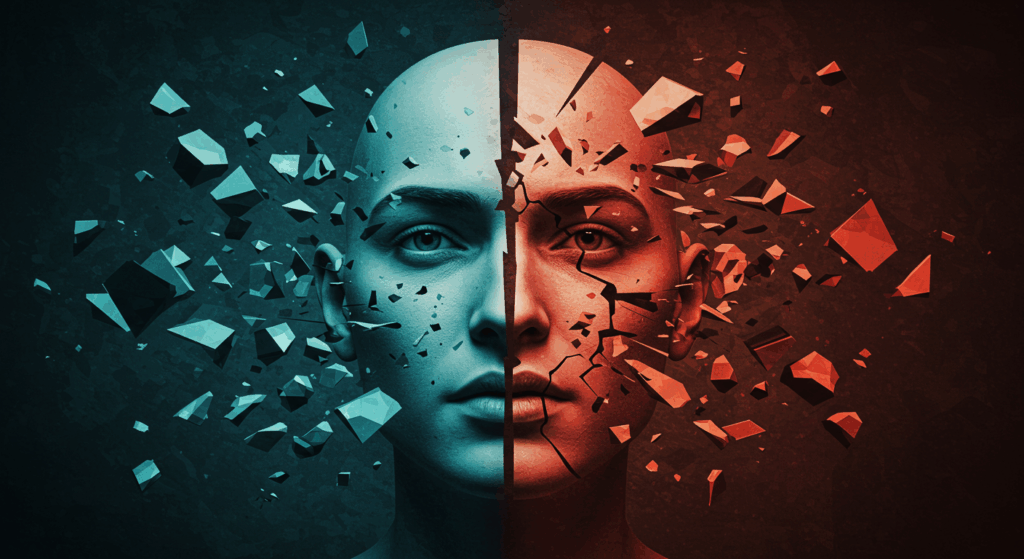
場面緘黙症の人が抱える「話したいのに話せない」内面の葛藤とは?
場面緘黙症の最も根本的な葛藤は、「話したいという強い気持ちがあるにも関わらず、声を出すことができない」という状態にあります。これは単純な「話したくない」という意思の問題ではなく、話そうとすると強い不安や緊張に襲われ、物理的に声が出せなくなってしまう状態です。
当事者の多くは、家庭などのリラックスできる環境では活発におしゃべりができます。しかし、学校や職場、特定の人物の前といった社会的状況になると、まるで別人のように無口で無表情になり、「地蔵のように固まる」状態になってしまいます。この極端な変化により、「本来の気持ちや性格を封じられてしまう」という深い絶望感を抱えることになります。
この葛藤の特徴として、全身のアンテナが過敏になるという現象があります。周囲の些細な変化にも強く反応してしまい、常に緊張状態が続きます。ある当事者は「理由も分からない苦しさ」が長年続くと表現しており、特に重要なことほど言えなくなる傾向があります。
さらに深刻なのは、自己の縛りという現象です。幼稚園に入る前から「外に出たらしゃべらないぞ」「本当の自分を出さないんだぞ」と無意識に自分を縛りつけてしまい、学校や習い事では「緘黙」状態の自分と、家庭でよく話す自分を使い分けるようになります。この二重生活が、当事者にとって大きな心理的負担となっているのです。
また、場面緘黙症における内面の葛藤は、特定の対象に限定されない漠然とした「不安」に起因することが多いとされています。話すことそのものよりも、「話すことへの不安」がどんどん膨らんでしまい、それが悪循環を生み出します。この不安は、外部環境からの刺激に対する過敏さによってさらに増幅され、当事者を苦しめ続けるのです。
学校や職場で場面緘黙症の人が経験する具体的な心の苦しみとは?
学校生活において、場面緘黙症の当事者が経験する心の苦しみは多岐にわたります。最も辛いのは、「力を発揮できない悔しさ」です。授業中に正しい答えが分かっていても発言できず、人と協力することが苦手で、本来の能力を示すことができません。
特に興味深いのは、国語の朗読や問題の答えなど指示された定型的な発話はできても、自由な会話はまったくできないという現象です。これは、自発的な対人コミュニケーションとの間に大きなギャップがあることを示しており、当事者にとって混乱と苦痛の源となります。
対人関係における苦悩も深刻です。優しく声をかけられても反応できず、話せないことで周囲から「腫れ物に触るかのような目で見られる」経験をします。これにより、「居たたまれず申し訳ない気持ち」や「話しかけられるのが怖い」という複雑な感情が積み重なり、休み時間もただ席で固まって過ごすことになります。話しかけられた際には「うれしい」と感じる一方で、「話しかけられるのがこわい」という矛盾した感情を抱くこともあります。
音や注目への過敏さも大きな苦しみの一つです。自分の体から出る音(咳、くしゃみ、鼻をかむなど)や、自分の行動によって出る音(椅子を引く、スーツケースを引きずるなど)を出すことが極度に苦手になります。これは「注目を浴びることが怖い」「大きい音を立てると周りに迷惑になるのでは」という強い思いから来ており、「喋らない、音を立てない、というのは恐怖から自分を守る手段」として機能しています。そのため、足音を立てずに忍びのような生活を送る人もいるほどです。
さらに深刻なのは、生理現象の困難です。学校などでトイレに行きたいと伝えられず、我慢してしまうなど、基本的な身体的ニーズを満たすことさえ困難になります。
成人期以降も、これらの困難は形を変えて続きます。職場では上司や同僚の質問に返事ができない、休憩中の雑談ができない、会議中に言いたいことがあっても発言できないといった問題が生じます。指示の内容が分からなくても聞き返せず、初めての状況で体が思うように動かない「緘動」という状態に陥ることもあります。
自己認識の歪みも深刻な問題です。「自分の声や話し方が気になって話せなくなる」「人前で話すとき、変に思われていないかが気になる」「他人から自分の欠点を見られていると感じる」といった思考パターンが定着し、「自分の意見を言うと否定される気がする」「自分には他人より劣っている部分が多い」という自己否定的思考が強まります。この結果、自己肯定感を持ちにくい状況に陥り、話さないことで一時的に不安が和らぐため、話さない行動が強化される悪循環に陥ってしまうのです。
場面緘黙症の当事者にとって「治る」とはどのような状態を指すのか?
場面緘黙症における「治癒」の概念は、医学的な診断基準と当事者の実感との間に大きな乖離があります。当事者にとっての「治った」という感覚は、単に発話が可能になること以上の、内面の変化を伴う複雑なプロセスとして語られています。
ある当事者(入江紗代さん)は、生活の中で緘黙的な症状が出る不安が常にあり、克服と緘黙状態の間を行ったり来たりすると感じています。この当事者にとって「治る」という言葉や感覚には違和感があり、体の病気のように常に再発するかもしれないという怯えがあると述べています。しかし、もし緘黙のことを頭の中から全く忘れて生活できる日が来たら、それが「治った」と言えるかもしれない、あるいは「緘黙気質」が残っていても毎日自分らしく過ごせていれば「治った」と言えるだろうと考えています。
別の当事者(らせんゆむさん)は、多少の苦手は残るものの、症状はほとんど「治った」と認識しています。彼女にとっての「治った」の定義は、「どの場面でも差し支えない程度で話せるようになった」ことに加え、場面緘黙であったことで傷ついた経験を「客観的な気持ち」で認められるようになり、それを蒸し返しても傷つかなくなったこと、そして「不得意なことは不得意だと認め、対処法を考えて乗り切れるようになった」ことです。これは、過去の経験を心の内で消化し、自己否定から脱却できた状態を「治癒」と捉える視点を示しています。
また別の当事者(浜田貴照さん)は、話すことはできているものの、「最初に緘黙になったときの緊張感」が今も残っているため、「まったく治っていない」と感じています。彼にとっての「治る」は、この異様な緊張感がなくなることだとされています。これは、言語症状が改善しても、内面の根本的な不安や緊張が残っていれば「治癒」とは言えないという深い洞察を示しています。
これらの多様な「治った」感覚から分かることは、真の治癒には以下の要素が含まれるということです:
- 内面の不安の軽減
- 過去の経験の消化と受容
- 自己肯定感の回復
- 生活の質の向上
- 自分らしい生き方の実現
さらに重要なのは、当事者の多くが場面緘黙を一時的な症状ではなく、生まれ持った「気質」や「体質」として捉えていることです。完全に症状がなくなることよりも、その特性と上手に付き合いながら、自分らしく生きられることを「回復」と考える視点が見られます。
場面緘黙症による内面の葛藤を軽減するために効果的な支援方法は?
場面緘黙症の内面の葛藤を軽減するためには、当事者の心に寄り添った多角的なアプローチが必要です。最も重要なのは、自己理解と自己肯定への道筋を作ることです。
27歳で初めて「場面緘黙」という言葉をインターネットで知った当事者(入江紗代さん)は、世界に一人ではなかったという衝撃とともに安心感を覚えたと語っています。今まで曖昧で八方塞がりだった悩みの輪郭を把握できたことで、話せない自分を以前のように責めすぎない「自己肯定」につながったのです。このように、インターネットや本、専門的な学習を通じて自分の症状を理解することは、大きな安心感と自己受容の始まりとなります。
「無理しないこと」も重要な支援方法の一つです。当事者は精神状態が良くないときは無理をせず、人に頼ったり、発話や対人を必要とする用事を先延ばしにしたりすることで、気が楽になり、安心して行動ができるようになると述べています。成功と失敗という考え方にとらわれないことで、自分を追い込まず、プレッシャーを軽減できるのです。
安心できる環境と人間関係の構築は支援の基礎となります。信頼できる友人、家族、教育者、職場の人の存在、そして信頼できる専門職との出会いは、当事者にとって大きな影響を与えます。特に、自分のことを真剣に考えてくれる専門家の関わりは、実際の支援効果以上に大きな喜びとなることがあります。
自助グループやフリースクールなど、安心できる居場所での活動も効果的です。同じ悩みを持つ仲間との交流を通じて安心感や楽しさ、エネルギーを得られる場となります。これらの場所では、話せるか話せないかにかかわらず、活動の中で楽しさを共有できることが重要です。
周囲の人々の適切な接し方も欠かせません:
- 話すことを強要しない
- 話さないこと自体を問題視しない
- 話せた時に過剰に反応しない
- 非言語的なコミュニケーションを尊重する
- 一対一で関わる時間を設ける
専門的な治療では、認知行動療法が最も推奨される治療法としてエビデンスがあります。不安を軽減し、非言語的コミュニケーションや対人交流、言語的コミュニケーションを段階的に増やしていくことを目標とします。また、マインドフルネスの実践も、緊張と不安の軽減、自信と安心の確保、生活の質的向上につながることが示されています。
家庭では、子どもが自由に話せ、安心して感情を出せる環境を維持することが重要です。「感情のラベリング」のように、自分の感情を理解し、言葉で表現する練習も効果的です。親が感情のモデルを示し、感情表現を肯定的に受け止めることで、安心感が育まれ、恐怖感が和らぎます。
場面緘黙症の理解を深めるために社会に求められる変化とは?
場面緘黙症への社会的理解を深めるためには、まず「緘黙」という名称への誤解を解くことが重要です。当事者からは、この名称が言語症状のみに注目されており、内面の葛藤や身体的側面を十分に表していないという指摘があります。実際には、話せないことだけでなく、体の動きや自己表現全般が抑えられる「緘動」という側面や、深いところにある不安、本当の自分を出せないという「二重人格的」な悩みを総合した理解が必要なのです。
専門的支援体制の整備は急務です。当事者は、場面緘黙の専門的な支援につながるシステムや、早い段階で症状が改善できるような適切な介入が社会に整備されることを強く望んでいます。現状では、多くの専門職が場面緘黙を十分に理解しているとは言い難く、医療機関を受診しても適切な支援を受けられなかったという声が聞かれます。
早期発見と早期介入の重要性も認識される必要があります。当事者の多くは「もっと早く知りたかった」という悔しさを抱えており、適切な情報や支援に早期にアクセスできることで、二次障害のリスクを大幅に軽減できる可能性があります。
社会全般への理解促進では、分かりやすい情報発信が効果的です。らせんゆむ氏のコミックエッセイ『私はかんもくガール』の出版は予想を超える反響を呼び、同じ思いを抱える人が多いことを実感させました。このように、漫画やメディアを通じた啓発活動は、当事者の自己肯定感向上にもつながります。
教育現場での理解向上も不可欠です。教師や保育士、学校関係者が場面緘黙について正しい知識を持ち、適切な対応ができるようになることで、子どもたちの学校生活における苦痛を軽減できます。また、合理的配慮の提供も重要で、受験時の面接をパソコンで行えるようにしたり、会話が必要な授業で筆談対応を認めたりするなど、当事者の状況に応じた配慮が求められます。
当事者活動の支援と促進も重要な変化の一つです。「かんもくの会」などの当事者活動は、自己肯定感を高める上でプラスに作用しており、自分の経験を活かして他者を助ける役割を持つことで、自己有用感や自信の獲得につながります。当事者が気軽にアクセスできる集まりや、同じ悩みを打ち明けられるミーティングの場を社会が提供することが求められています。
最終的に求められるのは、多様性を認める社会の実現です。話せない状態を「問題」として捉えるのではなく、一人ひとりの特性として理解し、それぞれの人が自分らしく生きられる環境を整備することが重要です。場面緘黙症の当事者が「声にならない声」を社会に届け、より生きやすい未来を築くためには、私たち一人ひとりの理解と配慮が不可欠なのです。



コメント