精神障がい者手帳の交付を申請しようと考えている方にとって、手帳がいつ手元に届くのか、その交付期間や日数は気になるところです。通院のための割引制度や税制優遇措置を早く利用したい、あるいは障がい者雇用枠での就職活動を始めたいなど、手帳の取得を急いでいる方も多いでしょう。精神障がい者保健福祉手帳の申請から交付までには一定の期間が必要であり、その流れを理解しておくことで計画的に準備を進めることができます。本記事では、精神障がい者手帳の交付期間や日数について、申請手続きの流れから更新時の注意点まで詳しく解説していきます。手帳取得を検討されている方や、すでに申請を済ませた方にとって、交付までのスケジュール感を把握し、安心して手帳の到着を待つための参考情報となれば幸いです。

精神障がい者手帳の交付期間の目安
精神障がい者保健福祉手帳の申請から交付までには、自治体によって多少の違いはあるものの、一般的に2ヶ月から3ヶ月程度の期間が必要とされています。この期間は全国的におおむね共通していますが、地域の審査体制や申請件数の状況によって前後することがあります。
鹿児島市では、申請から手帳の交付まで約2ヶ月から2ヶ月半程度の期間を要するとされており、西宮市においては申請書類を受け付けてから手帳が交付されるまでに約3ヶ月程度かかるという情報が提供されています。これらの事例から分かるように、自治体ごとに若干のばらつきはあるものの、おおむね60日から90日程度の審査期間を見込んでおくことが適切といえます。
交付決定の通知は、審査が完了した段階で申請者のもとに届きます。もし申請してから3ヶ月以上経過しても何の連絡もない場合には、申請した市区町村の担当窓口に問い合わせることをお勧めします。申請書類に不備があった場合や、審査に時間がかかっている特別な事情がある場合もありますので、確認することで状況を把握できます。
交付までの期間は、お住まいの地域だけでなく、審査の状況や申請書類の完備度によっても変動します。書類に不備があると再提出が必要となり、さらに時間がかかることもあります。そのため、申請時には必要書類をすべて揃え、記入漏れがないかを十分に確認することが重要です。余裕を持って申請手続きを進めることで、必要なタイミングで手帳を受け取ることができます。
申請手続きの流れと必要書類
精神障がい者保健福祉手帳の申請は、お住まいの市区町村の担当窓口で行います。本人が申請することが原則とされていますが、本人による申請が難しい場合には、保護者、家族、医療機関の職員などによる代理申請も可能です。代理申請の場合でも、交付までの期間は通常の申請と同じく約2ヶ月から3ヶ月程度であり、代理だからといって審査期間が長くなることはありません。
申請に必要な書類としては、まず申請書が必要です。申請書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必須となっており、各自治体の窓口で入手できます。次に、診断書または年金証書のいずれかを提出します。診断書を用いる場合は、精神疾患に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後の診断書で、かつ作成日が申請日から3ヶ月以内のものでなければなりません。診断書は障がい者手帳用の様式を使用することになります。
一方、精神障がいを支給事由とした障がい年金もしくは特別障がい給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写しでも申請が可能です。年金証書等を用いる場合は、診断書の提出は不要となります。また、本人の写真も必要で、写真のサイズは縦4センチメートル×横3センチメートルで、脱帽・上半身の写真を用意します。写真は申請日から1年以内に撮影したものでなければなりません。
マイナンバー関連書類として、個人番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類が必要です。マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカード1枚で個人番号確認と本人確認ができます。マイナンバーカードがない場合は、個人番号の通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどで個人番号を確認し、運転免許証や健康保険証などで本人確認を行います。
代理申請を行う場合には、通常の申請書類に加えて、代理権を証明する書類と代理人の本人確認書類が必要になります。代理権の確認書類として、法定代理人の場合は戸籍謄本その他資格を証明する書類が必要であり、任意代理人の場合は委任状などが必要となります。委任状には、申請者本人の署名や押印が必要です。代理人の本人確認書類としては、代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、在留カード、特別永住者証明書等のうちいずれか1つが必要です。
診断書の取得と有効期間
精神障がい者保健福祉手帳の申請において、診断書は非常に重要な役割を果たします。手帳の申請に使用する診断書は、初診日から6ヶ月以上を経過した日以後における診断書が必要です。初診日とは、手帳交付を求める精神疾患について初めて医師の診療を受けた日を指します。そのため、診断書作成医療機関での初診日とは必ずしも一致しないことに注意が必要です。
診断書の有効期間は、作成日から3ヶ月以内です。診断書を医療機関から入手してから3ヶ月以内に申請を行う必要があります。診断書が古くなってしまった場合は、新たに診断書を取得する必要が生じます。診断書は精神保健指定医、精神科の医師、または手帳の対象となる精神疾患について診断や治療を行っている医師が作成します。
診断書の作成には費用がかかり、その金額は医療機関によって異なりますが、一般的に数千円程度かかります。また、診断書の作成には1ヶ月ほど必要な場合があるため、余裕を持って医療機関に依頼することをお勧めします。診断書の作成期間と申請後の審査期間を合わせると、手帳取得までには相当な期間が必要となるため、早めの準備が大切です。
診断書を取得したら速やかに申請手続きを行うことが重要です。診断書の有効期間である3ヶ月を過ぎてしまうと、再度診断書を取得しなければならず、費用と時間の両面で負担が増えてしまいます。申請書類の準備は診断書を依頼する前に進めておき、診断書が手元に届いたらすぐに申請できるようにしておくことが効率的です。
障がい等級の判定と審査プロセス
精神障がい者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級があります。等級は精神疾患の状態と能力障がいの状態の両面から総合的に判断されます。等級の判定は、まず精神疾患の存在の確認を行い、次に精神疾患(機能障がい)の状態の確認、そして能力障がい(活動制限)の状態の確認を行い、最後に精神障がいの程度の総合判定が行われるという順序で進められます。
1級は、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とされています。日常生活において常時援助が必要な状態であり、精神障がいのため、身の回りのことがほとんどできない、または適切な援助があっても最低限の生活維持が困難な状態を指します。2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とされています。精神障がいのため、日常生活に著しい制限を受けており、時には援助が必要な状態です。
3級は、日常生活または社会生活が制限を受けるか、日常生活または社会生活に制限を加えることを必要とする程度とされています。精神障がいのため、日常生活または社会生活に一定の制限を受けており、特定の配慮が必要な状態です。この等級判定には専門的な審査が必要であり、そのために申請から交付までに2ヶ月から3ヶ月程度の期間を要することになります。
審査は都道府県の精神保健福祉センターなどで行われ、提出された診断書の内容や申請書類の情報をもとに、専門的な見地から等級が決定されます。申請者の日常生活能力や社会生活能力、精神症状の程度などが総合的に評価され、適切な等級が判定されます。この審査プロセスが慎重に行われるため、一定の期間が必要となるのです。
手帳の受け取り方法と有効期間
手帳の交付が決定すると、申請者に通知が届きます。通知が届いたら、指定された窓口で手帳を受け取ります。多くの自治体では、手帳は窓口で直接受け取る必要があります。郵送での受け取りは、原則として行っていない自治体が多いですが、一部の自治体では郵送による交付を行っている場合もあります。郵送を希望する場合は、申請時に確認しておくとよいでしょう。
手帳を受け取る際には、本人確認書類が必要になる場合があります。代理人が受け取る場合は、委任状や代理人の本人確認書類が必要になることがあります。新規申請と再申請の場合、都道府県で承認された場合の有効期間の開始日は、市区町村の窓口で書類を受け付けた日となります。この点は重要で、申請日が有効期間のスタート日となるため、早めに申請することで有効期間を最大限活用できます。
精神障がい者保健福祉手帳には有効期間があり、その期限は2年間です。手帳の有効期間は申請受理日から2年間で、正確には2年後の月末までとなります。有効期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。更新手続きは、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。更新の手続きは有効期限の3ヶ月前になったらすぐに始めることをお勧めします。
更新手続きを行う際も、新規申請と同様に診断書または年金証書が必要です。2年ごとに、障がい等級に定める精神障がいの状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。更新手続きを忘れてしまうと手帳は失効してしまいます。手帳が失効した場合は、再度新規申請として手続きを行う必要があります。
更新の際の等級は、新規申請時の等級と同じになるとは限りません。症状の変化によって等級が変わることもあります。症状が改善していれば等級が下がることもありますし、悪化していれば等級が上がることもあります。そのため、更新時には現在の状態を正確に反映した診断書を取得することが重要です。
手帳取得のメリットと活用方法
精神障がい者保健福祉手帳を取得することで、様々なメリットがあります。税制上の優遇措置として、所得税や住民税の障がい者控除が受けられます。障がい者控除として27万円が所得金額から差し引かれます。手帳の等級が1級の方は特別障がい者となり、特別障がい者控除として40万円が所得金額から差し引かれます。
精神障がい者保健福祉手帳の1級から3級までの方が、住民税の所得割控除を受けることができます。自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の減免は、精神障がい者保健福祉手帳1級の方が対象となります。各種サービスや料金の割引も受けられます。公共料金等の割引、NHK受信料の減免、税金の控除・減免、生活福祉資金の貸付などが利用できます。
交通機関の運賃割引も重要なメリットです。鉄道、バス、タクシー等の運賃割引が受けられます。航空会社の多くが、国内線に限って、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方を対象に、航空券の3割から5割引を実施しています。その他にも、携帯電話料金の割引、上下水道料金の割引、心身障がい者医療費助成、公共施設の入場料等の割引などが受けられる場合があります。
NHK受信料については、手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合は全額免除となります。重要な点として、精神障がい者保健福祉手帳を持つことで不利益が生ずることはありません。手帳の取得は任意ですので、必要に応じて取得を検討することができます。
日常生活での活用として、公共交通機関を利用する際に運賃割引を受けることができます。通勤や通院、買い物など、日常的な移動の費用を軽減できます。公共施設の利用料減免も受けられます。図書館、博物館、美術館、スポーツ施設などの利用料が減免される場合があります。文化的な活動やスポーツを楽しむ機会が増えます。
就労支援と障がい者雇用
精神障がい者保健福祉手帳を取得することで、就労支援に関しても様々なメリットがあります。以前は精神障がい者は法定雇用率の対象ではありませんでしたが、平成18年4月1日に障がい者自立支援法が施行されたことに伴い、精神障がい者保健福祉手帳所持者は法定雇用率の対象となりました。さらに、平成24年には厚生労働省内で雇用義務化の方針が決定され、平成30年4月1日からは雇用義務の対象者に追加されました。
この変更により、企業は一定の割合で障がい者を雇用することが義務付けられており、精神障がい者保健福祉手帳を持つことで、障がい者雇用枠での就職が可能になりました。障がい者雇用率制度では、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の所持者が、実雇用率の算定に計上されます。短時間労働者は一般的に0.5人として計算されます。
令和4年の障がい者雇用促進法の改正では、事業主の責務として、障がい者である労働者の職業能力の開発及び向上が明確化されました。また、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度身体障がい者、重度知的障がい者及び精神障がい者に関する特例給付金制度が創設され、多様な働き方の推進が図られています。
障がい者手帳を持つことで、一般就労だけでなく障がい者雇用での求人にも応募できるようになります。障がい者雇用で就職することで、通院や治療への配慮を受けやすくなり、周囲の理解も得やすくなります。また、障がいに対する配慮を企業に求めることができます。障がい者雇用促進法のもと、企業は障がい者雇用を推進しており、様々な配慮が行われています。例えば、勤務時間の調整、業務内容の配慮、休憩時間の確保、通院のための休暇取得などが挙げられます。
地域の障がい者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就職及び職場への定着に向けて、就業面と生活面の一体的な相談支援が行われています。障がい者総合支援法に基づく就労移行支援事業や就労継続支援事業などのサービスを利用できます。就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方を対象に、就職に必要な知識やスキルの習得、職場実習、求職活動の支援などを行います。
就労継続支援には、A型(雇用型)とB型(非雇用型)があります。A型は雇用契約を結んで働く形態で、最低賃金が保障されます。B型は雇用契約を結ばずに働く形態で、工賃が支払われます。その他、生活訓練や自立訓練などのサービスも利用可能です。これらのサービスは、日常生活能力の向上や社会生活への適応を支援します。
自立支援医療制度との違いと併用
精神障がい者保健福祉手帳とは別に、自立支援医療制度という医療費助成制度があります。自立支援医療制度は、心身の障がいを除去または軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。精神通院医療は、この自立支援医療制度の一つです。
通常、公的医療保険では3割の医療費を負担しますが、自立支援医療制度を利用すると、1割負担を原則としつつ、本人の所得や疾病状況、世帯の所得状況に応じて、月額負担上限額が認定されます。ただし、入院については対象とはなりません。外来通院、投薬、訪問看護などが対象となります。受給者証の有効期間は1年以内です。
精神障がい者保健福祉手帳と自立支援医療は、目的が異なります。手帳は障がいの認定と社会参加支援を目的とし、各種割引やサービスを受けることができます。一方、自立支援医療は通院医療費の負担軽減を目的としています。手帳を受けるためには、その精神障がいによる初診日から6ヶ月以上経過していることが要件となります。手帳の有効期間は2年です。
自立支援医療の受給者証の有効期間は1年以内で、毎年更新が必要です。これら二つの制度は別々に申請が必要で、併用も可能です。西宮市などでは、精神障がい者保健福祉手帳と自立支援医療の同時申請手続きも行えます。一部の自治体では、独自の医療費助成制度を設けています。例えば、東京都の心身障がい者医療費助成制度(マル障)では、平成31年1月1日から精神障がい者保健福祉手帳1級の方が対象になりました。
自立支援医療はマル障に優先して適用されますが、マル障との併用は可能です。このような自治体独自の制度については、お住まいの自治体に確認することをお勧めします。手帳と自立支援医療を併用することで、通院医療費の負担を軽減しながら、手帳による各種サービスも利用できます。これにより、経済的な負担を減らしつつ、社会参加や自立した生活を支援する様々なサービスを活用することが可能になります。
申請時の注意点と準備
精神障がい者保健福祉手帳を申請する際には、いくつかの注意点があります。まず、申請には初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。精神疾患の治療を開始してすぐには申請できませんので、この点に注意が必要です。診断書の有効期間は作成日から3ヶ月以内ですので、診断書を取得したら速やかに申請手続きを行うことが重要です。
診断書の作成には時間がかかる場合がありますので、余裕を持って医療機関に依頼することをお勧めします。申請書類に不備があると、審査に時間がかかったり、再提出が必要になったりします。申請前に必要書類がすべて揃っているか、記入漏れがないかをよく確認しましょう。マイナンバーの記載が必要ですので、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された書類を用意しておく必要があります。
写真は規定のサイズと条件を満たしたものを用意する必要があります。脱帽・上半身で、申請日から1年以内に撮影したものでなければなりません。申請から交付までの期間を考慮して、早めに手帳が必要な場合は、申請時に窓口で状況を説明し、おおよその交付時期を確認しておくとよいでしょう。
申請書類の準備は診断書を依頼する前に進めておき、診断書が手元に届いたらすぐに申請できるようにしておくことが効率的です。特に、更新時期が近づいている場合や、就職活動などで手帳が必要な時期が決まっている場合には、逆算して申請スケジュールを立てることが大切です。申請から交付まで2ヶ月から3ヶ月かかることを念頭に、診断書作成期間も含めて余裕を持った計画を立てましょう。
等級変更と再申請について
精神障がい者保健福祉手帳には、更新時だけでなく、有効期間中でも等級変更の申請を行うことができます。症状が悪化した場合や改善した場合、現在の等級が実態と合わなくなったと感じた場合に申請できます。等級変更の申請は随時受け付けられています。新規申請と同様に、精神障がいにかかる初診日から6ヶ月を経過した日以降に作成され、申請日において作成日から3ヶ月以内の診断書を提出する必要があります。
等級変更申請の際にも、マイナンバーの記載が必要です。申請書類は新規申請とほぼ同じで、写真も新たに必要になります。症状が悪化して、より重い等級への変更を希望する場合は、主治医と相談の上、最新の診断書を取得して等級変更の申請を行います。等級変更の審査には、申請から約2ヶ月程度かかります。
等級変更が認められない場合は、等級変更を行わない旨の通知書が送られます。その場合は、現在の等級のまま手帳を使い続けることになります。精神障がい者保健福祉手帳の申請で非該当となった場合や、等級変更が認められなかった場合でも、再申請は可能です。障がい者手帳は基本的に一度申請が認められなくても、再度申請することができます。
症状が変化した場合や、新たな診断書を取得できた場合には、再度申請を検討することができます。ただし、再申請の際にも診断書の作成費用などが必要になります。再申請を検討する際には、主治医と十分に相談し、申請のタイミングや診断書の内容について適切なアドバイスを受けることが重要です。
手帳取得のデメリットと心理的側面
精神障がい者保健福祉手帳を取得することには多くのメリットがありますが、一部デメリットや注意すべき点もあります。診断書の作成には1ヶ月ほど必要で、申請後の審査でも2ヶ月かかります。また、診断書の作成には費用がかかり、医療機関によって異なりますが、一般的に数千円程度の診断書作成料が必要です。
手帳の有効期限は2年で、自動更新はされません。そのため、2年ごとに更新手続きが必要となり、その都度診断書の取得や申請手続きを行う必要があります。この更新手続きの負担を感じる方もいます。手帳を持つこと自体に抵抗を感じる方もいらっしゃいます。自分が精神疾患によって抱えている障がいを自分で把握し、認める必要があるため、心理的な負担を感じることがあります。
ただし、手帳を持っているからといって、周りの人や職場に伝える義務はありません。また、いつでも返還することも可能です。手帳の取得と利用は本人の判断に委ねられています。症状が軽くなった場合は、更新手続きの審査で非該当となり、手帳を返還しなければならない場合もあります。これは症状の改善という良い面もありますが、それまで受けていたサービスや支援が受けられなくなる可能性があります。
精神障がい者保健福祉手帳は、交付を受けた人のプライバシーに配慮し、表紙の記載は「障がい者手帳」とのみ記されています。これは身体障がい者手帳や療育手帳とは異なる配慮で、手帳の種類が外見から分からないようになっています。手帳を使用する際も、本人の意思で提示するかどうかを選択できます。必要な場面でのみ提示すればよく、常に公開する必要はありません。
重要な確認事項として、精神障がい者保健福祉手帳を持つことで、不利益が生ずることはありません。これは厚生労働省も明言している点です。手帳の取得は任意であり、本人の判断で取得を決めることができます。また、手帳を取得した後でも、不要になった場合や取得したことを後悔した場合には、いつでも返還することが可能です。
各自治体の取り組みとサービスの違い
精神障がい者保健福祉手帳の交付や関連サービスは、各自治体によって詳細が異なる場合があります。先に述べたように、申請から交付までの期間は自治体によって異なります。一般的には2ヶ月から3ヶ月程度ですが、審査の混雑状況や自治体の体制によって前後することがあります。早めに手帳が必要な場合は、申請時に窓口で状況を説明し、おおよその交付時期を確認しておくとよいでしょう。
手帳を持つことで受けられるサービスや割引も、自治体によって異なります。公共交通機関の運賃割引、公共施設の利用料減免、税制優遇措置などは、自治体ごとに内容や条件が異なる場合があります。例えば、ある自治体では精神障がい者保健福祉手帳の全等級で公共交通機関の割引が受けられる一方、別の自治体では1級と2級のみが対象となっている場合もあります。
一部の自治体では、独自の支援制度を設けています。医療費助成、住宅支援、就労支援など、国の制度に加えて自治体独自の支援を提供している場合があります。これらの情報は、各自治体のホームページや窓口で確認できます。お住まいの自治体でどのような支援が受けられるのか、事前に調べておくことをお勧めします。
自治体によっては、精神障がい者保健福祉手帳と自立支援医療の同時申請手続きを行えるところもあります。これにより、申請の手間を省くことができます。また、郵送による手帳の受け取りが可能な自治体もあります。自分の住む自治体がどのようなサービスや手続きを提供しているか、申請前に確認しておくことで、より効率的に手続きを進めることができます。
申請を検討されている方へのアドバイス
精神障がい者保健福祉手帳の申請を迷っている方は、まず主治医や医療機関のソーシャルワーカー、お住まいの市区町村の担当窓口に相談することをお勧めします。自分の症状や生活状況に応じて、手帳を取得することでどのようなメリットがあるのか、どのような支援やサービスを利用できるのかを具体的に知ることができます。
また、手帳を取得しないという選択肢もあります。手帳がなくても利用できる支援やサービスもありますので、自分に合った支援の形を見つけることが大切です。手帳の取得は任意であり、強制されるものではありません。メリットとデメリットを十分に理解した上で、自分にとって最適な選択をすることが大切です。
申請から交付までには2ヶ月から3ヶ月程度かかることを念頭に、早めの準備を心がけましょう。診断書の作成期間も含めると、さらに時間がかかります。就職活動や各種サービスの利用で手帳が必要な時期が決まっている場合は、逆算してスケジュールを立てることが重要です。申請書類に不備があると審査に時間がかかるため、必要書類をすべて揃え、記入漏れがないか確認しましょう。
一度取得した後でも返還することは可能ですので、まずは取得してみて、実際に活用しながら判断するという方法もあります。精神障がいと向き合いながら、より良い生活を送るために、精神障がい者保健福祉手帳という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。手帳を取得することで、税制優遇や交通費の割引、就労支援など、様々な支援を受けることができ、日常生活の質の向上につながる可能性があります。

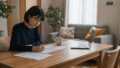

コメント