精神疾患の治療には長期間にわたる通院と服薬が必要となるケースが多く、医療費の負担が患者さんやご家族にとって大きな課題となっています。そのような中で、自立支援医療制度は精神疾患で継続的な通院治療を必要とする方々の経済的負担を大幅に軽減する重要な公的支援制度です。この制度を利用することで、通常3割の医療費自己負担が1割に減額され、さらに所得に応じた月額上限額が設定されるため、安心して治療を継続することができます。しかし、制度の対象者となるための条件や、どのような診断名が該当するのか、申請にはどのような要件が必要なのかについて、詳しく理解している方は意外と少ないのが実状です。本記事では、2025年現在の最新情報に基づき、自立支援医療制度の対象者の条件、対象となる診断名、利用するための具体的な要件について徹底的に解説します。これから申請を考えている方、すでに利用中で更新を控えている方、ご家族の申請をサポートされる方など、すべての関係者にとって役立つ実践的な情報をお届けします。
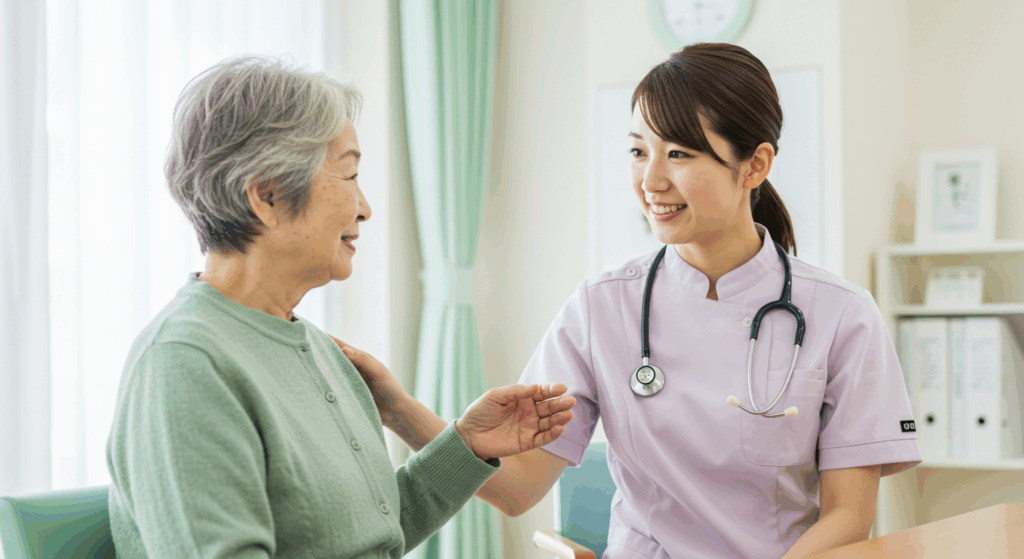
自立支援医療制度の基本的な仕組みと3つの種類
自立支援医療制度は障害者総合支援法に基づいて運営されている公費負担医療制度であり、心身の障害を除去または軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減することを目的としています。この制度には更生医療、育成医療、精神通院医療という3つの種類が存在しており、それぞれ対象者や目的が異なっています。更生医療は身体障害者手帳を持つ18歳以上の方を対象とした制度で、身体の障害を除去または軽減する手術などの治療に適用されます。育成医療は身体に障害のある18歳未満の児童を対象としており、障害の除去や軽減を目的とした医療に利用できます。そして精神通院医療は、精神疾患を有し通院による治療を継続的に必要とする方を対象とした制度で、多くの精神疾患患者が利用している最も広く活用されている自立支援医療のカテゴリーです。
精神通院医療の特徴として、受給者証の有効期間が原則1年間と定められており、継続して利用するためには毎年更新申請を行う必要があります。ただし診断書の提出については2年に1度となっているため、診断書が不要な年の更新では書類準備の負担が軽減されます。また、この制度は指定自立支援医療機関でのみ利用可能であり、医療機関や薬局を事前に指定しておく必要があるという特性があります。これは制度の適正な運用を確保するための仕組みであり、利用者は申請時に通院予定の医療機関や調剤薬局をあらかじめ登録することになります。
対象者となるための基本要件と年齢制限
自立支援医療制度の精神通院医療における対象者は、精神保健福祉法第5条に規定されている統合失調症などの精神疾患を有している者で、通院による精神医療を継続的に必要とする者と定義されています。ここで重要なポイントは「継続的に必要」という部分であり、一時的な症状や短期間の治療では対象とならず、ある程度長期にわたって通院治療が必要であることが要件となっています。この判断は原則として指定自立支援医療機関の医師による診断書に基づいて行われ、医師が専門的な見地から継続的な通院治療が必要と判断した場合に申請が可能となります。
対象者の年齢については制限が設けられておらず、子どもから高齢者まで、精神疾患で継続的な通院治療が必要であればどの年齢層でも制度を利用することができます。児童や思春期の発達障害、成人期のうつ病や統合失調症、高齢期の認知症など、ライフステージを問わず幅広い年齢層が対象となっており、それぞれの年代に応じた精神疾患の治療において経済的支援を受けることができます。ただし、入院医療は対象外となっており、あくまでも通院による治療が制度の適用範囲となっている点には注意が必要です。入院中の医療費については通常の医療保険制度や高額療養費制度を利用することになりますが、退院後の通院治療については自立支援医療制度を活用できます。
所得による利用条件と世帯の範囲
自立支援医療制度では所得に応じて制度の利用可否や自己負担上限額が設定されており、この所得判定が対象者となるための重要な条件の一つとなっています。2025年現在、区市町村民税の所得割が年23万5千円以上の世帯に属する方は原則として制度の対象外となっていますが、後述する「重度かつ継続」の要件に該当する場合には、令和9年3月31日までの経過措置によって一定所得以上の方でも制度を利用することが可能です。この経過措置は令和6年3月29日に公布された障害者総合支援法施行令により、従来の令和6年3月31日までという期限が令和9年3月31日まで延長されました。
所得区分の判定は個人単位ではなく世帯単位で行われるため、世帯の範囲を正しく理解することが重要です。世帯の範囲は受給者が加入している医療保険の被保険者とその被扶養者で構成され、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合は同じ保険に加入している家族全員が世帯として扱われます。一方、社会保険に加入している場合は被保険者本人と被扶養者が世帯となるため、同居している家族でも別の医療保険に加入していれば別世帯として判定されます。この世帯の考え方は所得区分の判定だけでなく、自己負担上限額の設定にも関わってくるため、申請時には正確な情報を提供することが求められます。
自己負担額については医療費の1割が基本となりますが、さらに所得に応じた月額上限額が設定されることで患者の経済的負担が軽減されます。生活保護世帯の場合は自己負担が完全に免除され、市町村民税非課税世帯で本人収入が80万円以下の場合は月額上限が2500円、本人収入が80万円を超える場合は月額上限が5000円となっています。市町村民税課税世帯では所得割の額に応じて上限が設定され、医療保険の自己負担限度額が適用されるケースもあります。
対象となる診断名とICDコード分類
自立支援医療制度の精神通院医療で対象となる疾患は、国際疾病分類であるICDに基づいて厳密に定められており、診断書に記載されるICDコードがF0からF9、およびG40に該当するものが制度の対象疾患となります。これらの分類には幅広い精神疾患が含まれており、多くの患者さんが制度を利用できる可能性があります。
F0に分類される症状性を含む器質性精神障害には、認知症やアルツハイマー病、血管性認知症などが含まれており、高齢化社会が進行する中で患者数が増加している疾患群です。これらは脳の器質的な変化によって生じる精神症状を対象としており、進行性の疾患であることが多いため長期的な通院治療と服薬管理が必要とされます。認知症の周辺症状である行動心理症状に対する薬物療法なども、この分類に含まれる治療として自立支援医療の対象となります。
F1は精神作用物質使用による精神および行動の障害であり、アルコール依存症や薬物依存症が該当します。依存症の治療は非常に長期間を要することが多く、再発のリスクも高いため継続的な医療的支援が不可欠です。依存症からの回復には専門的な治療プログラムと継続的な通院が必要であり、経済的負担の軽減によって治療継続率が向上することが期待されています。近年では依存症に対する社会的理解も深まりつつあり、適切な治療を受けることで回復が可能な疾患として認識されるようになってきました。
F2の統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害は、自立支援医療制度を利用する患者数が最も多い疾患群の一つです。統合失調症は慢性的な経過をたどることが多く、症状が安定した後も再発予防のために長期的な抗精神病薬の服用と定期的な通院が必要とされます。薬物療法に加えて精神科リハビリテーションや心理社会的治療も重要であり、包括的な治療アプローチが求められる疾患です。妄想性障害や統合失調症型障害についても同様に継続的な治療が必要であり、制度の対象となります。
F3は気分障害に分類され、うつ病や双極性障害が含まれています。うつ病は現代社会において非常に罹患率の高い精神疾患であり、自立支援医療制度の利用者も多い診断名です。抗うつ薬による薬物療法と精神療法を組み合わせた治療が一般的であり、症状の改善後も再発予防のために一定期間の服薬継続が推奨されています。双極性障害は躁状態とうつ状態を繰り返す疾患であり、気分安定薬の継続的な服用が治療の中心となります。服薬を中断すると症状が再燃するリスクが高いため、生涯にわたる治療が必要となるケースも少なくありません。
F4の神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害には、パニック障害、強迫性障害、社交不安障害、心的外傷後ストレス障害などが該当します。これらの疾患は不安症状が主体となることが多く、抗不安薬や抗うつ薬による薬物療法と、認知行動療法などの精神療法を組み合わせた治療が行われます。症状のコントロールには時間がかかることが多く、継続的な通院治療が必要です。特にPTSDは心理的トラウマに起因する疾患であり、専門的な治療が長期間にわたって必要となる場合があります。
F5の生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群では、摂食障害や睡眠障害が代表的な疾患です。摂食障害には神経性無食欲症や神経性大食症が含まれ、身体的な健康問題を伴うことも多いため、精神科医療と身体科医療の連携が重要です。治療には長期間を要することが一般的であり、栄養指導や心理療法、薬物療法を組み合わせた包括的なアプローチが必要とされます。重度の睡眠障害についても専門的な治療が継続的に必要な場合があり、生活の質の向上のために適切な治療を受けることが重要です。
F6は成人のパーソナリティおよび行動の障害であり、境界性パーソナリティ障害などが含まれます。パーソナリティ障害は対人関係の問題や感情のコントロールの困難さなどを特徴とし、精神療法を中心とした治療が行われます。治療には長期間を要することが多く、継続的な通院によって徐々に症状の改善を図っていきます。薬物療法は補助的に用いられることがあり、併存する抑うつや不安症状に対して処方されることがあります。
F7の精神遅滞は知的障害を指しており、知的障害に伴う精神症状や行動障害について精神科的な治療が必要な場合に対象となります。知的障害そのものを治療するというよりも、併存する精神症状や問題行動に対する対応が主な治療目的となります。適切な薬物療法や行動療法によって症状の軽減を図り、本人の生活の質を向上させることが治療の目標です。
F8は心理的発達の障害であり、自閉スペクトラム症、学習障害、発達性協調運動障害などの発達障害が含まれます。近年、発達障害の診断を受ける方が増加しており、自立支援医療制度を利用して治療を受ける患者も増えています。発達障害そのものに対する根本的な治療薬は存在しませんが、併存する二次障害としてのうつや不安、注意欠如多動症状などに対して薬物療法が行われることがあります。また、ソーシャルスキルトレーニングなどの支援も重要です。
F9は小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害で、注意欠如・多動症、素行障害、チック障害、分離不安障害などが該当します。ADHDについては中枢刺激薬や非刺激薬による治療が行われ、継続的な服薬と定期的な通院が必要です。チック障害には一過性のものもありますが、慢性化して長期的な治療が必要となるケースもあります。子どもの精神疾患については早期発見と早期治療が重要であり、適切な治療を継続することで症状の改善や社会適応の向上が期待できます。
G40はてんかんであり、脳の疾患として分類されますが精神科での治療も行われることがあるため、自立支援医療の精神通院医療の対象疾患とされています。てんかんは抗てんかん薬の継続的な服用によって発作をコントロールする必要があり、服薬を中断すると発作が再発するリスクが高まります。多くの患者が生涯にわたって服薬を継続する必要があるため、医療費の負担軽減が治療継続に大きく貢献します。
重度かつ継続の要件と該当条件
重度かつ継続は、自立支援医療制度の中でも特に重要な区分であり、症状が重い方や継続的に高額な医療費がかかる方を対象としています。この区分に該当すると、一定所得以上の世帯でも制度を利用できるという大きなメリットがあり、また自己負担上限額についても配慮された設定となっています。重度かつ継続に該当するためには、3つの条件のいずれかを満たす必要があります。
第一の条件は医療保険の多数該当者であることです。これは直近の12か月間に国民健康保険などの公的医療保険の高額療養費制度による給付を3回以上受けた方が該当します。高額療養費制度を繰り返し利用しているということは、それだけ医療費の負担が継続的に高額であることを客観的に示す指標となっており、医療費負担の実態に基づいた認定基準となっています。この条件で認定を受けるためには、高額療養費の支給決定通知書など多数該当を証明する書類の提出が必要となる場合があります。
第二の条件は特定の疾病に該当することです。精神通院医療の場合、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害のいずれかに該当する方が対象となります。これらの疾患は一般的に長期的な治療が必要とされ、症状も重いことが多いため、特別な配慮が必要と判断されています。統合失調症は慢性的な経過をたどることが多く、再発予防のために長期的な服薬が不可欠です。双極性障害やうつ病も再発を繰り返すことがあり、気分安定薬や抗うつ薬の継続的な服用が重要となります。てんかんについては抗てんかん薬の継続的な服用により発作をコントロールする必要があり、薬の中断は発作の再発につながるため生涯にわたる治療が必要な場合も多くあります。認知症等の脳機能障害は進行性の疾患であることが多く、症状の進行を遅らせるための治療や周辺症状への対応が継続的に必要です。薬物関連障害である依存症については回復に長期間を要し再発のリスクも高いため、継続的な医療的支援が重要となります。
第三の条件は医師の判断による認定です。3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、情動及び行動の障害、または不安及び不穏状態を示す精神障害のため、計画的・集中的な通院医療を継続的に要すると診断された方が対象となります。この計画的・集中的な通院医療には、症状の維持や悪化予防のための医療も含まれています。情動及び行動の障害としては、感情のコントロールが困難で衝動的な行動が見られる場合や、自傷行為や他害行為のリスクがある場合などが考えられます。不安及び不穏状態としては、強い不安症状が持続して日常生活に支障をきたしている場合や、落ち着きのなさや焦燥感が強い場合などが該当します。これらの症状は適切な治療を継続的に受けることで改善や安定が期待できますが、治療を中断すると急速に悪化する可能性があるため、専門医による慎重な判断が行われます。
重度かつ継続に該当する方の自己負担上限額は、所得に応じて異なる設定となっています。市町村民税非課税世帯で本人収入80万円以下の場合は5000円、80万円超の場合は10000円です。市町村民税課税世帯では所得割3万3千円未満が5000円、3万3千円以上23万5千円未満が10000円、23万5千円以上が20000円となっています。一定所得以上の世帯でも重度かつ継続に該当すれば月額20000円の上限で制度を利用できることは、継続的な治療が必要な患者にとって大きな支援となっています。
申請方法と必要書類の詳細
自立支援医療の申請は、お住まいの区市町村の担当窓口で行います。特別区地域では保健所や保健センター等が窓口となっており、市町村地域では市役所や町村役場の障害者福祉主管課等が担当しています。申請に必要な書類を正確に準備することが、スムーズな申請手続きのために重要です。
まず自立支援医療費支給認定申請書が必要です。これは各自治体で用意されている所定の様式に記入するもので、申請者本人の基本情報、加入している医療保険の詳細情報、指定を希望する医療機関や薬局の情報などを記載します。申請書の記入にあたっては、医療保険証を参照しながら正確な情報を記入することが求められます。
次に自立支援医療診断書が必要となります。これは原則として指定自立支援医療機関の医師が作成する専門の診断書で、対象疾患のICDコード、重症度、治療方針、重度かつ継続に該当するかどうかなどの詳細な医学的情報が記載されます。診断書の様式は全国共通で定められており、医師が専門的な見地から詳細な情報を記載します。診断書は新規申請時には必ず必要ですが、継続申請の場合は2年に1度の提出となるため、診断書が不要な年の更新では書類準備の負担が軽減されます。ただし受給者証の有効期間は原則1年間ですので、毎年の更新申請自体は必要です。
健康保険証のコピーも必要書類の一つです。申請者本人の保険証、および世帯の範囲を確認するために、同じ医療保険に加入している方全員の保険証のコピーが必要となる場合があります。国民健康保険に加入している場合は世帯全員分の保険証が必要となり、社会保険の場合は被保険者と被扶養者の保険証が必要です。
所得を確認するための書類として課税・非課税証明書が必要です。これは世帯の所得区分を判定し、自己負担上限額を決定するために使用される重要な書類です。1月から6月までの期間に申請する場合は前々年の所得に基づく証明書、7月から12月までの期間に申請する場合は前年の所得に基づく証明書が必要となります。ただし、マイナンバーを利用した情報連携により所得情報を行政機関間で共有できる場合は、課税証明書の提出を省略できることがあります。
マイナンバー関連書類としては、個人番号確認書類と本人確認書類が必要です。個人番号確認書類にはマイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票などがあります。本人確認書類にはマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などが該当します。マイナンバーカードを持っている場合は、それ1枚で個人番号確認と本人確認の両方ができるため便利です。
重度かつ継続に該当する場合で医療保険の多数該当を証明する必要がある場合は、高額療養費の支給決定通知書など多数該当を証明する書類が必要となることがあります。加入している医療保険の保険者から発行される書類を準備する必要があります。
申請から受給までの流れと更新手続き
申請書類を窓口に提出すると、自治体による審査が開始されます。審査には通常2か月から3か月程度の時間がかかるため、余裕をもって申請することが推奨されます。審査では申請内容の確認、診断書の内容の精査、所得区分の判定などが行われ、制度の要件を満たしているかどうかが慎重に検討されます。
審査の結果、認定されると自立支援医療受給者証が交付されます。受給者証には受給者番号、有効期間、対象となる医療機関・薬局、自己負担上限月額などの重要な情報が記載されています。この受給者証を医療機関や薬局に提示することで、制度による医療費の軽減を受けることができます。受給者証と併せて自己負担上限額管理票も交付され、これは月々の医療費負担額を管理するために使用されます。
有効期間は原則として1年間で、通常は申請月の1日から1年後の月末までとなります。例えば4月15日に申請した場合、認定されれば4月1日から翌年3月31日までが有効期間となることが一般的です。ただし自治体により取り扱いが異なる場合があるため、詳細は申請先の窓口で確認することが必要です。
申請から受給者証の交付までに時間がかかるため、その間に受診した場合の医療費については、いったん通常の自己負担額を支払い、後日受給者証が交付された後に償還払いの手続きを行うことができる場合があります。償還払いの取り扱いについては自治体により異なるため、申請時に窓口で確認しておくことが重要です。
継続申請(更新申請)は有効期限の3か月前から受け付けています。有効期限が切れる前に余裕をもって申請することが強く推奨されます。更新申請の手続きを忘れると制度を継続して利用できなくなり、有効期限が切れてから更新申請をした場合は新規申請と同じ扱いとなり、認定されるまでの間は通常の自己負担額を支払うことになるため注意が必要です。
更新申請では診断書は2年に1度の提出となりますが、その他の申請書類は毎年必要です。所得区分を判定するための所得情報も毎年確認され、前年の所得状況に応じて自己負担上限額が変更になることがあります。また、指定医療機関や薬局に変更がある場合は、更新時に変更することができます。
制度利用時の重要な注意事項
自立支援医療制度を利用する際には、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。まず、指定自立支援医療機関でのみ利用可能であるという制限があります。受給者証に記載された医療機関や薬局以外では制度を利用することができず、指定外の医療機関で受診した場合は通常の3割負担となってしまいます。
医療機関や薬局は申請時にあらかじめ指定する必要があり、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションなど利用する可能性のあるところをすべて指定しておく必要があります。ただし指定できる数には制限がある場合があるため、主に利用する医療機関等を優先的に選んで指定します。指定医療機関を変更したい場合は変更届を提出する必要があり、変更届が受理され新しい受給者証が交付されるまでは変更後の医療機関では制度を利用できないため、計画的に手続きを進めることが重要です。
対象となる医療は精神疾患とそれに関連する医療に限られます。同じ医療機関であっても精神疾患以外の診療については制度の対象外となります。例えば精神科クリニックで風邪の治療を受けた場合、その医療費は通常の負担割合となります。診療明細をよく確認し、どの診療が自立支援医療の対象となるのかを理解しておくことが大切です。
入院医療は対象外であることも重要な注意点です。自立支援医療の精神通院医療はあくまでも通院による治療が対象であり、入院した場合の医療費には適用されません。入院が必要になった場合は通常の医療保険による負担となり、高額療養費制度などを利用することになります。ただし入院から退院した後の通院治療については、引き続き自立支援医療制度を利用できます。
受給者証の有効期限が切れた後は制度を利用できません。更新申請を忘れないよう有効期限を確認し、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。スマートフォンのカレンダーアプリなどでリマインダーを設定しておくことが有効です。有効期限が切れてから更新申請をした場合、新たに認定されるまでの間は制度を利用できず通常の自己負担額を支払うことになります。
住所や氏名、加入している医療保険に変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。特に医療保険が変わると世帯の範囲や所得区分が変わる可能性があり、自己負担上限額が変更になることがあります。転職や結婚、離婚などで医療保険が変更になった場合は、必ず届け出るようにしましょう。
所得区分の判定に用いる所得は毎年7月に切り替わります。前年の所得に基づいて判定されるため、所得が変動した場合は7月から自己負担上限額が変わることがあります。所得が増えて区市町村民税の所得割が23万5千円以上になった場合、重度かつ継続に該当しなければ制度を利用できなくなる可能性があるため、所得の変動がある場合は注意が必要です。
2025年現在の制度改正と経過措置の延長
自立支援医療制度は時代のニーズや社会状況の変化に応じて制度の見直しが行われています。2025年現在、特に重要な点は一定所得以上の方に関する経過措置の延長です。区市町村民税の所得割が年23万5千円以上の世帯の方は原則として自立支援医療の対象外となっていますが、重度かつ継続に該当する場合は経過措置により対象となっています。
この経過措置は当初の予定では令和6年3月31日までとされていましたが、令和6年3月29日に公布された障害者総合支援法施行令により、令和9年3月31日まで延長されることになりました。これにより2025年現在も、一定所得以上の世帯で重度かつ継続に該当する方は引き続き制度を利用することができ、月額20000円の自己負担上限で医療費の軽減を受けられます。
この経過措置の延長は、精神疾患で継続的な治療が必要な方にとって治療を継続しやすくするための重要な配慮です。精神疾患の治療は長期にわたることが多く、経済的な負担が治療中断の原因とならないようにすることが制度の重要な目的の一つとなっています。令和9年3月31日以降の取り扱いについては今後の制度改正により決定されることになりますが、患者団体や医療関係者からはさらなる延長や恒久化を求める声も上がっています。
また、デジタル化の推進により、マイナンバーを活用した申請手続きの簡素化が進められています。マイナンバーによる情報連携により課税証明書などの添付書類を省略できるケースが増えており、申請者の負担軽減が図られています。オンライン申請については自治体により対応状況が異なりますが、今後さらにデジタル化が進むことで申請手続きがより便利になることが期待されています。
制度活用のメリットと他の支援制度との併用
自立支援医療制度を活用することで、精神疾患の治療を継続的に受けやすくなります。医療費の負担が軽減されることで、経済的な理由による治療中断を防ぐことができ、これは患者本人だけでなく家族や社会にとっても大きなメリットとなります。
精神疾患の治療において服薬や通院を継続することは非常に重要です。症状が改善しても治療を中断すると再発するリスクが高い疾患が多いため、安定した状態を維持するためにも継続的な治療が必要です。通常3割の自己負担が1割に軽減され、さらに月額上限額が設定されることで、毎月の医療費負担が大幅に減少します。特に複数の薬を服用している場合や頻繁に通院が必要な場合は、負担軽減の効果が非常に大きくなります。
制度の利用により経済的な不安が軽減されることで、治療に専念しやすくなります。医療費の心配をすることなく医師の指示通りに服薬や通院ができることは、治療効果を高めることにつながります。また、自立支援医療制度の申請をすることで、精神障害者保健福祉手帳の申請も検討するきっかけになることがあります。
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、税制上の優遇措置や公共交通機関の割引、各種サービスの利用など、さまざまな支援を受けることができます。自立支援医療の診断書と精神障害者保健福祉手帳の診断書は様式が異なりますが、同時期に申請する場合は同じ医師に両方の診断書を作成してもらうことができます。制度を組み合わせて活用することでより充実した支援を受けることが可能になります。
障害年金との併用も重要な選択肢です。障害年金は病気やケガで生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる年金で、精神疾患により日常生活や就労に支障がある場合は障害年金の対象となる可能性があります。障害年金を受給することで経済的な安定が得られ、治療に専念しやすくなります。
生活保護制度を利用している方も自立支援医療制度を併用でき、生活保護受給者の場合は自己負担額が0円となり医療費の自己負担はありません。また、介護保険制度との関係では、65歳以上の方や40歳以上65歳未満で特定疾病に該当する方は介護保険のサービスを利用できる場合があり、認知症などの精神疾患を有する高齢者の場合は自立支援医療制度による医療費の軽減と介護保険サービスによる介護支援の両方を受けることができます。
精神疾患は決して特別なものではなく、誰でもかかる可能性のある病気です。適切な治療を受けることで症状をコントロールし、社会生活を送ることができます。自立支援医療制度はそのための重要な支援制度であり、制度の利用を検討している方はまず主治医に相談してみることをお勧めします。主治医が制度の対象となると判断すれば診断書を作成してもらい、申請手続きを進めることができます。お住まいの自治体の窓口でも制度についての説明や申請方法の案内を受けることができます。

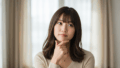
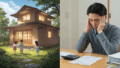
コメント