障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、障害のある方が福祉サービスや医療費助成、税制優遇などの支援を受けるために欠かせない証明書となっています。これらの手帳は、日常生活や社会参加を支える重要な役割を果たしていますが、手帳の種類によって更新手続きの有無や頻度、必要書類が大きく異なるため、正確な知識を持って適切に管理することが求められます。特に精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必須であり、更新を怠ると医療費助成や各種割引サービスが利用できなくなるリスクがあります。一方、身体障害者手帳は原則として更新不要ですが、一部のケースでは再認定が求められることもあります。本記事では、障害者手帳の更新手続きにおける期間の目安、必要書類の詳細、手続きの流れ、注意すべきポイントまで、実践的な情報を網羅的に解説します。更新期限を過ぎてしまった場合の対処法や、各自治体による手続きの違い、診断書作成時の重要なポイントについても触れ、手帳を持つすべての方が安心して更新手続きを進められるよう、わかりやすくサポートします。

障害者手帳の種類と更新の必要性
障害者手帳には、対象となる障害の種類によって3つのタイプが存在し、それぞれ更新の要否や頻度が異なる制度設計となっています。
身体障害者手帳は、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能の障害)などを持つ方を対象としています。この手帳の最大の特徴は、原則として更新手続きが不要である点です。身体障害は恒久的な状態であることが多く、一度交付されれば基本的に生涯有効となります。ただし、障害の程度が変化する可能性があると判断された場合や、医師が将来的に障害の軽減を予想する場合には、手帳に再認定の時期が記載されることがあり、この場合は指定された時期に再度障害の認定を受ける必要があります。再認定の時期は、手帳交付時から1年以上5年以内に設定されるのが一般的で、再認定時期の約2か月前には障害者更生相談所から診断書用紙や案内の通知が届きます。
療育手帳は、知的障害のある方を対象とした手帳で、自治体によっては「愛の手帳」「みどりの手帳」などの名称で呼ばれることもあります。知的障害の程度を示す等級は自治体ごとに異なる基準が用いられており、定期的な再判定が必要とされています。この手帳の更新頻度は年齢によって大きく異なるのが特徴です。18歳未満の児童の場合は、成長に伴う知的発達の変化を考慮して、児童相談所でおおむね2年から4年ごとに再判定を受ける必要があります。一方、18歳以上の成人の場合は、知的障害の状態が比較的安定していることから、知的障害者更生相談所でおおむね10年ごとに再判定を受けることになっています。ただし、この期間はあくまで目安であり、自治体や個々の状況によって異なる場合があるため、手帳に記載されている次回判定日を必ず確認しておくことが重要です。
精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、発達障害、高次脳機能障害、薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症など、様々な精神疾患を持つ方を対象としています。この手帳の有効期限は2年間と明確に定められており、2年ごとに必ず更新手続きが必要となります。3種類の障害者手帳の中で最も頻繁に更新手続きが求められる手帳であり、更新を怠ると手帳の効力が失効し、医療費助成や各種割引サービスが利用できなくなってしまいます。精神障害は症状の変化や治療経過によって障害の程度が変わりやすいため、定期的な再評価が必要とされているのです。
精神障害者保健福祉手帳の更新期間と手続き
精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要なため、更新手続きの期間について正確に理解しておくことが極めて重要です。
更新可能期間は、有効期限の3か月前から更新手続きを開始できる仕組みになっています。具体的には、有効期限の翌日から3か月前の月の初日から、有効期限後3か月以内の間に申請が可能です。例えば、手帳の有効期限が2025年10月31日の場合、2025年8月1日から2026年1月31日までの間に更新申請を行うことができます。この期間設定により、申請者は余裕を持って手続きを進めることができるようになっています。
ただし、更新申請から新しい手帳が交付されるまでには一定の審査期間が必要となります。紙形式の手帳の場合は約2か月程度、カード形式の手帳の場合は約2か月半程度の期間がかかります。この審査期間は、自治体の処理状況や申請が集中する時期によって前後することがあり、場合によってはさらに時間がかかることもあります。そのため、有効期限ぎりぎりに申請すると、新しい手帳が交付される前に有効期限が切れてしまい、一時的に手帳を使用できない期間が発生してしまう可能性があります。
こうしたリスクを避けるためには、有効期限の3か月前になったらすぐに手続きを開始することが強く推奨されます。遅くとも有効期限の1か月前までには申請を完了させることが望ましいでしょう。特に、医療費助成や障害者雇用での就労など、手帳を日常的に利用している方にとって、手帳が使えない期間が発生することは大きな不利益につながります。計画的に余裕を持った申請スケジュールを組むことが、安心して福祉サービスを継続利用するための鍵となります。
また、有効期限が切れてしまった場合でも、有効期限後3か月以内であれば更新手続きを行うことができます。ただし、この期間中は手帳の効力が一時的に失われているため、医療費助成や各種割引などの福祉サービスを利用することができません。障害者雇用で働いている場合は、雇用主に状況を説明する必要が生じることもあります。更新を忘れないための工夫として、手帳の有効期限をスマートフォンのカレンダーやリマインダーアプリに登録し、3か月前と1か月前に通知が来るように設定しておくことをお勧めします。
精神障害者保健福祉手帳の更新に必要な書類
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きには、いくつかの書類を用意する必要があります。事前に必要書類を把握し、余裕を持って準備することが円滑な手続きにつながります。
まず、精神障害者保健福祉手帳申請書が必要です。この申請書は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で入手できるほか、多くの自治体ではホームページからPDF形式でダウンロードすることも可能です。申請書には、氏名、住所、生年月日、障害の状況、希望する等級、連絡先などの基本情報を記入します。記入漏れや誤記があると手続きが遅れる原因となるため、丁寧に正確に記入することが大切です。
次に、医師の診断書または年金関連書類が必要となります。診断書を提出する場合は、精神障害者保健福祉手帳用の専用診断書を用意する必要があります。この診断書は、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後に作成され、かつ作成日が申請日から3か月以内のものでなければなりません。診断書には、診断名、初診日、現在の症状、治療内容、服薬状況、日常生活能力の判定、就労状況などが詳細に記載されます。診断書の作成には費用がかかり、医療機関によって異なりますが、一般的に3000円から10000円程度の費用が必要です。例えば、和こころクリニックでは2025年4月時点で6000円、養神館病院では3300円、はたらく人・学生のメンタルクリニックでは9500円(税込)となっています。診断書の作成には通常1週間から2週間程度の時間がかかるため、余裕を持って主治医に依頼することが重要です。
診断書の代わりに、精神障害を支給事由とした障害年金または特別障害給付金を現に受給していることを証する書類の写しを提出することもできます。具体的には、年金証書、年金振込通知書、年金支払通知書、特別障害給付金受給資格者証などの写しです。障害年金を受給している方は、診断書を新たに取得する必要がないため、費用面での負担を大きく軽減できます。ただし、年金の等級と手帳の等級は必ずしも一致するわけではなく、手帳の等級は別途審査されることになります。
写真も必要書類の一つです。サイズは縦4センチメートル×横3センチメートルで、申請日から6か月以内に撮影されたものを用意します。写真は上半身を写したもので、帽子やサングラスを着用していない、正面を向いたものが求められます。背景は無地が望ましく、写真館やスピード写真機で撮影するのが確実です。写真は手帳に貼付されるため、本人確認ができる鮮明なものを用意しましょう。最近では、デジタルカメラやスマートフォンで撮影した写真を使用できる場合もありますが、自治体によって基準が異なるため、事前に確認することをお勧めします。
本人確認書類も必要です。運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書が一般的です。顔写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証や年金手帳など、複数の書類の組み合わせで本人確認を行う場合もあります。自治体によって求められる書類が異なることがあるため、申請前に窓口に確認しておくと安心です。
マイナンバー関連書類の提出も必要です。マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードのコピー(表面と裏面)を提出します。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバー通知カードのコピーまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを提出します。マイナンバーの提供には、本人確認のための身分証明書も併せて必要となるため、忘れずに用意しましょう。
そして、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳も持参する必要があります。更新手続きの際には、現在の手帳を返納することになります。手帳番号などの情報が必要となるため、必ず持参するようにしてください。
更新手続きの具体的な流れ
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きは、計画的に進めることでスムーズに完了させることができます。以下、手続きの流れを段階的に解説します。
第一段階は、必要書類の準備です。有効期限の3か月前になったら、更新に必要な書類の準備を開始しましょう。診断書が必要な場合は、かかりつけの精神科医または心療内科医に診断書の作成を依頼します。診療時には、現在の症状だけでなく、日常生活での具体的な困難さや治療の経過について詳しく伝えることが重要です。例えば、「朝起きられない」「買い物に行けない」「人混みが苦手」「服薬の管理が難しい」など、具体的なエピソードを交えて説明すると、医師は診断書に適切な記載をしやすくなります。診断書の作成には1週間から2週間程度かかることが多いため、余裕を持って依頼しましょう。障害年金を受給している方は、年金証書などの写しを用意します。また、申請書を自治体のホームページからダウンロードするか、窓口で入手し、必要事項を記入します。写真も忘れずに準備しましょう。
第二段階は、市区町村の障害福祉担当窓口での申請です。必要書類をすべて揃えたら、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に提出します。窓口の名称は自治体によって異なり、障害福祉課、福祉課、社会福祉課などと呼ばれています。窓口の受付時間は自治体によって異なるため、事前にホームページで確認するか、電話で問い合わせておくと安心です。多くの自治体では平日の日中のみの受付となっていますが、一部の自治体では夜間や休日の受付窓口を設けている場合もあります。また、郵送での申請が可能な自治体も増えてきており、窓口に行くことが難しい方は郵送申請を検討するとよいでしょう。申請時には、窓口の担当者が書類の記入漏れや不備がないか確認してくれます。不明な点があれば、この時に質問することができます。
第三段階は、審査期間です。申請後、都道府県または政令指定都市の精神保健福祉センターなどで審査が行われます。審査では、提出された診断書の内容や年金関連書類に基づいて、手帳の交付要件を満たしているか、どの等級に該当するかが判定されます。紙形式の手帳の場合は約2か月程度、カード形式の手帳の場合は約2か月半程度の期間が必要です。この期間は、自治体の処理状況や申請が集中する時期によって前後することがあります。特に年度末や年度始めなど、申請が多い時期には通常より時間がかかる場合もあります。審査期間中は、申請者側で特に行うことはありませんが、もし追加の書類が必要になった場合は、自治体から連絡が来ることがあります。
第四段階は、新しい手帳の交付です。審査が完了すると、市区町村から交付準備が整った旨の連絡がありますので、指定された窓口で新しい手帳を受け取ります。手帳の受け取りには、本人確認書類が必要です。代理人が受け取る場合は、委任状や代理人の本人確認書類も必要となります。新しい手帳を受け取ったら、記載内容に誤りがないか必ず確認しましょう。氏名、生年月日、住所、等級、有効期限などが正しく記載されているか、写真が適切に貼付されているかをチェックします。もし誤りがあった場合は、すぐに窓口に申し出てください。
更新手続きにおける重要な注意点
更新手続きを円滑に進めるためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。
最も重要なのは、期限内に必ず手続きを行うことです。有効期限内に更新手続きを完了させないと、手帳の効力が失効してしまいます。手帳が失効すると、自立支援医療制度による医療費助成、特別障害者手当などの各種手当、所得税や住民税の障害者控除、自動車税の減免、公共交通機関の運賃割引、携帯電話料金の割引、NHK受信料の減免など、現在利用している多くの福祉制度が使えなくなってしまいます。特に医療費助成が受けられなくなると、治療費の負担が大きく増加してしまうため、経済的な影響も深刻です。また、障害者雇用で働いている方の場合、手帳が失効すると雇用関係に影響が出る可能性もあります。再度手帳を取得するには、新規申請と同様の手続きが必要となり、時間と手間がかかります。
審査期間を考慮して早めに申請することも大切です。手帳の交付には2か月以上の時間がかかるため、有効期限ぎりぎりに申請すると、新しい手帳が交付される前に有効期限が切れてしまう可能性があります。有効期限の3か月前から申請可能ですので、できるだけ早めに手続きを開始しましょう。特に、年度末や年度始め、ゴールデンウィークや年末年始の前後など、行政機関が混雑する時期には通常より審査に時間がかかる場合があるため、より一層の余裕を持った申請が求められます。
診断書の有効期間にも注意が必要です。診断書は作成日から3か月以内のものでなければなりません。あまり早く診断書を取得してしまうと、申請するまでに3か月を過ぎてしまい、診断書が使えなくなってしまう可能性があります。逆に、診断書の取得が遅れると、申請期限に間に合わなくなるリスクもあります。申請のタイミングを見計らって、適切な時期に診断書を取得する必要があります。目安としては、申請予定日の2週間から1か月前に診断書の作成を依頼するとよいでしょう。また、診断書は精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後に作成されたものでなければならないという条件もあります。初診から6か月未満の方は診断書による申請ができないため、この点にも注意が必要です。
等級の変更を希望する場合の対応についても知っておきましょう。更新時に、障害の状態が変化している場合は、等級の変更を申請することができます。症状が重くなった場合は上位の等級へ、症状が軽くなった場合は下位の等級への変更が認められる可能性があります。等級の変更を希望する場合は、その旨を申請書に記載し、現在の障害の状態を正確に反映した診断書を提出する必要があります。主治医には、症状の変化について具体的に説明し、診断書にその内容を反映してもらうことが重要です。ただし、等級の判定は提出された診断書の内容に基づいて行われるため、必ずしも希望通りの等級になるとは限りません。
有効期限後でも一定期間内であれば更新可能な場合があります。万が一、有効期限内に更新手続きができなかった場合でも、有効期限後3か月以内であれば更新手続きを行うことができます。ただし、この期間中は手帳の効力が一時的に失われているため、福祉サービスの利用に支障が出る可能性があります。医療費助成や各種割引が受けられず、経済的な負担が増加してしまいます。できる限り有効期限内に手続きを完了させることが重要です。有効期限後3か月を過ぎてしまった場合は、更新ではなく新規申請として手続きを行う必要があり、手続きには同様に2か月程度の時間がかかります。
身体障害者手帳の再認定について
身体障害者手帳は、原則として更新手続きが不要な手帳ですが、一部のケースでは定期的な再認定が必要となります。
身体障害は一般的に恒久的な状態であることが多いため、一度交付されると基本的には生涯有効となります。そのため、精神障害者保健福祉手帳のような定期的な更新手続きは不要です。これは、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害などの多くが、時間の経過とともに回復する可能性が低いことが理由です。
ただし、すべての場合において更新が不要というわけではありません。障害の状態が変化する可能性がある場合や、将来的に障害が軽減されることが予想される場合には、手帳に再認定の時期が記載されることがあります。例えば、成長期にある児童の場合、身体の発達に伴って障害の程度が変化する可能性があります。また、リハビリテーションによる機能回復が期待される場合や、医療技術の進歩により治療効果が見込まれる場合なども、再認定の対象となることがあります。内部障害の場合、人工透析を受けている方や心臓疾患のある方など、医学的な治療により状態が変化する可能性がある場合に再認定が設定されることがあります。
再認定の時期は、手帳交付時から1年以上5年以内に指定されるのが一般的です。再認定時期の約2か月前には、障害者更生相談所から診断書用紙や案内の通知が届きます。この通知を受け取ったら、速やかに再認定の手続きを開始する必要があります。正当な理由なく再認定の手続きを行わない場合は、手帳の返還を求められることがあるため、注意が必要です。
再認定が必要な場合は、手帳に次回認定日が記載されています。この日が近づいたら、市区町村の障害福祉担当窓口に連絡し、再認定の手続きについて確認しましょう。再認定では、指定医による診断書の提出が必要となります。指定医とは、都道府県知事または指定都市市長から指定を受けた、身体障害の診断に関する専門的知識を持つ医師のことです。指定医のリストは、市区町村の障害福祉担当窓口や都道府県のホームページで確認することができます。
再認定の手続きに必要な書類は、指定医師が作成した診断書、顔写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)、マイナンバーがわかるもの(個人番号カードなど)、本人確認書類(運転免許証など)、現在お持ちの身体障害者手帳です。これらの書類を揃えて、お住まいの市町村の障害福祉担当窓口で申請を行います。
再認定の結果、障害の程度が軽減されて障害程度等級表に満たないレベルになった場合は、手帳を返納する必要があります。これは、障害者手帳が一定以上の障害を持つ方を支援するための制度であるためです。逆に、障害の程度に変化がない場合や悪化した場合は、引き続き手帳を使用することができます。等級が変更になる場合は、新しい等級の手帳が交付されます。
また、再認定の時期以外でも、障害の程度が変化した場合には、等級の変更申請を行うことができます。例えば、障害が重度化した場合は上位の等級への変更を、リハビリテーションなどにより障害が軽減した場合は下位の等級への変更を申請できます。等級の変更には、現在の障害の状態を示す指定医の診断書が必要です。障害の状態に変化があった場合は、早めに市区町村の窓口に相談しましょう。
療育手帳の更新制度
療育手帳は、知的障害のある方を対象とした手帳で、定期的な再判定が制度として組み込まれています。
療育手帳の特徴として、名称が自治体によって異なることが挙げられます。東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」、横浜市では「愛の手帳」、名古屋市では「愛護手帳」など、地域によって様々な名称が使われています。また、等級の区分方法も自治体ごとに異なり、A・Bの2区分、A1・A2・B1・B2の4区分など、地域によって異なる基準が用いられています。
療育手帳の更新頻度は年齢によって大きく異なります。18歳未満の児童の場合、児童相談所でおおむね2年から4年ごとに再判定を受ける必要があります。これは、成長期にある児童の知的発達の状態は変化する可能性があるためです。幼児期から学童期にかけては特に発達の変化が大きく、教育や療育の効果によって知的機能が向上することもあります。再判定の時期は、手帳に記載されていますので、その時期が近づいたら児童相談所に連絡して再判定の予約を取りましょう。
一方、18歳以上の成人の場合は、知的障害者更生相談所でおおむね10年ごとに再判定を受けます。成人の場合は知的障害の状態が比較的安定していることが多いため、児童期よりも更新の間隔が長く設定されています。ただし、この期間はあくまで目安であり、自治体によって異なる場合があります。また、障害の状態に大きな変化があった場合は、再判定の時期を待たずに等級の変更申請を行うことも可能です。
療育手帳の更新手続きには、再判定が必須です。再判定では、知能検査や面接、場合によっては行動観察などを通じて、現在の知的障害の程度を総合的に評価します。知能検査では、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、処理速度などの能力が測定され、知能指数(IQ)が算出されます。面接では、日常生活能力、社会適応能力、コミュニケーション能力などについて確認されます。再判定の結果、障害の程度に変化がある場合は、等級が変更されることもあります。
再判定の予約は、早めに取ることをお勧めします。児童相談所や知的障害者更生相談所は混雑している場合が多く、希望する日時に予約が取れないこともあります。特に、学校の長期休暇期間や年度末などは予約が集中しやすい時期です。手帳に記載されている次回判定日の数か月前には連絡を取り、予約を確保しましょう。再判定には半日程度の時間がかかることが多いため、スケジュールに余裕を持って予約を取ることが大切です。
再判定に必要な持ち物は、現在お持ちの療育手帳、健康保険証、印鑑などです。自治体によって必要な持ち物が異なる場合があるため、予約時に確認しておきましょう。また、児童の場合は、学校での様子がわかる資料(通知表や個別の教育支援計画など)を持参すると、より適切な判定につながることがあります。
手帳更新時の等級判定
障害者手帳には、障害の程度に応じて等級が設定されており、等級によって受けられる福祉サービスや支援の内容が異なる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳の場合、1級から3級までの等級があります。1級が最も重度の障害で、3級が最も軽度の障害となります。1級は「精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」とされ、常時の援助が必要な状態を指します。具体的には、食事や入浴、着替えなどの日常的な行為に常に援助が必要で、単独での外出も困難な状態です。2級は「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされ、日常生活に大きな制限がある状態を指します。例えば、金銭管理や服薬管理に援助が必要で、就労は困難または相当な配慮が必要な状態です。3級は「精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」とされ、日常生活や社会生活に一定の制限がある状態を指します。就労は可能ですが、障害への配慮が必要な状態です。
更新時には、現在の障害の状態に基づいて等級が判定されます。障害の状態が変化している場合は、等級が変更される可能性があります。症状が悪化している場合は上位の等級に、症状が改善している場合は下位の等級に変更されることがあります。また、医師の判断によっては、手帳の交付要件を満たさないと判断され、手帳が交付されない場合もあります。これは、治療により症状が大きく改善し、日常生活や社会生活に制限がほとんどなくなった場合などです。
等級の判定は、提出された診断書の内容に基づいて行われます。そのため、診断書には現在の障害の状態を正確に記載してもらうことが重要です。日常生活での困難さや症状の変化などを、主治医に詳しく伝えましょう。診察室での短時間の様子だけでは、日常生活での実際の困難さが伝わらないことがあります。具体的なエピソードを交えて説明することで、医師は診断書により適切な記載をすることができます。例えば、「週に何回パニック発作が起こるか」「外出できる範囲はどの程度か」「家事や買い物はどの程度できるか」「対人関係でどのような困難があるか」といった具体的な情報を伝えることが大切です。
身体障害者手帳の場合は、1級から6級までの等級があり、障害の種類や程度によって細かく区分されています。療育手帳の場合は、自治体によって等級の区分方法が異なりますが、一般的に重度(A)と軽度(B)、または最重度(A1)、重度(A2)、中度(B1)、軽度(B2)などに区分されています。
手帳を利用できる福祉サービスの詳細
障害者手帳を持っていると、様々な福祉サービスや支援を受けることができ、日常生活や社会参加を支える重要なツールとなります。
医療費の助成制度として、自立支援医療制度があります。精神障害の治療にかかる医療費の自己負担額を軽減する制度で、通常3割の自己負担が、所得に応じて1割または上限額までに軽減されます。継続的に精神科の治療を受けている方にとって、医療費の負担を大幅に減らすことができる重要な制度です。自立支援医療の対象となるのは、通院による精神科の治療費、デイケアやカウンセリングの費用、精神科の薬代などです。入院費用は対象外となるため注意が必要です。
各種手当の支給も受けられます。特別障害者手当は、20歳以上で著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当で、月額約27,980円(2025年度)が支給されます。障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする児童に支給される手当で、月額約15,220円(2025年度)が支給されます。ただし、これらの手当には所得制限や障害の程度の要件があります。また、東京都の重度心身障害者手当など、一部の自治体では独自の手当制度を設けている場合もあります。
税制上の優遇措置も多数あります。所得税では、障害者控除として27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除されます。住民税でも同様に、障害者控除として26万円(特別障害者の場合は30万円)が控除されます。相続税では、障害者が相続人である場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。また、自動車税や軽自動車税の減免を受けられる場合もあり、障害者本人または生計を一にする方が所有する自動車で、障害者の通院や通学などに使用される場合に減免の対象となります。
公共交通機関の運賃割引も重要なサービスです。JRでは、精神障害者保健福祉手帳の場合、1級の方は本人と介護者が普通乗車券の5割引を受けられます。私鉄やバスでも、多くの事業者で割引制度が用意されており、割引率は事業者によって異なりますが、5割引が一般的です。タクシーでも、一部の事業者や自治体で割引制度があります。航空会社でも、国内線の航空運賃が割引になる制度があり、本人と介護者(1名)が対象となります。
公共施設の利用料金の減免も受けられます。博物館、美術館、動物園、水族館などの公共施設の入場料が無料または割引になる場合があります。例えば、国立博物館や国立美術館では、障害者手帳を提示すると本人と介護者1名が無料で入場できます。地方自治体が運営する施設でも同様の制度があることが多く、文化的な活動やレクリエーションを楽しむ機会が広がります。
携帯電話料金の割引サービスも提供されています。NTTドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルなどの大手携帯電話会社では、障害者手帳を持っている方向けの料金プランや割引サービスを用意しています。基本料金の割引や通話料の割引など、内容は各社で異なりますが、月々の通信費を抑えることができます。
駐車禁止除外指定車標章の交付も受けられます。歩行が困難な方は、駐車禁止区域でも駐車できる標章の交付を受けることができます。この標章は、都道府県公安委員会が交付するもので、標章を車内に掲示することで、駐車禁止区域や時間制限のある駐車区域でも駐車が可能になります。外出時の利便性が大きく向上します。
NHK受信料の減免制度もあります。世帯構成員全員が市町村民税非課税で、かつ世帯の中に障害者がいる場合は全額免除、精神障害者保健福祉手帳1級または身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度)を持つ方が世帯主で受信契約者の場合は半額免除が適用されます。
これらの福祉サービスを活用することで、経済的な負担を軽減し、より豊かな生活を送ることができます。利用できるサービスは自治体や等級によって異なるため、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談し、利用可能なサービスについて確認することをお勧めします。
手帳更新を忘れた場合の対処法
万が一、手帳の更新を忘れてしまった場合でも、適切に対処することで再度手帳を取得することができます。
精神障害者保健福祉手帳の場合、有効期限後3か月以内であれば、更新手続きを行うことができます。この期間内に必要書類を揃えて申請しましょう。ただし、有効期限が切れている間は、手帳を使った福祉サービスを利用できないため、できるだけ早く手続きを行うことが重要です。医療費助成や各種割引が受けられず、経済的な負担が増加してしまいます。
有効期限後3か月を過ぎてしまった場合は、更新ではなく新規申請として手続きを行う必要があります。新規申請の場合も、必要書類は更新の場合とほぼ同じですが、手続きには更新と同様に2か月程度の時間がかかります。新規申請となると、手帳番号が変わる可能性があり、関連する各種サービスの登録変更が必要になる場合もあります。
手帳の効力が失効している期間中は、医療費助成や各種割引などの福祉サービスを利用できません。自立支援医療制度を利用している場合、医療費の自己負担が3割に戻ってしまうため、通院や服薬の費用が大きく増加します。また、障害者雇用で働いている場合は、雇用主に状況を説明する必要があります。障害者雇用の助成金などが一時的に受けられなくなる可能性もあるため、会社との調整が必要です。福祉サービスの利用が途切れることによる不利益を避けるためにも、更新は必ず期限内に行いましょう。
更新を忘れないための対策として、いくつかの工夫があります。手帳の有効期限をスマートフォンのカレンダーやリマインダーアプリに登録し、有効期限の3か月前と1か月前に通知が来るように設定しておくことをお勧めします。Googleカレンダーやスマートフォンの標準カレンダーアプリなどを活用すれば、確実にリマインドを受けることができます。また、手帳のコピーを取っておき、自宅の見やすい場所に貼っておくことも効果的です。冷蔵庫や玄関など、日常的に目にする場所に有効期限を記載したメモを貼っておくと、更新を忘れにくくなります。
かかりつけの医療機関に相談すれば、更新時期について助言してもらえる場合もあります。定期的に通院している方は、診察時に医師や看護師、精神保健福祉士などに更新時期を確認してもらうよう依頼しておくとよいでしょう。医療機関によっては、更新時期が近づいたら患者に連絡してくれるサービスを提供している場合もあります。
家族や支援者に更新時期を伝えておくことも有効です。一人で管理するのが難しい場合は、家族や支援者に協力してもらい、更新時期を一緒に管理してもらうことで、更新を忘れるリスクを減らすことができます。
各自治体による手続きの違い
障害者手帳の手続きは、基本的な枠組みは全国共通ですが、細かい部分では自治体によって違いがあります。
申請窓口は、ほとんどの場合、市区町村の障害福祉担当課です。ただし、課の名称は自治体によって異なります。障害福祉課、福祉課、社会福祉課、福祉支援課、保健福祉課などと呼ばれています。不明な場合は、市区町村の代表電話に問い合わせれば、適切な窓口を案内してもらえます。多くの自治体では、ホームページに障害者手帳の申請手続きについての情報が掲載されているため、事前に確認しておくとスムーズです。
申請方法も自治体によって異なります。多くの自治体では窓口での申請が基本ですが、郵送での申請を受け付けている自治体も増えています。郵送申請の場合、必要書類を封筒に入れて障害福祉担当課宛てに送付します。郵送事故を防ぐため、簡易書留や特定記録郵便など、配達記録が残る方法で送付することをお勧めします。また、最近では電子申請に対応している自治体も増えてきています。マイナポータルを利用した電子申請が可能な自治体では、自宅から24時間いつでも申請手続きができるため、非常に便利です。郵送や電子申請が可能かどうかは、お住まいの自治体のホームページで確認するか、窓口に問い合わせてください。
手帳の形式も、紙形式とカード形式があります。従来は紙形式の手帳が一般的でしたが、最近ではカード形式の手帳を導入する自治体が増えています。カード形式は、クレジットカードサイズで携帯しやすく、財布に入れて持ち歩くことができます。また、手帳の表紙に「精神障害者保健福祉手帳」などの記載がないため、プライバシーの保護にも優れています。ただし、カード形式の手帳は、紙形式よりも交付までに時間がかかる場合があります。製造工程が複雑で、専門の業者に発注する必要があるためです。どちらの形式を希望するかは、申請時に選択できる場合が多いですが、自治体によってはカード形式のみ、または紙形式のみの場合もあります。
診断書の様式も、自治体によって若干異なる場合があります。ほとんどの場合、全国共通の様式が使用されますが、一部の自治体では独自の様式を使用していることもあります。診断書を作成してもらう前に、お住まいの自治体の様式を確認し、医療機関に提供しましょう。自治体のホームページから診断書の様式をダウンロードできる場合が多いので、事前に入手して医療機関に持参することをお勧めします。
手数料については、多くの自治体では手帳の申請や交付に手数料はかかりません。障害者福祉の観点から、手続き自体に費用負担を求めないのが一般的です。ただし、診断書の作成費用は自己負担となります。診断書の作成費用は医療機関によって異なりますが、一般的に3000円から10000円程度です。また、写真の撮影費用も自己負担となります。写真館で撮影する場合は1000円から2000円程度、スピード写真機を利用する場合は800円程度の費用がかかります。
審査期間も自治体によって若干異なります。一般的には紙形式の手帳で約2か月、カード形式の手帳で約2か月半程度ですが、自治体の処理体制や申請の集中状況によって前後します。年度末や年度始めなど、申請が集中する時期には通常より時間がかかる場合があります。
更新時の診断書について
更新時に提出する診断書は、手帳取得において非常に重要な書類であり、診断書の内容によって手帳が交付されるかどうか、どの等級になるかが決まります。
診断書は、精神保健指定医または精神障害の診断や治療に従事する医師が作成します。通常は、かかりつけの精神科医や心療内科医に作成を依頼します。初めて受診する医師に診断書を依頼する場合は、これまでの治療経過や症状について詳しく説明する必要があります。可能であれば、紹介状や過去の診療記録を持参すると、医師が適切な診断書を作成しやすくなります。
診断書には、診断名、初診日、現在の症状、治療内容、日常生活能力の判定、就労状況などが記載されます。特に重要なのは、日常生活能力の判定です。食事、身辺の清潔保持、金銭管理、通院と服薬、他人との意思伝達、社会性などの項目について、「できる」「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4段階で評価されます。この評価が等級判定の重要な基準となるため、正確な評価が求められます。
診断書を作成してもらう際には、現在の症状や日常生活での困難さを正確に医師に伝えることが重要です。診察の時には症状が軽く見えても、実際の日常生活では様々な困難を抱えていることがあります。診察室という限られた時間と空間では、日常生活の実態が十分に把握できない場合があるため、具体的なエピソードを交えて、日常生活での困難さを医師に伝えましょう。例えば、「週に何回パニック発作が起こるか」「夜は何時間眠れるか」「外出できる範囲はどの程度か」「家事や買い物はどの程度できるか」「対人関係でどのような困難があるか」「仕事や学業への影響はどうか」といった具体的な情報を伝えることが大切です。
また、症状の変化についても詳しく説明しましょう。前回の診断書作成時と比べて症状が悪化している場合や、新たな症状が出現している場合は、その旨を医師に伝えることで、診断書に適切に反映してもらうことができます。逆に、症状が改善している場合も、その事実を正直に伝えることが大切です。
診断書の作成には、通常1週間から2週間程度の時間がかかります。混雑している時期や医療機関によっては、さらに時間がかかる場合もあります。更新の期限に間に合うよう、余裕を持って診断書の作成を依頼しましょう。診察時に診断書の作成を依頼し、後日受け取るという流れが一般的です。診断書ができあがったら、医療機関から連絡が来るので、受け取りに行きます。郵送で受け取れる医療機関もあるため、希望する場合は依頼時に確認してください。
診断書の作成費用は、医療機関によって異なりますが、一般的に3000円から10000円程度です。この費用は、健康保険の適用外となるため、全額自己負担となります。ただし、自立支援医療を利用している場合でも、診断書の作成費用は別途必要となります。具体的な医療機関の診断書作成費用の例としては、和こころクリニックでは2025年4月時点で6000円、養神館病院では3300円、はたらく人・学生のメンタルクリニックでは9500円(税込)となっています。このように医療機関によって費用に幅があるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
また、さいたま市など一部の自治体では、精神障害者保健福祉手帳申請用診断書料の補助制度を設けている場合があります。お住まいの自治体でそのような補助制度があるかどうか、市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。補助制度を利用できれば、診断書作成の経済的負担を軽減することができます。補助額や対象者の条件は自治体によって異なりますが、診断書作成費用の一部または全額が補助される場合があります。
よくある質問と回答
手帳の更新に関して、多くの方が抱える疑問とその回答をまとめました。
更新中に古い手帳は使えるのかという質問がよくあります。更新申請をした後、新しい手帳が交付されるまでの間も、有効期限内であれば古い手帳を使用することができます。医療費助成や各種割引などのサービスも引き続き利用可能です。ただし、有効期限が切れた後は、新しい手帳が交付されるまで手帳を使用することはできません。そのため、有効期限が切れる前に新しい手帳が交付されるよう、早めに申請することが重要です。
引っ越しをした場合の手続きについても質問が多いです。他の市区町村に引っ越した場合は、転居後の住所地で手帳の記載事項変更届を提出する必要があります。この手続きにより、手帳の住所が新しい住所に変更されます。同じ都道府県内での引っ越しの場合は、記載事項変更届の提出のみで済むことが多いです。都道府県をまたぐ引っ越しの場合は、新しい手帳の交付を受ける必要がある場合もあります。身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳は都道府県が発行するため、都道府県が変わる場合は新しい手帳の交付が必要となります。引っ越しをしたら、できるだけ早く新しい住所地の障害福祉担当窓口で手続きを行いましょう。転入届を提出する際に、障害者手帳を持っていることを伝えると、必要な手続きについて案内してもらえます。
氏名が変わった場合も、記載事項変更届の提出が必要です。結婚や離婚などで氏名が変更になった場合は、市区町村の障害福祉担当窓口で手続きを行います。この手続きには、氏名の変更を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票など)と現在の手帳が必要です。自治体によっては、新しい写真の提出を求められる場合もあります。
手帳を紛失した場合は、すぐに再交付の手続きを行いましょう。市区町村の障害福祉担当窓口で再交付申請書を提出します。再交付には、申請書、写真、本人確認書類、印鑑などが必要です。手帳を紛失した場合は、悪用を防ぐためにも早めに手続きを行うことが重要です。再交付には数週間かかる場合があるため、その間は福祉サービスの利用に支障が出る可能性があります。医療機関などで手帳の提示を求められた場合は、再交付手続き中である旨を説明しましょう。
障害年金を受給していない場合でも手帳は取得できるのかという質問もあります。障害年金の受給は手帳取得の必須条件ではありません。診断書を提出することで、障害年金を受給していなくても手帳を取得することができます。逆に、障害年金を受給していても、必ずしも手帳が交付されるとは限りません。手帳と障害年金は別々の制度であり、判定基準も異なります。障害年金は主に就労能力や日常生活能力の制限を基準とするのに対し、手帳は精神障害の程度を総合的に評価します。
働いている場合でも手帳は取得できるのかという質問もよくあります。就労していることは手帳取得の妨げにはなりません。働きながらでも、精神障害により日常生活や社会生活に制限がある場合は、手帳を取得することができます。むしろ、障害者雇用で働く場合には手帳が必要となることが多いです。一般雇用で働いている方でも、職場での配慮を得るために手帳を取得することがあります。就労状況は診断書に記載されますが、就労しているからといって手帳が取得できないわけではありません。
手帳を返納することはできるのかという質問もあります。障害が回復し、手帳が不要になった場合は、自主的に手帳を返納することができます。市区町村の障害福祉担当窓口に手帳を持参し、返納の手続きを行います。返納すると、その時点で手帳を使った福祉サービスは利用できなくなります。ただし、症状が再発する可能性がある場合は、すぐに返納せず、次回の更新時まで持っておくことも選択肢の一つです。
まとめ
障害者手帳の更新手続きは、手帳の種類によって大きく異なります。身体障害者手帳は原則更新不要ですが、一部のケースでは再認定が必要です。療育手帳は年齢に応じて2年から10年ごとの再判定が求められます。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必須であり、最も頻繁な手続きが必要となります。
特に精神障害者保健福祉手帳は定期的な更新が求められるため、計画的な手続きが極めて重要です。有効期限の3か月前から更新手続きを開始でき、審査には約2か月かかるため、早めの申請が強く推奨されます。更新を忘れると、医療費助成、各種手当、税金の減免、公共料金の割引などの福祉サービスが利用できなくなり、日常生活に大きな影響が出てしまいます。
更新に必要な書類は、申請書、診断書または年金関連書類、写真、本人確認書類、マイナンバー関連書類、現在の手帳などです。診断書は作成日から3か月以内のものでなければならず、作成には時間と費用がかかるため、余裕を持って準備することが大切です。診断書作成時には、日常生活での具体的な困難さを医師に詳しく伝えることで、より適切な診断書を作成してもらうことができます。
手帳が失効すると、医療費助成、各種手当、税金の減免、公共交通機関の運賃割引、公共施設の利用料金減免、携帯電話料金の割引、NHK受信料の減免など、多くの福祉サービスが利用できなくなります。更新を忘れないよう、有効期限をカレンダーやスマートフォンのリマインダーに登録しておくことをお勧めします。3か月前と1か月前に通知が来るように設定しておけば、確実に更新手続きを行うことができます。
手続きの詳細は自治体によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認することが確実です。申請方法(窓口、郵送、電子申請)、手帳の形式(紙形式、カード形式)、診断書の様式などが自治体によって異なることがあります。不明な点があれば、遠慮なく窓口に相談しましょう。担当者が丁寧に説明してくれます。
障害者手帳は、障害のある方が自立した生活を送り、社会参加を促進するための重要なツールです。適切に更新手続きを行い、必要な支援を受けながら、充実した生活を送りましょう。手帳を活用することで、経済的な負担を軽減し、より良い医療を受け、社会参加の機会を広げることができます。更新手続きは面倒に感じられるかもしれませんが、福祉サービスを継続して利用するために不可欠なプロセスです。計画的に余裕を持って手続きを進めることで、安心して日常生活を送ることができます。


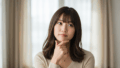
コメント