障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が生じた方が利用できる重要な社会保障制度です。多くの方が「働きながらでも障害年金を受給できるのか」「所得制限があるのか」という疑問を抱えています。実際に厚生労働省の統計では、障害年金受給者の約半数が何らかの形で就労を続けており、働きながら受給することは決して珍しいケースではありません。障害年金の受給と就労は両立可能であり、適切な理解と手続きを行うことで、多くの方が安定した生活を維持できています。2025年現在の最新情報に基づいて、働きながら障害年金を受給するための条件、所得制限の詳細、注意すべきポイントについて詳しく解説いたします。

障害年金の基本的な受給要件
障害年金を受給するためには、3つの基本要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は障害年金制度の根幹をなすものであり、就労状況に関わらず全ての申請者に適用されます。
まず初診日要件について説明します。初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日のことです。この初診日において、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入していることが必要です。特に重要なのは、初診日時点の加入制度によって受給できる年金の種類が決まることです。国民年金加入者は障害基礎年金、厚生年金加入者は障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できる可能性があります。ただし、病気や怪我の初診日が65歳の誕生日以降の場合は、原則として申請することができません。
次に保険料納付要件です。この要件には原則と特例の2つのパターンがあります。原則として、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていることが必要です。特例として、初診日が平成38年4月1日以前の場合は、初診日が属する月の前々月までの過去1年間に保険料の滞納月がないことで要件を満たすことができます。重要な注意点として、初診日に慌てて1年遡って保険料を納めても、初診日の前日時点での納付状況で判断されるため意味がありません。
最後に障害状態該当要件があります。障害認定日において、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当する障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは、初診日から1年半経過した日、またはその期間内にその傷病が治った日を指します。この日における障害の程度が、法律で定められた基準を満たしているかどうかが審査されます。
所得制限の詳細な仕組み
障害年金における所得制限は、多くの方が混乱しやすい部分ですが、基本的な原則を理解すれば明確になります。通常の障害年金には所得制限はありません。つまり、障害基礎年金や障害厚生年金を受給しながら働いて高い収入を得ても、年金の支給が停止されることはありません。この点が老齢年金や遺族年金とは大きく異なる特徴です。
ただし、2つの例外的なケースでは所得制限が適用されます。最も重要なのが20歳前傷病による障害基礎年金です。20歳前の病気やケガで障害年金を受給している場合、所得による支給制限が発生します。これは、20歳前障害が原因の受給者は国民年金の保険料を納めていない、あるいは保険料納付要件を満たしていないにもかかわらず給付を受けているためです。
2025年の所得制限額は、単身者の場合472万1,000円となっています。扶養親族がいる場合は、扶養親族数1人につき380,000円が加算されます。例えば、配偶者と子ども1人の扶養親族がいる場合、472万1,000円+380,000円×2人=549万7,000円が所得制限額となります。
前年所得に基づく給付対象期間は10月分から翌年9月分となり、所得制限にかかると該当期間の障害年金の受給額が2分の1に減額、または全額停止されます。所得が398万4,000円を超えて472万1,000円以下の場合は2分の1支給停止、472万1,000円を超える場合は全額支給停止となります。
もう一つの例外が特別障害給付金です。この制度は、国民年金の任意加入対象であった学生や厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者が、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害状態にある方に支給される制度です。特別障害給付金にも所得制限が適用され、年収360万4,000円を超える場合は支給停止となります。
就労状況と障害年金の関係性
令和5年の社会保障審議会年金部会の資料によると、2019年では障害年金を受給されている方の中で、身体障害48.0%、知的障害58.6%、精神障害34.8%の方が就労しながら障害年金を受給されています。この統計からも分かるように、働きながらの障害年金受給は決して例外的なケースではありません。
障害年金の等級と就労の関係について詳しく見ていきましょう。1級は日常生活に常時介護を要する程度の障害状態とされ、就労は極めて困難な状況です。2級は身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとされています。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度とされています。
しかし、実際には2級受給者でも適切な配慮や支援があれば就労可能な場合があります。3級は労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のものとされ、フルタイムの労働に耐えられない、または軽労働以外はできない状態です。日常生活については、家族など他人のサポートは不要とされています。
重要なのは、等級の判定は就労の有無だけで決まるものではないということです。就労していても、職場での特別な配慮や周囲のサポートが必要な状況であれば、それは障害による制限があることの証明となります。例えば、勤務時間の短縮、業務内容の調整、定期的な休憩の確保、騒音の少ない環境での作業などの配慮を受けている場合、これらは全て障害年金の継続受給において重要な要素となります。
更新時における就労状況の影響と対策
障害年金は多くの場合、有期認定となっており、定期的な更新が必要です。更新の頻度は障害の状態により1年から5年の間で設定され、まれに永久認定となる場合もあります。更新時には現在の障害状態が審査され、この際に就労状況が影響する場合があります。
近年、障害年金の更新時に「就労の開始」を理由として等級が下がったり、年金が停止となったという相談が増加しており、就労が審査に及ぼす影響は年々増していると感じられています。しかし、これは就労したから必ず等級が下がるということではありません。
更新審査では、就労状況、生活状況(家事などがどのくらいできるか)、家族の状況(独り暮らしかどうかなど)など、いろいろな角度から総合的に審査されます。就労の事実よりも、どのような配慮や支援を受けて就労しているかが重要です。
就労している場合の更新対策として、以下の点が重要です。まず、会社から受けている特別な配慮について具体的に記録することです。勤務時間の短縮、業務内容の調整、定期的な面談やカウンセリング、通院のための休暇取得の配慮、作業環境の特別な配慮などを詳細に記録し、診断書や病歴・就労状況等申立書に反映させる必要があります。
また、日常生活での困りごとや制限についても継続的に記録することが大切です。通勤時の困難さ、集中力の持続時間、対人関係での困難、疲労の蓄積具合、症状の変動など、働いていても残存する障害の影響を具体的に示すことが重要です。
精神疾患における特別な考慮事項
精神障害を持つ方の場合、就労状況が等級判定により強く影響する可能性があります。身体障害や内部障害の場合、客観的な医学的所見が重視されるため、就労の有無がそれほど大きな影響を与えないことが多いです。しかし、うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害などの精神関連の障害では、就労状況が等級判定に大きく影響する可能性があります。
平成28年9月より運用されている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、診断書の「日常生活能力の程度」の評価(5段階評価)及び「日常生活能力の判定」の評価(4段階評価)の平均を組み合わせて等級の目安が設定されています。この中で就労状況についても詳細な評価が行われます。
精神障害で就労している場合の重要なポイントは、働けることと障害がないことは別問題であることを明確に示すことです。例えば、継続的な服薬が必要、定期的な通院が欠かせない、ストレス耐性が低い、対人関係に困難がある、集中力が続かない、疲労しやすい、症状の波があるなど、働いていても残存する障害の影響を具体的に記載することが重要です。
また、職場での配慮についても詳細に記録する必要があります。時差出勤や短時間勤務、業務量の調整、ストレスの少ない部署への配置、定期的な面談、通院のための休暇の確保、騒音の少ない環境の提供、作業手順の簡素化、上司や同僚からの特別なサポートなど、これらの配慮がなければ就労継続が困難であることを明確に示すことが大切です。
診断書と申立書の重要性
働きながら障害年金を受給するためには、適切な書類の準備が極めて重要です。特に診断書と病歴・就労状況等申立書は、審査において中核となる書類です。
診断書は障害年金申請の最重要書類であり、医師は現在の障害状態を客観的に記載する必要があります。就労している場合は、「職場内外を問わず就労を継続するために受けている援助や配慮」について詳細に記載してもらうことが重要です。受診日より前1年以内に病気休職や休業期間があった場合は、「職場における援助や配慮の状況」の欄に開始年月日と終了年月日、復職後の状況を記載していきます。
診断書の記載において特に重要なのは、働けることと障害がないことは別問題であることを医師に理解してもらうことです。就労していても、継続的な治療が必要、症状の変動がある、特別な配慮が必要、日常生活に制限があるなど、障害による影響が継続していることを医学的根拠に基づいて記載してもらう必要があります。
病歴・就労状況等申立書は、診断書の補足資料として機能し、治療の経過や日常生活、就労状況について申請者の視点から詳しく記載します。この書類では、診断書だけでは伝わらない、障害が日常生活にどのように影響しているかを具体的に説明することができます。
特に就労している場合は、以下の点を詳しく記載することが重要です。会社から受けている特別な配慮として、勤務時間の短縮、作業内容の調整、定期的な面談、通院のための特別休暇、作業環境の配慮などを具体的に記載します。周囲からのサポート内容として、上司や同僚からの業務上のサポート、家族からの日常生活でのサポート、医療機関や福祉サービスからの支援などを詳述します。
日常生活での困りごとや不便なことについても具体的に記載します。疲労の蓄積、集中力の持続困難、対人関係での困難、家事や身の回りのことでの困難、外出時の困難などを詳しく説明します。通院や治療の頻度、服薬の状況、症状の変動、病気による仕事への影響なども重要な情報です。
職場での配慮と支援の具体例
働きながら障害年金を受給している方が受けている職場での配慮や支援には、障害の種類に応じて様々な例があります。これらの配慮を受けていることは、障害年金の継続受給において重要な要素となります。
身体障害の場合の配慮例として、車いす対応の職場環境整備、エレベーターの優先利用、専用駐車場の確保、重量物の取り扱い免除、階段昇降の回避、作業台の高さ調整、福祉機器の貸与、移動時間の配慮、休憩場所の確保、作業補助具の提供などがあります。
精神障害の場合は、勤務時間の短縮または時差出勤、業務量の調整、定期的な面談やカウンセリング、ストレスの少ない業務への配置転換、通院のための休暇取得の配慮、騒音の少ない職場環境の提供、集中できる個別スペースの確保、業務指示の文書化、緊急時の休憩許可、症状悪化時の早退許可などの配慮が行われています。
知的障害の場合は、業務内容の単純化、作業手順の視覚化、反復練習の時間確保、専任指導者の配置、ゆっくりとした説明、業務の細分化、成果の評価方法の調整、コミュニケーション方法の工夫、安全確保のための見守り、休憩時間の調整などの配慮が必要です。
視覚障害の場合は、音声読み上げソフトの導入、点字資料の提供、拡大文字での資料作成、照明の調整、移動経路の確保、ガイドヘルプの提供、危険箇所の音声案内、触覚で確認できる目印の設置、画面読み上げ機能の活用、資料の電子化などの配慮が行われています。
聴覚障害の場合は、手話通訳者の配置、筆談での情報伝達、資料の文字化、会議での要約筆記、光による連絡手段、振動アラームの設置、唇読みしやすい環境の確保、視覚的な情報提供、緊急時の連絡方法の確立、コミュニケーション機器の提供などの配慮が必要です。
これらの配慮を受けていることは、障害による制限が存在することの証明となります。診断書や申立書には、これらの配慮の具体的な内容、配慮がなければ就労継続が困難であること、配慮を受けていても完全に健常者と同等の業務遂行は困難であることなどを詳細に記載することが重要です。
2025年度の受給額と家族加算
令和7年度(2025年度)の障害年金の受給額について詳しく説明します。適切な受給額の理解は、生活設計において重要な要素です。
障害基礎年金の受給額は、1級が年額1,039,625円、2級が年額831,700円となっています。これは月額に換算すると、1級が約86,635円、2級が約69,308円です。18歳になった後の最初の3月31日までの子がいる場合は、子の加算があります。第1子・第2子は各228,700円、第3子以降は各76,200円が加算されます。
障害厚生年金の受給額は、加入期間中の給与などに基づいて計算される報酬比例年金額によって決まります。1級は報酬比例年金額の1.25倍、2級は報酬比例年金額と同額、3級は報酬比例年金額となります。ただし、3級には最低保障額が設定されており、2025年度は622,750円となっています。
配偶者加算についても重要な制度です。障害厚生年金の1級または2級受給者で、生計を維持している配偶者がいる場合、配偶者加算額224,700円が支給されます。配偶者の年収が850万円未満(所得655万5千円未満)であることが条件となります。
働きながら受給している場合、これらの年金額と勤労収入を合わせた総収入で生活設計を立てることができます。ただし、前述の所得制限に該当する場合は注意が必要です。また、税制上、障害年金は非課税所得のため、所得税・住民税ともに課税されません。
手続きの流れと必要書類
障害年金の申請手続きは以下の6つのステップで進めることができます。適切な手続きを行うことで、スムーズな受給開始が可能になります。
まず年金事務所での相談予約を行います。多くの年金事務所が予約制を採用しているため、電話で予約を入れる必要があります。混雑している場合は、予約できる時期が3週間程度先になることもあります。相談時には、病気やケガの詳細、初診日、現在の症状、就労状況などについて詳しく聞かれます。
次に保険料納付要件の確認を行います。初診日の前日の時点で保険料を納めていたか「保険料納付要件」を確認します。これは年金事務所や街角の年金相談センター、市町村役場の国民年金課で調べてもらうことができます。保険料納付要件を満たしていない場合は、残念ながら障害年金の受給はできません。
必要書類の準備では、基本的な必要書類として年金請求書、診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書があります。診断書は障害の部位別に8種類あり、該当する診断書を医師に作成してもらいます。病歴・就労状況等申立書は申請者自身が記載する書類で、発病から現在までの経過を詳細に記載します。
書類の提出先は初診日の加入制度により異なります。国民年金加入中、20歳前、60歳以上65歳未満の場合は住所地の市区町村の国民年金課に提出します。厚生年金加入中、国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
審査は書類のみで行われ、要介護認定の審査のように調査員が訪問することはありません。審査期間は通常3~4か月程度ですが、書類に不備がある場合や追加資料が必要な場合はさらに時間がかかることがあります。
最後に結果通知が行われます。支給決定の場合は年金証書が送付され、年金の受給が開始されます。不支給の場合は不支給決定通知書が送付され、不服申立ての手続きを検討することができます。
不支給決定への対策と再申請
申請が不支給となった場合でも、諦める必要はありません。適切な対策を講じることで、受給の可能性を高めることができます。
不支給の主な原因として、障害程度が軽いと判断される場合、初診日が証明できない場合、申請書類の不備や必要書類の不足、保険料納付要件を満たしていない場合などがあります。これらの原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。
対策方法として、まず審査請求(不服申立て)があります。処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行うことができます。審査請求の成功率は約10%程度と低めですが、新たな医学的証拠や生活状況の詳細な説明により覆る可能性があります。審査請求が認められなかった場合は、さらに再審査請求を行うことができますが、成功率は約2%程度とさらに低くなります。
再申請という方法もあります。不服申し立てではなく、初めから書類を揃え直して再申請する方法です。前回提出した書類も必ずチェックされるため、問題点を改善した上で再提出することが重要です。診断書の記載内容の充実、病歴・就労状況等申立書の詳細な記載、新たな医学的証拠の追加などにより、再申請で認定される場合があります。
状態悪化による新たな請求として、請求後に病状が悪化したときは「額改定請求」をすることができます。これは障害認定日から1年を経過した日以降に行うことができ、現在の障害状態が以前より悪化している場合に有効です。
社会保険労務士への依頼について
障害年金の申請は複雑な手続きのため、社会保険労務士(社労士)に依頼することも検討できます。専門家への依頼により、適切な書類作成や手続きのサポートを受けることができます。
社労士への依頼にかかる費用は、着手金が1~3万円(無料の事務所もあり)、成功報酬が年金支給額の2~3ヶ月分または遡及金額の10~15%程度、事務手数料・実費が10,000~30,000円となっています。
相談料については、初回相談は無料としている事務所も多く、有料の場合は1時間あたり5,000円から10,000円程度です。料金体系には成功報酬制と固定報酬制があり、成功報酬制では障害年金の受給が決定した後に報酬を支払い、不支給の場合は報酬不要となります。固定報酬制では結果に関わらず一定の報酬を支払います。
注意点として、社労士の成功報酬は受給額の20~30%を要求される場合があり、月8万円で2年間の受給なら約60万円近い報酬となる可能性があります。依頼前に料金体系を明確に確認し、複数の事務所を比較検討することが重要です。
社労士に依頼するメリットとして、専門知識に基づく適切な書類作成、審査のポイントを押さえた申請、医師との連携による診断書の充実、不支給時の対応サポート、更新時の継続的なサポートなどがあります。一方で、費用がかかること、依頼者自身が制度を理解する機会が減ること、社労士の技量によって結果に差が生じることなどのデメリットもあります。
よくある質問と具体的な回答
Q:パートタイムで働いていても障害年金は受給できますか?
A:はい、十分に可能です。就労形態(正社員、パート、アルバイト等)よりも、職場での配慮の内容や日常生活の状況が総合的に判断されます。パートタイムであっても、勤務時間の短縮が障害による制限のためであり、適切な配慮を受けて働いていることを示すことが重要です。
Q:障害年金受給中に転職した場合の手続きは?
A:転職自体で特別な手続きは不要ですが、更新時に新しい職場での状況を正確に伝えることが重要です。新しい職場でも継続的な配慮が必要であること、転職により業務内容や労働条件が障害に配慮したものになっていることなどを診断書や申立書に記載してもらいましょう。
Q:精神障害で働いている場合、等級が下がりやすいですか?
A:働いていることだけでは等級は決まりません。重要なのは、職場での配慮や支援の状況、日常生活での困難さを具体的に示すことです。継続的な治療の必要性、服薬の状況、症状の変動、ストレス耐性の低さ、対人関係の困難さなど、働いていても残存する障害の影響を詳細に記載することが大切です。
Q:障害年金受給者は健康保険の扶養に入れますか?
A:障害年金を含む年間収入が180万円未満であれば扶養に入ることができます。ただし、健康保険組合によって基準が異なる場合があるため、加入予定の健康保険組合に事前に確認することをお勧めします。
Q:更新の頻度はどのくらいですか?
A:障害の状態により1年から5年の有期認定が多く、症状が安定しており改善の見込みが少ない場合は永久認定となることもあります。精神障害の場合は比較的短期間での更新となることが多く、身体障害や内部障害の場合は比較的長期間の認定となる傾向があります。
支援制度との併用と生活の安定化
障害年金と併用できる支援制度を活用することで、より安定した生活を送ることができます。これらの制度を組み合わせることで、経済面だけでなく、医療、就労、日常生活全般にわたる支援を受けることができます。
自立支援医療制度では、精神通院医療、更生医療、育成医療の医療費が1割負担になります。障害年金受給と併用可能で、継続的な治療が必要な方には大きな経済的メリットがあります。
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を取得することで、各種減免制度やサービスを利用できます。公共交通機関の割引、税金の減免、公共施設の利用料減免、携帯電話料金の割引など、日常生活での経済的負担を軽減できます。
就労支援としては、障害者就労移行支援事業、障害者就労継続支援事業(A型・B型)、ジョブコーチ支援などがあります。これらのサービスを利用することで、自分の障害特性に合った働き方を見つけ、安定した就労を継続することができます。
生活保護については、障害年金受給者でも要件を満たせば受給が可能です。障害年金は収入として認定されますが、最低生活費を下回る場合は差額が支給されます。特に20歳前傷病による障害基礎年金で所得制限により支給停止となった場合などに重要な制度となります。
今後の制度動向と対策
2025年以降の障害年金制度は40年ぶりの大幅な見直しが検討されており、受給者の生活に大きな影響を与える可能性があります。
主な検討事項として、直近1年要件の特例措置延長があります。現在令和8年4月1日までとされている特例措置の延長が検討されており、これにより保険料納付要件の緩和が継続される可能性があります。
精神障害の認定基準の見直しも重要な課題です。就労状況の評価方法の見直し、社会復帰支援との連携強化、地域格差の更なる是正などが検討されています。
デジタル化の推進により、オンライン申請の拡充、AI活用による審査の効率化、電子診断書の導入などが進められる予定です。これにより手続きの簡素化や迅速化が期待されています。
国際基準への対応として、ICF(国際生活機能分類)に基づく評価方法の導入、WHO基準との整合性確保、国際的な障害者権利条約への対応などが検討されています。
これらの変更に対応するため、定期的に最新情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。制度の変更により受給要件や手続きが変わる可能性があるため、常に最新の情報を把握しておくことが大切です。


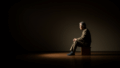
コメント