日本の税制には、障害のある方やそのご家族の経済的負担を軽減するためのさまざまな仕組みが用意されています。その中でも特に重要なのが障害者控除という制度です。この控除制度を活用することで、所得税や住民税の負担を大幅に減らすことができますが、実は多くの方がこの制度の存在を知らなかったり、手続き方法がわからなかったりして、本来受けられるはずの控除を受け損ねているケースが少なくありません。障害者控除は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの方だけでなく、65歳以上で要介護認定を受けている方も対象となる可能性があります。年末調整や確定申告の際に適切に申請することで、一般の障害者で27万円、特別障害者で40万円、同居特別障害者の場合は最大75万円もの所得控除を受けることができます。この記事では、障害者控除の申請方法から必要書類、具体的な手続きの流れまで、わかりやすく詳しく解説していきます。
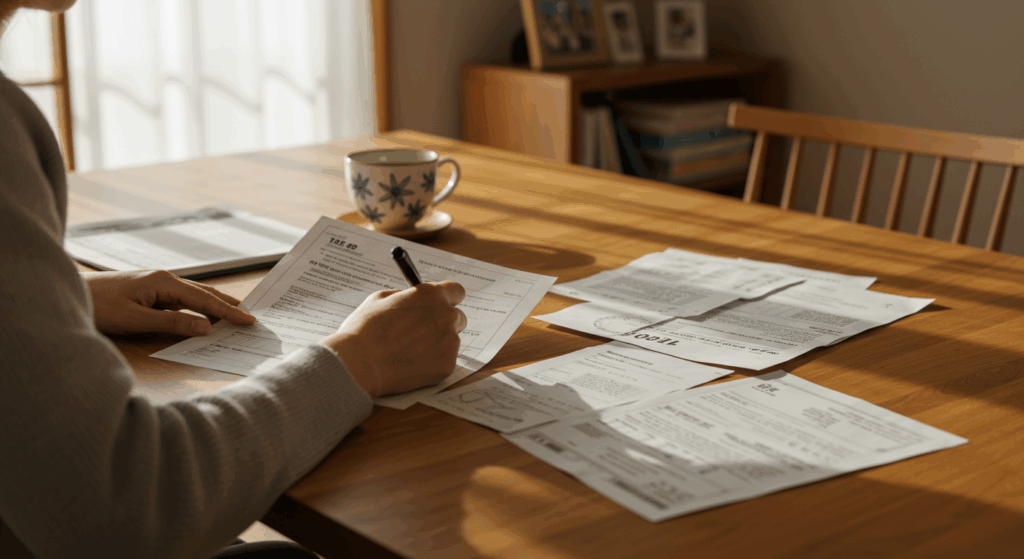
障害者控除の基本的な仕組みと対象者
障害者控除は、所得税法に基づいて設けられている所得控除の一つです。納税者本人が障害者である場合はもちろん、同一生計配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも適用されます。この制度の重要なポイントは、条件を満たしていても自動的には適用されないという点です。年末調整または確定申告の際に、必ず自分で申請する必要があります。
対象となるのは、身体障害者手帳の交付を受けている方です。身体障害者手帳には1級から6級までの等級があり、障害の程度によって控除額が変わってきます。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方も対象となります。精神障害の程度に応じて1級から3級までの等級が設定されており、等級によって一般の障害者か特別障害者かが区分されます。
療育手帳(地域によっては愛の手帳と呼ばれます)の交付を受けている方も障害者控除の対象です。知的障害の程度により等級が分かれており、重度の場合は特別障害者として扱われます。戦傷病者手帳の交付を受けている方も対象となります。戦傷病の程度により特別項症から第6項症までの等級があり、等級によって控除額が異なります。
特に注目すべきなのが、65歳以上で要介護認定を受けている方です。身体障害者手帳などを持っていなくても、市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、障害者控除を受けられる場合があります。これは介護保険法に基づく要介護認定において、障害者に準ずる状態であると認定された場合に適用される制度です。多くの自治体では、要介護1から要介護2の方は一般の障害者に、要介護3以上の方は特別障害者に該当する可能性が高くなります。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方や、常に就床を要し複雑な介護を要する状態にある方も障害者控除の対象となることがあります。
控除金額の詳細と税負担軽減効果
障害者控除で控除される金額は、障害の程度によって明確に区分されています。2025年現在も以下の金額が適用されています。
一般の障害者の場合、所得税における控除額は27万円、住民税では26万円の控除となります。身体障害者手帳の3級から6級、精神障害者保健福祉手帳の2級または3級、療育手帳の軽度から中度の方などが該当します。この27万円という控除額は、課税所得から差し引かれるため、実際の税負担軽減額は所得税率によって変わります。例えば所得税率が10パーセントの方であれば、約2万7千円の所得税が軽減されることになります。
特別障害者の場合は、所得税で40万円、住民税で30万円の控除を受けることができます。身体障害者手帳の1級または2級、精神障害者保健福祉手帳の1級、療育手帳の重度の方などが特別障害者に該当します。また、常に就床を要し複雑な介護を要する状態にある方も特別障害者とみなされます。所得税率が20パーセントの方であれば、8万円の所得税軽減効果があります。
同居特別障害者の場合は、さらに控除額が大きくなり、所得税で75万円、住民税で53万円の控除を受けることができます。同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている方を指します。この75万円という大きな控除額は、介護が必要な家族と同居している世帯の経済的負担を大きく軽減する効果があります。
重要なのは、これらの控除は所得税だけでなく住民税にも適用されるという点です。確定申告または年末調整で一度申告すれば、住民税の計算にも自動的に反映されますので、別途申告する必要はありません。
必要書類の準備方法
障害者控除を申請するために必要な書類は、申請する方法や状況によって異なります。
基本的な証明書類となるのは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、戦傷病者手帳などの障害者手帳です。これらの手帳を所持していることが障害者であることの証明となります。実は、税務署や勤務先への提出時に手帳のコピーの提出は必須ではありませんが、確認を求められることがあるため、コピーを準備しておくと安心です。
会社員の方が年末調整で障害者控除を受ける場合は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に必要事項を記入して勤務先に提出します。この申告書には、障害者の氏名、続柄、障害者の種類(一般、特別、同居特別)などを記入する欄が設けられています。通常、この申告書は毎年11月から12月にかけて勤務先から配布されますが、新しく雇用された場合は入社時に提出することもあります。
個人事業主の方や、会社員でも年末調整で申告しなかった方が確定申告で障害者控除を受ける場合は、確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の欄にある障害者控除の欄に必要事項を記入します。確定申告書は税務署で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることも、e-Taxを利用してオンラインで作成することも可能です。
65歳以上の方で要介護認定を受けている場合は、市区町村の窓口に障害者控除対象者認定書の交付を申請する必要があります。この申請には、要介護認定結果通知書のコピーや本人確認書類などが必要となります。多くの場合、既に介護保険の認定調査で取得している情報を活用するため、新たに医師の診断書を取得する必要はありませんが、自治体によって必要書類が異なりますので、事前に窓口で確認することをお勧めします。申請から交付までには通常2週間から1か月程度かかりますので、年末調整や確定申告の時期を考慮して早めに手続きを行うことが重要です。
身体障害者手帳などの交付を申請中である場合でも、交付を受けるための医師の診断書を有していることにより、障害者控除の適用を受けることができる場合があります。この場合、医師の診断書のコピーなどを添付することが必要になります。詳細については税務署に相談することをお勧めします。
会社員の年末調整での申請手続き
会社員の方は、年末調整で障害者控除を申請するのが最も簡便な方法です。手続きの流れを詳しく見ていきましょう。
まず、勤務先から配布される給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を受け取ります。この申告書は、通常、年末調整の時期である11月から12月にかけて配布されますが、会社によっては前年の年末に翌年分を配布することもあります。申告書を受け取ったら、必要事項を正確に記入していきます。
申告書の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄に必要事項を記入します。納税者本人が障害者の場合は、「本人」の欄にチェックを入れます。同一生計配偶者や扶養親族が障害者の場合は、該当する人の氏名、続柄を記入し、障害者の種類を選択します。一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者のうち、該当するものにチェックまたは丸印をつけます。
身体障害者手帳などの手帳番号を記入する欄がある場合は、手帳番号も記入します。手帳番号は手帳に記載されていますので、正確に転記してください。また、障害の等級を記入する欄がある場合もありますので、該当する等級を記入します。
記入が完了した申告書を、指定された期日までに勤務先の人事部門や経理部門に提出します。期日を過ぎると年末調整に間に合わない可能性がありますので、余裕を持って提出することが大切です。
勤務先が年末調整の計算を行い、障害者控除が適用された結果、源泉徴収票が発行されます。源泉徴収票を受け取ったら、「所得控除の額の合計額」の欄に障害者控除が含まれていることを確認しましょう。また、「障害者の数」の欄に該当する人数が記載されているかも確認してください。
もし年末調整で障害者控除の申告を忘れた場合でも、翌年の確定申告期間中に自分で確定申告を行うことで、控除を受けることができます。年末調整後に障害者手帳を取得した場合なども、確定申告で追加の控除を申請できます。
個人事業主と確定申告での申請手続き
個人事業主の方や、会社員でも年末調整で申告しなかった方は、確定申告で障害者控除を申請します。確定申告の手続きについて詳しく説明します。
まず、確定申告書を準備します。確定申告書は、最寄りの税務署で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。また、e-Taxを利用してオンラインで作成・提出することも可能です。e-Taxを利用すると、24時間いつでも申告ができ、還付金の受け取りも早くなるというメリットがあります。
確定申告書の第一表の「所得から差し引かれる金額」の欄にある「障害者控除」の欄に、該当する控除額を記入します。一般の障害者が1人いる場合は27万円、特別障害者が1人いる場合は40万円、同居特別障害者が1人いる場合は75万円と記入します。複数人が該当する場合は、それぞれの控除額を合計した金額を記入します。例えば、本人が一般の障害者で配偶者が特別障害者の場合は、27万円と40万円を合計した67万円を記入します。
確定申告書の第二表の「障害者控除」の欄に、障害者の氏名、続柄、障害者の種類などの詳細を記入します。本人が障害者の場合は、「本人に関する事項」の欄の「障害者」または「特別障害者」の該当する方に丸印をつけます。配偶者や扶養親族が障害者の場合は、「配偶者や親族に関する事項」の欄に、対象者の氏名、続柄を記入し、「障」(一般の障害者)、「特障」(特別障害者)、「同居特障」(同居特別障害者)のうち、該当するものに丸印をつけます。
必要に応じて、身体障害者手帳などのコピーを添付書類として準備します。ただし、確定申告書への添付は必須ではなく、提出後に税務署から確認を求められた場合に提示できるように保管しておけば十分です。
確定申告期間中(通常2月16日から3月15日まで)に、税務署に確定申告書を提出します。税務署の窓口に直接持参する方法、郵送での提出、e-Taxによる電子申告のいずれかの方法で提出できます。e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダライタ、またはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。
e-Taxで申告する場合の流れは次のようになります。国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、確定申告書の作成を開始します。所得控除の入力画面で「障害者控除」の項目を選択し、障害者控除の対象者(本人、配偶者、扶養親族)を選択します。障害の種類(一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者)を選択すると、自動的に控除額が計算されます。複数の対象者がいる場合は、それぞれについて入力を繰り返します。
確定申告の結果、還付金がある場合は、指定した口座に振り込まれます。通常、申告から1か月から1か月半程度で振り込まれますが、e-Taxで申告した場合はさらに早く、3週間程度で振り込まれることもあります。還付金の振込先口座は本人名義の口座に限られますので、申告書に記入する際は金融機関名、支店名、口座番号を正確に記入してください。
障害者控除対象者認定書の申請手続き
65歳以上で要介護認定を受けている方が、身体障害者手帳などを持っていない場合、市区町村から障害者控除対象者認定書の交付を受けることで障害者控除を受けられる可能性があります。この認定書は、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方が、市区町村の認定基準により障害者または特別障害者に準ずる状態であると認められた場合に交付される証明書です。
まず、お住まいの市区町村の福祉課や介護保険課などの窓口に、障害者控除対象者認定書の交付申請について相談します。自治体によって窓口が異なる場合がありますので、事前に代表電話に問い合わせて担当部署を確認することをお勧めします。多くの自治体では、ウェブサイトに認定書についての情報が掲載されており、申請書のダウンロードもできます。
窓口で申請について相談し、必要な書類や手続きについて説明を受けます。この際、認定の基準や審査にかかる期間なども確認しておくとよいでしょう。申請書を入手し、必要事項を記入します。申請書には、本人の氏名、住所、生年月日、要介護認定の状況などを記入します。記入方法がわからない場合は、窓口で相談することができます。
必要書類を準備します。要介護認定結果通知書のコピー、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)、場合によっては介護保険被保険者証のコピーが必要となります。申請は本人または親族からの申請が必要で、代理人が申請する場合は委任状が必要になることがあります。
申請書と必要書類を窓口に提出します。窓口申請のほか、郵送で申請を受け付けている自治体もあります。市区町村が、介護保険の認定調査結果や主治医の意見書などを基に審査を行います。審査では、日常生活の自立度、認知症の程度、身体の状態などが総合的に判断されます。
審査の結果、障害者または特別障害者に準ずる状態であると認められた場合、障害者控除対象者認定書が交付されます。認定書には、一般の障害者に該当するか、特別障害者に該当するかが記載されます。申請から交付までには、通常2週間から1か月程度かかります。認定書が交付されたら、年末調整や確定申告で障害者控除を申請する際に使用します。認定書のコピーを取って保管しておくとよいでしょう。
重要なポイントとして、介護保険法の要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象とはなりません。要介護認定と障害者控除認定は判断基準が異なるものであるため、要介護認定を受けた方が必ずしも障害者控除認定の対象になるとは限りませんが、申請して審査を受けることで認定される可能性があります。一般的には、要介護1または要介護2の方は一般の障害者に準ずるとして認定される可能性があり、要介護3以上の方は特別障害者に準ずるとして認定される可能性が高くなります。
障害者控除の申請を過去に忘れていた場合でも、最大5年前まで遡って障害者控除対象者認定書の申請ができます。例えば、2020年から要介護認定を受けていたが障害者控除の存在を知らなかったという場合、2025年中であれば2020年分から2024年分までの認定書の交付を申請することができます。過去の年度の認定書が交付されたら、税務署で更正の請求を行うことで、過去に納めすぎていた税金の還付を受けることができます。
申請時の重要な注意事項
障害者控除を申請する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解しておくことで、適切に控除を受けることができます。
最も重要なのは、障害者控除は条件を満たしていても自動的には適用されないという点です。必ず年末調整や確定申告で申請する必要があります。申請を忘れると控除を受けることができませんので、毎年忘れずに申請しましょう。特に、新たに障害者手帳を取得した場合や、要介護認定を受けた場合は、その年から申請できますので見逃さないようにしてください。
年末調整で申告を忘れた場合でも、翌年の確定申告期間中に自分で確定申告を行うことで、控除を受けることができます。また、過去5年分まで遡って申告することも可能です。過去に申請を忘れていたことに気づいた場合は、更正の請求を行うことで、過去に納めすぎていた税金の還付を受けることができます。
障害者控除は、その年の12月31日の現況で判定します。年の途中で障害者手帳を取得した場合でも、12月31日時点で手帳を持っていれば、その年分の控除を受けることができます。逆に、年の途中で亡くなられた場合は、亡くなられた時点での現況で判定されます。
扶養親族や同一生計配偶者が障害者の場合、その方の合計所得金額が48万円以下であることが条件となります。この条件を満たさない場合は、扶養親族としての障害者控除の対象となりませんので注意が必要です。ただし、納税者本人が障害者の場合は、所得金額に関係なく控除を受けることができます。
身体障害者手帳などの交付を申請中である場合でも、医師の診断書を有していることにより障害者控除の適用を受けることができる場合があります。具体的には、障害者手帳の交付を受けるための医師の診断書や各種手帳の申請書類の写しなどが該当します。詳しくは税務署にご相談ください。
同居特別障害者の控除を受けるためには、納税者本人、配偶者、生計を一にする親族のいずれかと「同居を常況としている」ことが必要です。同居を常況としているとは、日常的に生活を共にしていることを意味します。病院への長期入院などで一時的に別居している場合でも、退院後は同居する予定であれば同居を常況としていると認められる場合があります。しかし、老人ホームなどの施設に入所している場合は、通常、同居を常況としているとは認められません。
障害者控除は、所得税だけでなく住民税にも適用されます。確定申告または年末調整で申告すれば、住民税の計算にも自動的に反映されますので、別途申告する必要はありません。所得税で控除しきれなかった場合でも、住民税では控除されますので、必ず申告することが大切です。
障害者控除と他の制度との併用
障害者控除は、他の税制上の優遇措置や控除制度と併用できる場合があります。複数の控除を適切に組み合わせることで、より大きな節税効果が得られます。
医療費控除との併用は、障害のある方にとって特に重要です。障害のある方は医療費が高額になることが多いため、医療費控除の対象となる可能性が高くなります。医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円(または総所得金額等の5パーセントのいずれか少ない方)を超える場合に、その超えた金額を所得から控除できる制度です。障害者控除と医療費控除は併用できますので、両方の要件を満たす場合は、どちらも申請することでより大きな節税効果が得られます。医療費控除を申請する際は、医療費の領収書や明細書を保管しておく必要があります。
扶養控除との併用も可能です。扶養親族が障害者の場合、扶養控除と障害者控除の両方を受けることができます。扶養控除は、扶養親族の年齢や同居の有無により控除額が異なります。例えば、70歳以上の父親を扶養している場合、老人扶養親族として48万円の扶養控除を受けることができます。父親が特別障害者である場合は、さらに40万円の障害者控除が加算され、合計88万円の控除を受けることができます。父親が同居特別障害者であれば、扶養控除48万円と同居特別障害者控除75万円で、合計123万円もの控除となり、大きな節税効果があります。
配偶者控除・配偶者特別控除との併用も認められています。配偶者が障害者の場合、配偶者控除または配偶者特別控除と障害者控除を併用できます。配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除の対象となり、さらに障害者控除も適用されます。配偶者が一般の障害者の場合は、配偶者控除38万円に加えて障害者控除27万円が適用され、合計65万円の控除となります。配偶者が特別障害者の場合は、合計78万円の控除となります。
住宅ローン控除との関係については理解が必要です。住宅ローン控除は税額控除であり、障害者控除は所得控除です。両者は控除の種類が異なるため、併用が可能です。ただし、住宅ローン控除により所得税額が既にゼロになっている場合、障害者控除を申請しても所得税の還付は発生しません。しかし、住民税の計算には障害者控除が適用されますので、住民税の負担は軽減されます。したがって、住宅ローン控除で所得税がゼロになる場合でも、障害者控除を申告する意味はあります。
自治体独自の支援制度も確認することをお勧めします。障害者控除以外にも、各自治体が独自に障害のある方への支援制度を設けている場合があります。例えば、福祉手当や医療費助成、公共料金の減免、交通費の助成などがあります。これらの制度は障害者控除とは別の制度ですので、併用することができます。お住まいの自治体の窓口に問い合わせて、利用できる制度がないか確認することをお勧めします。
各種証明書の取得方法
障害者控除を受けるためには、障害の状態を証明する書類が必要です。ここでは、各種証明書の取得方法について詳しく説明します。
身体障害者手帳の取得方法は次の通りです。まず、お住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口に相談します。申請に必要な書類や手続きについて説明を受けます。指定医師の診断を受ける必要があります。身体障害者手帳の申請には、都道府県知事が指定する医師(指定医)の診断書が必要です。診断書の様式は市区町村の窓口で入手できます。診断書を医師に作成してもらいます。診断書の作成には費用がかかる場合があります。申請書、診断書、顔写真、マイナンバーがわかるものなどを揃えて、市区町村の窓口に申請します。都道府県で審査が行われ、身体障害者手帳が交付されます。申請から交付までには、通常1か月から2か月程度かかります。身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの等級があります。等級により受けられるサービスや控除の内容が異なります。
精神障害者保健福祉手帳の取得方法は次の通りです。お住まいの市区町村の障害福祉課や保健所などの窓口に相談します。医師の診断書または精神障害による障害年金の年金証書のコピーを準備します。診断書は、精神疾患の初診日から6か月以上経過している必要があります。申請書、診断書または年金証書のコピー、顔写真、マイナンバーがわかるものなどを揃えて、市区町村の窓口に申請します。都道府県で審査が行われ、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。申請から交付までには、通常1か月から3か月程度かかります。精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度により1級から3級までの等級があります。手帳の有効期限は2年間で、更新が必要です。
療育手帳(愛の手帳)の取得方法は次の通りです。お住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口に相談します。児童相談所(18歳未満の場合)または知的障害者更生相談所(18歳以上の場合)で判定を受けます。判定には予約が必要な場合が多いので、早めに連絡してください。判定の結果、知的障害があると認められた場合、市区町村の窓口に申請書、顔写真、マイナンバーがわかるものなどを提出します。療育手帳が交付されます。療育手帳は、障害の程度により等級が分かれています。自治体により等級の区分や呼称が異なる場合があります。
戦傷病者手帳の取得方法は次の通りです。都道府県の戦傷病者援護担当窓口に相談します。申請書、診断書、戦傷病の原因となった事実を証明する書類などを準備します。都道府県の窓口に申請書類を提出します。国(厚生労働省)で審査が行われ、認定されると戦傷病者手帳が交付されます。戦傷病者手帳には、特別項症から第6項症までの等級があります。
税務署や自治体への相談方法
障害者控除の申請について不明な点がある場合は、税務署や市区町村の窓口に相談することができます。
税務署への相談については、障害者控除の税務上の取り扱いについて、お住まいの地域を管轄する税務署に相談することができます。税務署には納税相談窓口が設けられており、電話または窓口で相談することができます。税務署の電話番号は、国税庁のウェブサイトで確認できます。確定申告の時期(2月16日から3月15日)には、税務署内や各地の会場で確定申告の相談会が開催されます。この時期には、障害者控除の記入方法についても相談できます。
国税庁のウェブサイトには、タックスアンサーという税に関する質問と回答のコーナーがあります。障害者控除についての基本的な情報を確認できます。電話での相談は、国税庁の電話相談センター(0570-00-5901)でも受け付けています。自動音声案内に従って操作すると、税務相談の担当者につながります。
市区町村への相談については、障害者控除対象者認定書に関してお住まいの市区町村の窓口に相談します。高齢者福祉課、介護保険課、障害福祉課などが窓口となっている場合が多いです。自治体によって担当部署が異なりますので、代表電話に問い合わせて担当部署を確認してください。多くの自治体では、ウェブサイトに障害者控除対象者認定書についての情報が掲載されています。申請書のダウンロードや、認定の基準、必要書類などが確認できます。
専門家への相談も選択肢の一つです。複雑な税務相談については、税理士などの専門家に相談することも検討できます。税理士は、税に関する専門的な知識を持っており、個別の状況に応じたアドバイスを受けることができます。税理士への相談は有料となる場合が多いですが、初回相談は無料という事務所もあります。確定申告の時期には、税理士会が無料の税務相談会を開催している場合があります。お住まいの地域の税理士会に問い合わせてみてください。
また、社会福祉士やケアマネジャーなどの福祉の専門家も、障害者控除対象者認定書の申請について情報を持っている場合があります。介護サービスを利用している場合は、担当のケアマネジャーに相談してみるのもよいでしょう。
よくある質問への回答
障害者控除についてよくある質問とその回答をまとめました。
質問:障害者控除は自動的に適用されますか
回答:いいえ、障害者控除は自動的には適用されません。年末調整または確定申告で必ず申請する必要があります。条件を満たしていても申請しなければ控除を受けることができませんので、忘れずに申請しましょう。
質問:障害者手帳を持っていませんが、障害者控除を受けることはできますか
回答:65歳以上で要介護認定を受けている場合、市区町村から障害者控除対象者認定書の交付を受けることで、障害者控除を受けられる可能性があります。市区町村の窓口に相談してください。身体障害者手帳などがなくても、この認定書があれば障害者控除を申請できます。
質問:年の途中で障害者手帳を取得しました。その年の障害者控除は受けられますか
回答:はい、受けられます。障害者控除は、その年の12月31日の現況で判定しますので、年の途中で取得した場合でも、12月31日時点で手帳を持っていれば、その年分の控除を受けることができます。年末調整または確定申告で申請してください。
質問:扶養している父親が障害者です。父親の所得が多い場合でも障害者控除を受けられますか
回答:扶養親族が障害者の場合、その方の合計所得金額が48万円以下であることが条件となります。所得が48万円を超える場合は、扶養親族として障害者控除の対象とはなりません。ただし、父親本人が確定申告をする際に、自分自身の障害者控除を申請することは可能です。
質問:障害者控除を受けると、いくら税金が戻ってきますか
回答:還付される税金の額は、所得金額や他の控除の状況によって異なります。一般的には、控除額に税率を掛けた金額が還付されます。例えば、税率10パーセントの方が一般の障害者控除27万円を受けた場合、約2万7千円の所得税還付が見込まれます。さらに住民税も軽減されますので、実際の節税効果はより大きくなります。
質問:過去に障害者控除の申請を忘れていました。今からでも申請できますか
回答:はい、できます。5年以内であれば、更正の請求を行うことで、過去に納めすぎていた税金の還付を受けることができます。税務署に相談して、更正の請求書を提出してください。過去5年分まで遡って申告できますので、該当する年度の還付を受けることが可能です。
質問:同居していない親を扶養していますが、親が障害者の場合、同居特別障害者の控除を受けられますか
回答:いいえ、受けられません。同居特別障害者の控除を受けるためには、納税者本人、配偶者、生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としていることが必要です。同居していない場合は、通常の特別障害者控除(40万円)となります。
質問:身体障害者手帳の交付を申請中です。まだ手帳が届いていませんが、障害者控除を受けられますか
回答:身体障害者手帳などの交付を申請中である場合でも、交付を受けるための医師の診断書を有していることにより、障害者控除の適用を受けることができる場合があります。診断書のコピーなどを準備して、詳しくは税務署にご相談ください。
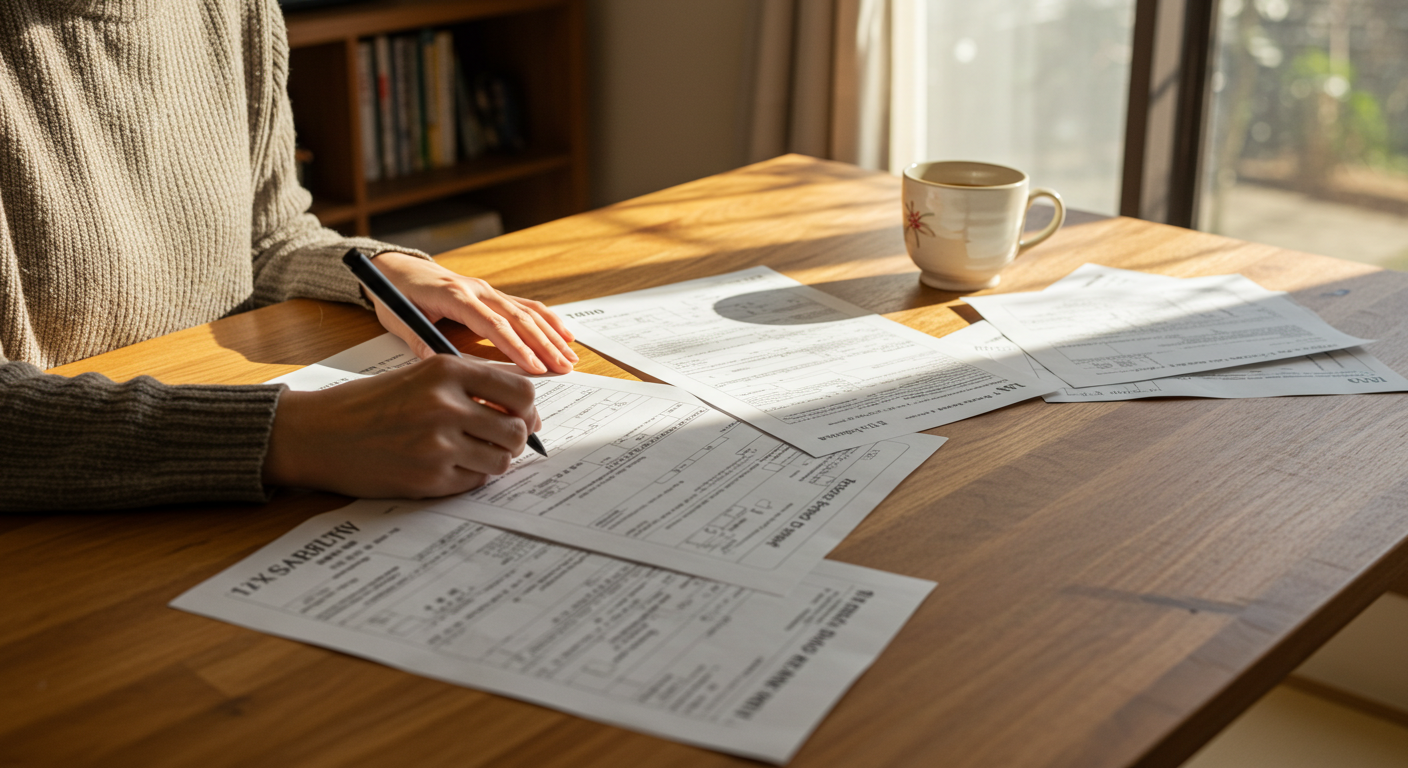


コメント